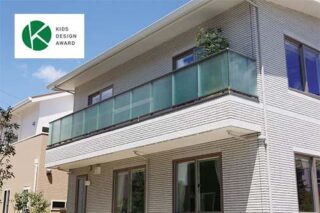この記事はメグリエ運営事務局によって作成しました。
「水害に強いハウスメーカーはどこ?」「水害の多い地域で家づくりをする際のポイントや注意点は?」といった疑問をお持ちでしょうか?日本の住宅は耐震性能にばかり目が行きがちですが、津波や河川の氾濫、台風など、意外に水害も多く発生しています。そのため、家づくりにおいても、水害への対策は非常に重要なポイントとなるでしょう。
今回は、水害に強いおすすめのハウスメーカーを5つ紹介し、その特徴や水害対策などについて解説します。水害に強い家づくりのポイントや、水害被害に遭わないための土地選びなどについてもお伝えしていますので、ぜひ参考にしてみてください。
水害に強いハウスメーカー
まずは、水害に強いおすすめのハウスメーカーを5つ紹介します。水害に強いといえる理由や、その特徴や仕組みを解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
一条工務店

一条工務店は、「家の性能をとことん追求する姿勢」が強みのハウスメーカーです。特に断熱性や気密性に定評がありますが、水害への備えにも真剣に取り組んでいます。
「耐水害住宅」という仕組みが特徴的であり、浸水や逆流、水没、建物が浮いてしまうといったリスクに対して、細かく対策を講じています。床下換気口には水が入ると自動で閉まるフロート弁を取りつけたり、外壁や窓・玄関ドアの隙間から水が入らないように高い水密性を確保したりと、さまざまな工夫がされているのです。
また、排水管には逆流防止弁が取り付けられ、汚水が戻ってくるのを防ぎます。さらに、エアコンの室外機やエコキュートなどの設備を高い位置に設置することで、水に浸かりにくい構造になっています。
特にユニークなのが「建物をあえて浮かせる」という発想です。敷地内に設置されたポールと係留装置を使って、大きな水害の時には家を浮かせ、壊れたり、流されたりするのを防ぐ仕組みが採用されています。
また、水害対策以外でも次のようなメリットがあります。
- 省エネ性能が高い
- 高気密・高断熱性能で快適
- 耐震性能に優れている
- 標準仕様が重質していてコストパフォーマンスが高い
- 長期保証付きの手厚いアフターサービスが受けられる
断熱性・気密性に優れていることで、夏は涼しく、冬はあたたかい室内環境をキープできます。冷暖房の使用を減らせるため、毎月の光熱費も抑えられます。そしてこの「高気密・高断熱」の性能が、快適な暮らしに直結します。家の中の温度差が少なくなるため、どの部屋にいても過ごしやすくなるでしょう。
耐震性にも定評があり、揺れに強い構造で建てられているというのは大きな安心材料です。また、一条工務店は「標準仕様」がとても充実しており、一般的にはオプション扱いになるような設備や仕様が、最初から付いてくるケースが多いため、結果的なコストを抑えて高性能な家が手に入ります。
これらを踏まえ、一条工務店は水害対策をしつつ、「長く快適に安心して住みたい」という人にとって、魅力的な選択肢と言えるでしょう。
一条工務店についてより詳しく知りたい方は、「まかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】」でまかろにおが一条工務店について詳しく解説しているこちらの動画をチェックしてみてください。
セキスイハイム
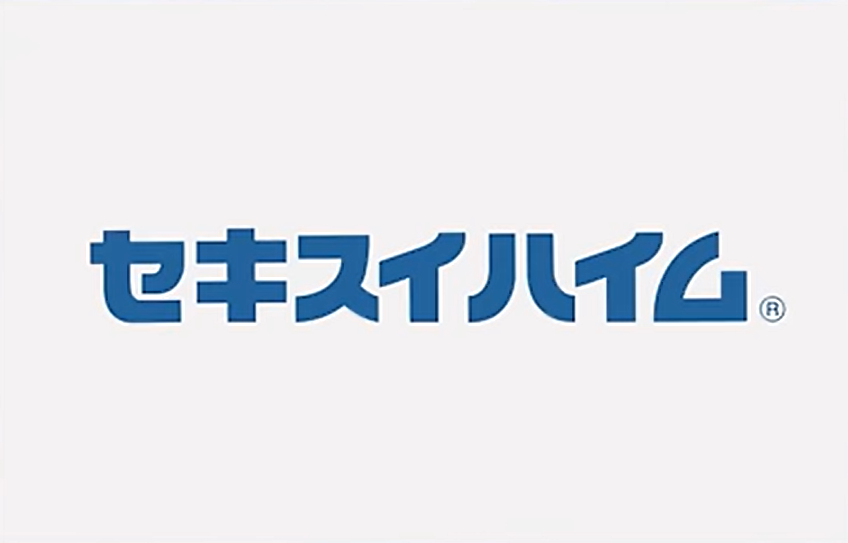
セキスイハイムは、住宅の一部を工場であらかじめ作ってから現場で組み立てる「ユニット工法」が特徴のハウスメーカーです。耐久性や安心感を重視していて、長期保証制度も整っています。
水害に対しては「レジリエンス(回復力)」という考え方のもと、さまざまな災害に対応できる家づくりを進めています。たとえば、電気設備や給湯器などは高い場所に設置するように設計し、万が一浸水しても設備が壊れにくくなっています。
オプションとして、断水時でも水が使えるように基礎の中に飲料水を貯めておけるシステムや、エコキュートの水を生活用水に使う仕組みも用意されていることも特徴的です。
建物自体は、地震にも強い基礎と強固な構造で作られているため、外からの力にも耐えやすく、水害に対しても安心感があります。また、「特定設備水災補償特約」という保険オプションが用意されていて、水で壊れた機器の修理費などをカバーできます。
必要な対策をいろいろと組み合わせることで、水害だけでなく他の災害にも強い住宅を実現しているのが魅力です。
また、その他のメリットとして、下記なども挙げられるでしょう。
- 耐震性能が高い
- 工期が短い
- メンテナンスがしやすい
- 60年間のアフターサポートがある
- 高品質な設備や資材が標準仕様
ユニット工法により耐震性能が非常に高く、面で支えるため、倒壊のリスクが少ないです。また、ユニットを組み合わせる工法は現場作業の工数が少なく、工期が比較的短いのもメリットといえるでしょう。
構造的にメンテナンスがしやすいため、60年間のアフターサポートが用意されているのも強みです。坪単価は高めですが、標準仕様でも十分に高性能なので、オプション費用がかさむ心配も比較的少ないです。
セキスイハイムについてより詳しく知りたい場合は、「まかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】」でまかろにおがセキスイハイムについて詳しく解説しているこちらの動画をチェックしてみてください。
ヘーベルハウス
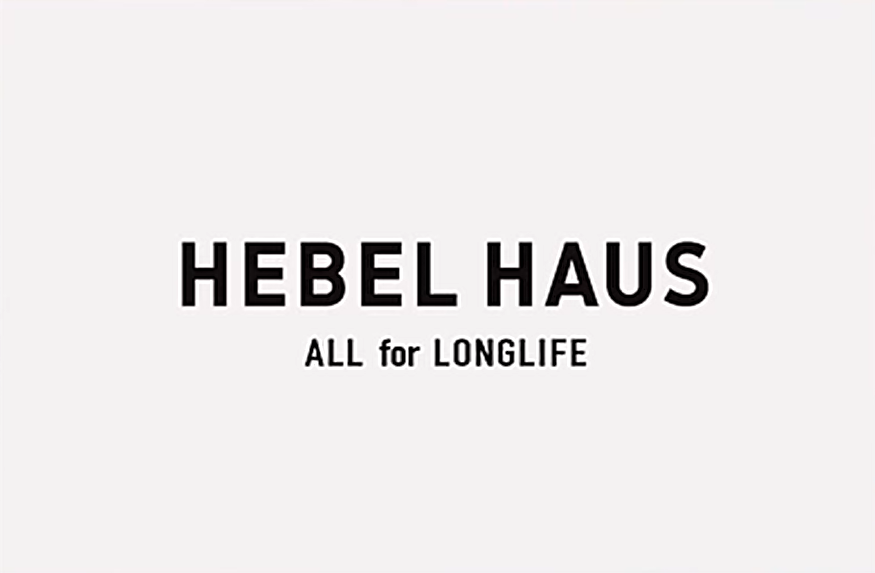
ヘーベルハウスは、軽量気泡コンクリート(ALC)という特殊な素材を使った外壁が特徴の住宅ブランドです。この素材は耐火性や耐久性が高いだけでなく、水にも強く、長期間にわたって劣化しにくいという利点があります。
防水対策も徹底されており、外壁には多層の塗装を施し、屋上部分には耐久性の高い防水シートを採用しています。これにより、雨水が住宅内部に侵入しにくい構造になっていることが特徴です。
さらに、ヘーベルハウス独自の「ヘーベル災害保険」では、水害によって建物が浸水した場合でも修理費用をカバーしてくれるプランが用意されています。一般的な保険では補償されにくい床下や床上の浸水被害も対象になるため、安心感があるでしょう。
ただし、ALC外壁の防水性能は、定期的なメンテナンスが求められます。長く安心して住み続けるためには、点検や補修をきちんと行うことが大切です。
また、ヘーベルハウスは防水対策以外でも、次のような面で優れています。
- 耐震性・耐火性に優れている
- 遮音性に優れている
- 築60年の耐久性を誇る
- 独自の構法により高い断熱性能を実現
- 60年間のアフターサービスやメンテナンスを受けられる
ヘーベルハウスは、地震や火災に強い家づくりが得意なハウスメーカーです。独自の「ヘーベル板」という素材を使うことで、耐震性・耐火性はもちろん、遮音性や断熱性も高いレベルを実現しています。
建物の耐久性も非常に高く、なんと築60年を想定した設計になっています。さらに、長期にわたる点検・メンテナンスがしっかり用意されているので、安心して暮らすことができます。
ヘーベルハウスについては、「まかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】」でまかろにおがヘーベルハウスについて詳しく解説しているこちらの動画をチェックしてみてください。
ユニバーサルホーム
ユニバーサルホームは、独自の「地熱床システム」が大きな特徴です。床下に空間を作らず、地面と床の間をコンクリートで密閉しているため、そもそも床下浸水が起こらない構造になっています。
この構造は、水害に強いだけでなく、湿気やシロアリにも強く、断熱性にも優れています。外壁にはALCという耐水性のある素材がよく使われており、建物全体としても災害に強い設計です。
ただし、床下収納が作れない点や、外壁のメンテナンスが必要になることもあるので、そのあたりは事前にチェックしておくと安心です。
ヤマダホームズ
ヤマダホームズでは、「水害対策仕様」をすべての住宅にオプションで追加することができます。浸水の可能性に応じて、止水板の設置や基礎の止水処理、設備の高所設置など、柔軟な対策が取れるのがポイントです。
また、1階と2階で分電盤を分けたり、避難スペースになる小屋裏収納を提案したりするなど、災害時の過ごしやすさにも配慮されています。専用の災害保険も用意されており、経済的な備えも整えやすくなっています。
コストと機能のバランスを重視したい人にとって、選びやすいハウスメーカーです。
水害に強いハウスメーカーやその最新情報などを詳しく知りたい方は、元大手ハウスメーカー勤務で登録者10万人以上の住宅系YouTuber「まかろにお」が解説する「まかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】」の視聴がおすすめです。
各ハウスメーカーのトップ営業マンから仕入れた生の情報や、過去の無料相談で蓄積したリアルな悩みやその解決策などをお伝えしています。
水害に強い家づくりのポイント

水害に強い家を作るためには、ハウスメーカー選びだけではなく、家づくりの工夫も大切です。具体的には、次のようなポイントを意識することで、より水害に強い家づくりが可能となるでしょう。
もちろん、すべてを採用する必要はありませんが、土地の特性などに併せて検討してみてください。ここでは、各ポイントについて、詳細をお伝えします。
盛土する
盛土とは、建物の周囲や敷地内に土を盛り上げることで、土地の標高を人工的に高くする工法です。敷地全体の高さが上がるため、洪水でも浸水のリスクを低くすることができます。
また、盛土を適切に行うことで、地盤の均一性が向上し、建物の安定性が増すこともメリットです。盛土の形状を工夫することで、雨水が効率よく流れる勾配を作ることも可能なため、水はけの良い土地に整えることもできます。
特に、低地や周囲の地形が平坦で水が溜まりやすい地域、または河川や用水路の近くに位置する土地などにおいては、盛土の恩恵が多く得られるでしょう。ただし、盛土を行う際は、土の種類や圧密状態、排水計画を十分に検討することが重要です。
高床にする
高床とは、建物の床面を地面から持ち上げ、基礎部分を高く設計する構造のことです。伝統的な日本家屋では、湿気対策として用いられてきた手法でもあります。
地面から離れた位置に建物を構築するため、洪水時や浸水時にも家屋自体が水に直接触れるリスクが減ります。また、床下に隙間を設けることで、湿気がこもらず、カビや腐食のリスクも低減できるでしょう。
メンテナンスもしやすく、建物を長持ちさせやすくなるメリットもあります。また、基礎部分に防水シートや排水設備を組み合わせることで、さらなる水害対策を施すことが可能です。
高い塀や壁で家を囲む
高い塀や壁は、外部からの水流を直接遮断するバリアとして機能します。洪水や急激な増水が発生した場合、これらが障壁の役割を果たし、水の侵入を防ぐことができます。建物周辺の水位をコントロールし、急激な水の勢いを緩和することで、浸水被害を最小限に抑えられるでしょう。
また、プライバシーの保護や防犯性の観点からもおすすめできます。特に住宅が隣接するような地域では、周囲の住宅との境界線になり、近隣トラブルもおきづらいでしょう。やや施工コストはかかりますが、予算に余裕がある場合はおすすめできます。
防水性の高い建物にする
防水性の高い建物とは、外部からの水の侵入を徹底的に防ぐ設計と施工がなされている建物です。具体的には、壁や屋根、窓、基礎部分において、水が侵入しにくい素材や構造、シーリング処理が施されていることが求められます。
また、内部の水害対策として、床下の防湿層や防水シート、排水システムが完備されていることもポイントです。防水対策は、初期投資としてのコストが発生しますが、長期的な視点で見れば水害による被害を未然に防ぐため、メンテナンス費用や修繕費用を考慮すれば、トータルではメリットが大きいです。
特に水害の多い地域では、防水性の高さは非常に重要なポイントといえるでしょう。
水害被害に遭いやすい土地の特徴
水害で家に被害が及ぶ自体を避けるためには、そもそも水害の多い土地を選ばないようにすることも大切です。もしまだ土地が決まっていない場合は、次のような土地を避けることで、水害被害に遭うリスクを減らせます。
ここでは、それぞれの特徴などについて詳細を解説します。
埋立地
埋立地は、もともと水辺であった場所を人工的に陸地化した地域です。このような土地は、自然な地盤の強度が失われがちで、次のような特徴があります。
- 地盤が弱い
- 浸水しやすい
- 地盤沈下のリスクがある
埋立地は自然の土壌とは異なり、人工的な資材が使用されることも多いため、地盤が弱くなりやすいです。地盤の弱さや排水機能の低下により、雨水がスムーズに流れず、浸水リスクが高まります。
また、時間の経過とともに、地盤沈下が進む可能性があり、これにより排水能力がさらに低下し、水害時の被害が拡大することもあるでしょう。
このような埋立地を避け、自然の地盤がしっかりしている場所、または地盤改良工事がすでに行われた土地を選ぶのがおすすめです。
海や河川の近く
海や河川の近くは自然の水の動きに大きく影響されるため、水害のリスクが特に高いエリアです。特に海の高潮や河川の氾濫によるリスクがあり、台風の影響も受けやすいです。
このような地域では堤防や排水設備にも力を入れてはいますが、それでも限界はあります。想定を超える雨量や地形上の制約により、被害が拡大することもあるでしょう。
海や川に近いと、日常的に水位の変動があるため、土地自体が常に湿気を帯びやすく、浸水のリスクも高くなりがちです。自然の排水機能が働きやすい標高差がある土地や、河川から離れた地域を選ぶことで、水害リスクを減らすことができます。
ハザードマップの危険区域
自治体が作成・公開しているハザードマップは、地域ごとの水害リスクを把握するために重要です。これらのマップには、次の情報が示されていることが多いです。
- 浸水想定区域
- 洪水危険エリア
大雨時や洪水時に実際に浸水が予測される地域、河川の氾濫や高潮のリスクが高い地域などが示されており、土地選びの際の重要な判断材料となります。
逆にハザードマップ上で安全とされているエリアを選ぶことで、水害被害を避けやすくなるでしょう。
このような家づくりの注意点やその対策について知っておきたい方は、YouTubeチャンネル「まかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】」の視聴がおすすめです。当チャンネルは、『人から始める家造りの重要性を世に広める』をコンセプトとした住宅系YouTuber「まかろにお」が運営しています。2025年3月現在で登録者は約13万人を超え、住宅系チャンネルの中では最大規模です。家づくりやハウスメーカーについて勉強しておくことで、より失敗やトラブルのリスクを減らすことができるでしょう。
水害に備えて覚えておくべき補償制度

そもそも水害に遭わないことが理想的ですが、自然災害である以上、必ずしも避けられるとは限りません。そのため、万が一の時のために、補償制度を確認しておくことも重要です。
各ハウスメーカーの補償を確認するのはもちろん、下記のような補償についても把握しておきましょう。
それぞれ詳細をお伝えします。
火災保険の補償
火災保険には、通常の火災リスクに加えて「水災補償」が付帯できるプランがあります。水害による被害をカバーするため、適用範囲や補償内容をしっかり確認することが大切です。
また、すべての火災保険に水災補償が自動的に含まれているわけではありません。契約内容を詳細にチェックし、必要に応じてオプションとして追加する必要があるでしょう。
災害発生時にスムーズな補償申請を行うためにも、契約前や更新時に水災補償の有無、補償限度額、免責事項などをしっかりと確認しておくことが大切です。
国の支援金・補償
大規模な水害が発生した場合、国や自治体から「被災者生活再建支援金」や「災害救助法」に基づく支援など、さまざまな支援金や補償が受けられるケースがあります。これらの支援は、被災後の生活再建や一時的な経済的困難の際に手助けとなるため、軽くでも確認しておきましょう。
また、支援制度を利用するには、一定の条件を満たし、所定の手続きを経る必要があることが多いです。いざという時のために仕組みを知っておき、家づくりの関連書類なども大切に保管しておきましょう。
まとめ
水害に強いおすすめのハウスメーカーについて解説しました。また、水害に強い家づくりのポイントや、避けるべき土地などについても紹介しました。
水害が多い地域はなるべく避けることが望ましいですが、すでに土地を持っている、決めているなど、避けられないケースもあるでしょう。しっかりと対策を行うことでリスクを抑えることは十分に可能なため、家を建てる土地の特性にあわせて、家づくりを考えてみましょう。
今回紹介したようなハウスメーカーの情報や家づくりのポイントを知りたい方は、元大手ハウスメーカー勤務で登録者10万人以上の住宅系YouTuber「まかろにお」が解説する「まかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】」を参考にしてみてください。
動画では各ハウスメーカーの優秀な営業マンからもらったリアルな情報をもとにして、役立つコンテンツを多数配信しています。
また、当サイト「メグリエ(MEGULIE)」では、公式LINEを通じた無料相談も実施しています。住宅に関する悩みや質問がある方は、下記のリンクから友だち追加をしていただくと、最新の情報や具体的なアドバイスがリアルタイムで受け取れます。ぜひご活用ください。
家づくりは事前に勉強をしておくことで、後悔することが少なくなります。正しい知識を身につけて、後悔しない理想の住まいを建てられるようにしましょう。