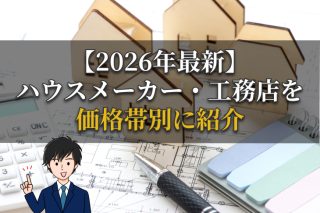この記事はメグリエ運営事務局によって作成しました。
「そろそろ理想の注文住宅を建てたい」と考え始めたものの、調べていくうちに費用の高さに驚いている方も多いのではないでしょうか?「注文住宅はなぜこんなに高い?」「自分たちの予算で本当に建てられる?」そんな不安を感じるのは、当然のことです。しかし、その理由と対策を正しく知れば、闇雲に不安がる必要はありません。
そこで今回は、注文住宅が高い理由をわかりやすく解説するとともに、予算内で理想の家を実現するための具体的なコスト削減術を紹介します。後悔しない家づくりのために、まずは正しい知識から身につけていきましょう。
注文住宅の相場はいくらくらい?

「理想の家を建てたい」と考えたとき、真っ先に気になるのが「一体いくらかかる?」という費用面ではないでしょうか?注文住宅の価格は、建てる場所や家の仕様によって大きく変わります。ここでは、具体的なデータをもとに、注文住宅の費用相場について解説します。
最新データで見る全国の平均建築費用
まずは建物本体にかかる費用から見ていきましょう。住宅金融支援機構の「フラット35利用者調査」によると、注文住宅のみを建てた場合の建築費は、全国平均で3,932万円です。
ただし、この金額は地域によって差があり、首都圏では4,252万円、近畿圏では4,118万円と、都市部の方が高くなる傾向が見られます。まずはこの全国平均を一つの目安として捉え、ご自身が家を建てたいエリアの相場はどのくらいなのかを意識することが大切です。
土地代を含めた総額の全国平均
土地もセットで購入する場合、費用総額はさらに大きく変わります。
先ほど紹介した住宅金融支援機構の「フラット35利用者調査」では、土地付き注文住宅の購入にかかった費用の全国平均は5,007万円でした。つまり、建物代とは別に、土地代だけで1,000万円以上の費用がかかる計算になります。土地の価格はエリアによる差が非常に大きく、都心部と郊外では数倍以上の価格差が生まれることも珍しくありません。
見落としがちな本体工事費以外の費用内訳
注文住宅の総費用は、建物そのものの「本体工事費」だけで収まらない点に注意しましょう。総費用は「本体工事費」「付帯工事費」「諸費用」の3つで構成されています。
付帯工事費は外構や地盤改良など、諸費用は登記費用やローン手数料などで、これらが総額の2〜3割を占めます。これらの費用を見込んでいないと、後から数百万円単位での予算オーバーにつながるため、あらかじめ総額の内訳を理解しておくことが不可欠です。
予算オーバーしやすい追加費用
計画的に進めても、契約後に追加費用が発生して予算オーバーにつながるケースは少なくありません。
代表的なものが、土地の調査後に必要性が判明する地盤改良工事費です。また、打ち合わせを重ねるうちに「キッチンのグレードを上げたい」「壁紙をおしゃれなものにしたい」といったこだわりが生まれ、オプション費用が膨らむことも主な原因です。
こうした不測の事態に備え、契約前に何に追加料金がかかるのかよく確認しておくことが重要です。
注文住宅の価格が高い理由

「昔よりも家の値段が上がった」と感じる方は多いかもしれません。その感覚は正しく、近年、注文住宅の価格はさまざまな要因が重なって高騰しています。ここでは、注文住宅が高くなっている主な理由について解説します。
世界的なウッドショックの影響
注文住宅の価格高騰の大きな要因の一つが「ウッドショック」です。これは、コロナ禍からの経済回復に伴い、世界中で住宅建設の需要が急増したことで木材が不足し、価格が高騰した現象を指します。
アメリカや中国の旺盛な需要に加え、コンテナ不足による海上輸送の混乱や輸送コストの上昇も、木材価格をさらに押し上げました。国内でも国産材への切り替えが進められていますが、供給が需要に追いつかず、すぐには価格が安定しにくい状況が続いています。
アイアンショックによる資材価格の上昇
住宅価格を押し上げているのは、木材だけではありません。「アイアンショック」と呼ばれる鉄骨やアルミサッシといった金属資材の価格高騰も深刻です。鉄鉱石などの原材料価格の上昇に加え、ウクライナ情勢などを背景とした世界的なエネルギーコストの上昇が、製品価格に影響を与えています。
この影響は、キッチンやユニットバス、給湯器といった住宅設備にも及んでおり、メーカー各社が相次いで値上げを発表しているのが現状です。
深刻化する建築業界の人手不足
建築現場で働く職人の人手不足も、建築コストを上昇させる大きな要因となっています。
長年にわたって、建設業界では職人の高齢化と若手の担い手不足が問題視されてきました。限られた人材を確保するため、人件費、いわゆる労務単価は年々上昇を続けています。
この傾向は今後も続くと見られており、設計や工事にかかる人件費が建築コスト全体に反映されるため、住宅価格が下がりにくい構造的な問題を抱えています。
最新の省エネ基準への対応コスト
住宅に求められる性能が向上していることも、価格上昇の一因です。
特に、2025年4月からはすべての新築住宅に対して「省エネ基準」への適合が義務化されています。これにより、断熱性能の高い窓や壁の断熱材、エネルギー効率の良い換気システムなどの導入が必須となりました。
注文住宅の価格高騰はいつまで続くのか

これからの家づくりを考える上で「この価格高騰はいつ落ち着くのか」「今建てるべきか、待つべきか」という点は、誰もが悩む大きな問題です。建築費の動向だけではなく、住宅ローン金利の動きも総支払額に大きく影響するため、両方の視点から見極める必要があります。
ここでは、今後の価格の見通しと、家を建てるタイミングを考える上で重要な「待つ」ことのメリット・デメリットについて解説します。
価格はすぐには下がりにくい
結論からお伝えすると、注文住宅の価格がすぐに下がる可能性は低いと考えられます。
ウッドショックのピーク時に比べ、一部の資材価格は落ち着きを見せていますが、人件費やエネルギーコストは依然として上昇傾向にあります。加えて、不安定な世界情勢や円安の影響も無視できません。
こうした複合的な要因から、専門家の間でも、住宅価格は今後も高止まりするか、緩やかに上昇を続けるという見方が大勢を占めており、急激な価格下落は期待しにくい状況です。
住宅ローン金利の今後の動向
住宅購入の総額を左右するもう一つの要素が、住宅ローン金利です。長らく続いた日本の超低金利政策は転換期を迎え、長期金利に連動する固定金利はすでに上昇傾向にあります。
低水準で推移している変動金利も、将来的に上昇するリスクを抱えています。建築費だけではなく、金利の動きも重要な判断材料です。
「待つ」ことのメリット・デメリット
価格高騰を受けて「建築価格が下がるまで待つ」という選択肢には、メリットとデメリットの両面があります。
メリットは、価格が下がる可能性に期待できる点や、その間に自己資金を貯められることです。
一方、デメリットは、待っている間に住宅ローン金利が上昇してしまうリスクや、ご自身の年齢が上がることでローン返済期間が短くなったり、審査が厳しくなったりする可能性が挙げられます。
現在の家賃を払い続けるコストも無視できません。これらの要素を天秤にかけ、ご自身のライフプランに合った総合的な判断が求められます。
高すぎる注文住宅の費用を抑えるコツ
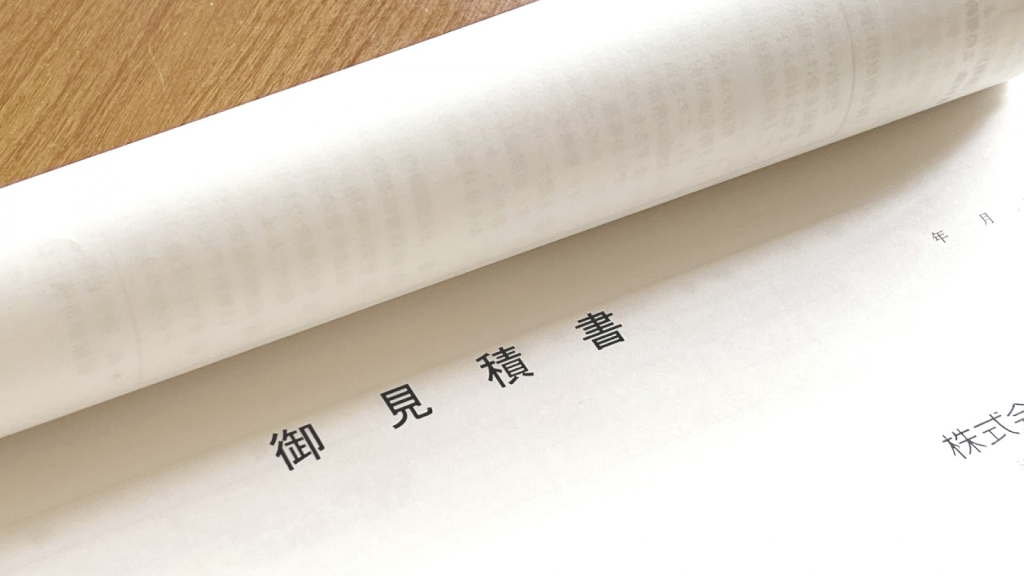
注文住宅の価格が高騰している中でも、工夫次第で費用を抑え、予算内で理想の家を建てることは可能です。ポイントは、設計の工夫から設備の選び方、さらには制度の活用まで、あらゆる角度からコストを見直すことです。ここでは、今日から実践できる具体的な9つのコツを解説します。
- 建物の形状をシンプルにする
- 部屋数を減らし間仕切りをなくす
- 窓の数やサイズを見直す
- 水回りの設備を1箇所に集中させる
- こだわる部分と諦める部分にメリハリをつける
- 外構工事の費用を計画的に削減する
- 規格住宅という選択肢を検討する
- 複数の会社から見積もりを取る
- 補助金や優遇制度を最大限活用する
建物の形状をシンプルにする
建物の形状は、建築コストに直接影響します。
コスト効率が良いのは、凹凸のない正方形や長方形の箱型で、屋根の形もシンプルな「総二階建て」です。反対に、L字型やコの字型など複雑な形状の家は、壁や屋根の面積が増え、角の部分の処理に手間がかかるため、材料費も人件費も割高になります。
部屋数を減らし間仕切りをなくす
コストダウンの有効な手段として、間仕切り壁を減らすことも挙げられます。壁やドアの数が減れば、その分の材料費や工事費をシンプルに削減できます。
たとえば、LDKを一つの大きな空間にしたり、子ども部屋を最初は大きな一部屋にしておき、将来必要になったら間仕切りを追加できるような設計にしたりするのも良い方法です。
なお、リビングの間取り設計について詳しく知りたい方は、住宅系YouTuberの「まかろにお」が運営する「まかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】」内の「【間取り解説】最悪なリビングの特徴3選と解決策」を参考にしてください。
運営者である「まかろにお」は、『人から始める家造りの重要性を世に広める』をコンセプトとした住宅系YouTuberです。元ハウスメーカー営業担当者として全国1位の営業成績を誇り、その後も不動産融資を扱う大手金融機関での実務経験を経て、幅広いハウスメーカー事情に精通しています。
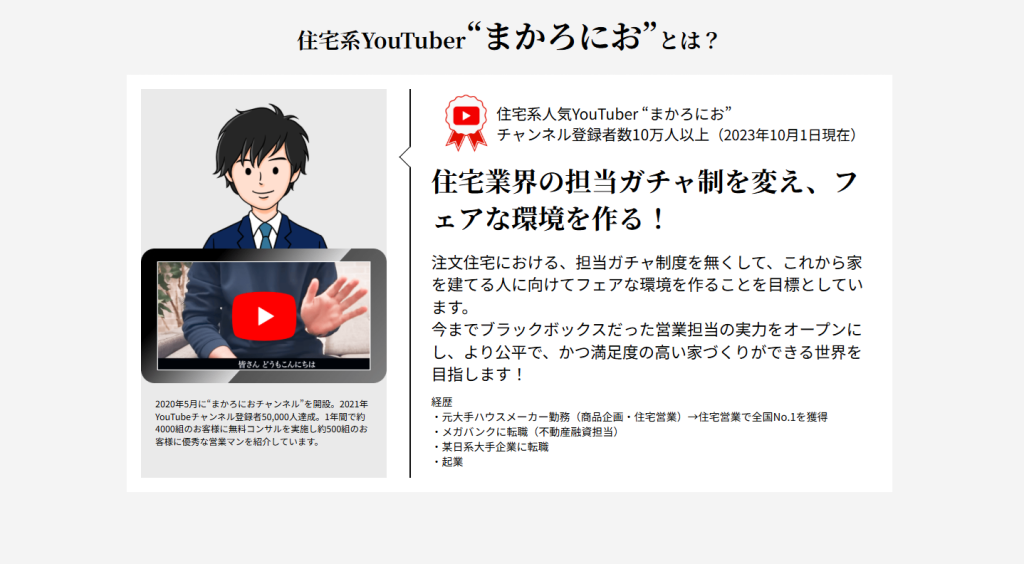
大手ハウスメーカーの特徴やメリット、デメリット、さらに注文住宅を建てる前に知っておきたい知識を中立的な立場で発信しています。
窓の数やサイズを見直す
窓は、実は壁よりもコストがかかるパーツです。特に大きな窓やデザイン性の高い窓は価格が上がり、数が増えればそれだけ費用もかさみます。
また、窓は家の断熱性能にも大きく影響する部分です。コストを抑えるには、本当に必要な窓を見極めることが大切です。
水回りの設備を1箇所に集中させる
キッチン、浴室、洗面所、トイレといった水回りの設備を、できるだけ近い場所にまとめることもコスト削減に大きく貢献します。
設備が集中していると、給水管や排水管の長さを短くできるため、配管工事の費用を大幅に抑えることが可能です。特に2階にトイレを設置する場合は、1階の水回りの真上に配置するといった工夫が有効です。
こだわる部分と諦める部分にメリハリをつける
予算内で理想の家を建てるには「選択と集中」が不可欠です。家族で話し合い「絶対に譲れないこだわりポイント」と「ここは妥協しても良い」という部分を明確にしましょう。すべての希望を100%叶えようとすると、予算はあっという間にオーバーしてしまいます。
なお、こだわるべき床材について詳しく知りたい方は、住宅系YouTuberの「まかろにお」が運営する「まかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】」内の「【地雷】後悔する床材とおすすめの床材」を参考にしてください。
外構工事の費用を計画的に削減する
駐車場やアプローチ、フェンスといった外構工事はつい後回しにしがちですが、総費用の1割近くを占めることもある重要な項目です。ここを計画的に削減するのも一つの手です。建物と同時に外構計画を進めることで、土の処理などで無駄な費用が発生することを防ぐこともできます。
なお、外構計画の失敗パターンについて詳しく知りたい方は、住宅系YouTuberの「まかろにお」が運営する「まかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】」内の「【続編】注文住宅の外構計画で失敗する場合の特徴と具体例3選」を参考にしてください。
規格住宅という選択肢を検討する
フルオーダーの注文住宅と建売住宅の中間的な選択肢として「規格住宅」があります。
規格住宅は、ハウスメーカーが用意した複数のプランやデザイン、仕様の中から好みのものを選んで組み合わせる建築スタイルです。ある程度デザインの制約はありますが、その分、建材の一括仕入れなどでコストが抑えられており、フルオーダーよりも安価に建てられます。
複数の会社から見積もりを取る
家づくりを依頼する会社を決める際は、必ず複数の会社から見積もりを取りましょう。これは「相見積もり」と呼ばれ、最低でも3社以上から同程度の条件で見積書を出してもらうことが鉄則です。
各ハウスメーカーの価格を比較できるだけではなく、提案内容や設計プラン、営業担当者の対応まで総合的に判断する材料になります。
補助金や優遇制度を最大限活用する
国や自治体は、住宅取得を支援するためにさまざまな補助金や優遇制度を用意しています。これらを活用しない手はありません。
また、年末のローン残高に応じて所得税が控除される「住宅ローン控除」も大きな節税につながります。利用できる制度はもれなく調べ、最大限活用しましょう。
注文住宅の価格に関するよくある質問

注文住宅の費用について考えると、さまざまな疑問が浮かんでくるものです。「価格は今後どうなる?」「坪単価は信用できる?」「値引きは可能?」など、多くの人が抱く共通の悩みや疑問があります。
最後に、注文住宅の価格に関して特によく寄せられる質問と、その回答を紹介します。
注文住宅の価格は今後下がる見込みはありますか?
多くの方が気になる点ですが、残念ながら急激な価格下落は考えにくい状況です。一部の建材価格は落ち着く可能性もありますが、職人の人件費や、2025年から義務化される省エネ基準への対応コストは、今後も価格を支える要因となります。また、価格が下がるのを待っている間の家賃負担や、今後の住宅ローン金利が上昇するリスクも考慮しなくてはなりません。
「坪単価」が安いハウスメーカーを選べば総額も安くなりますか?
「坪単価が安い=総額も安い」とは限らないため、注意が必要です。なぜなら、「坪単価」にどの工事費用まで含めるかというルールはなく、ハウスメーカーによって定義がバラバラだからです。坪単価はあくまで大まかな目安と捉え、広告の数字だけで判断するのは避けましょう。
ローコスト住宅が安いのは品質に問題があるからですか?
安いからといって、品質が悪いわけではありません。ローコスト住宅が価格を抑えられる主な理由は、仕様やデザインを規格化して絞り込み、建材や設備を大量に一括発注することでコストダウンを図っているためです。
また、現在の建築基準法では、どの住宅も定められた耐震性や安全性をクリアすることが義務付けられています。そのため、法律で定められた最低限の品質は確保されていると考えて良いでしょう。
注文住宅は値引き交渉はできますか?
値引き交渉自体は可能ですが、何十万円、何百万円といった大幅な金額の値引きは難しい場合がほとんどです。建築費用は材料費や人件費の積み重ねであり、単純に削れる余地が少ないからです。
交渉するなら、金額の値引きよりも「キッチンのグレードを上げてもらう」「食洗機をサービスしてもらう」といった、オプション設備の追加サービスをお願いする方が成功しやすいでしょう。
まとめ
注文住宅の価格は高止まりが続いていますが、費用を抑えるコツはあります。まずは正しい知識を身につけ、予算内で理想の家づくりを計画しましょう。
限られた予算で、後悔しない注文住宅の建て方を動画で学びたい方は、YouTubeチャンネル「まかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】」の動画をチェックして知識を身につけましょう。運営者のまかろにおが、費用を抑えるための具体的なポイントやハウスメーカー選びのコツをわかりやすく解説しています。
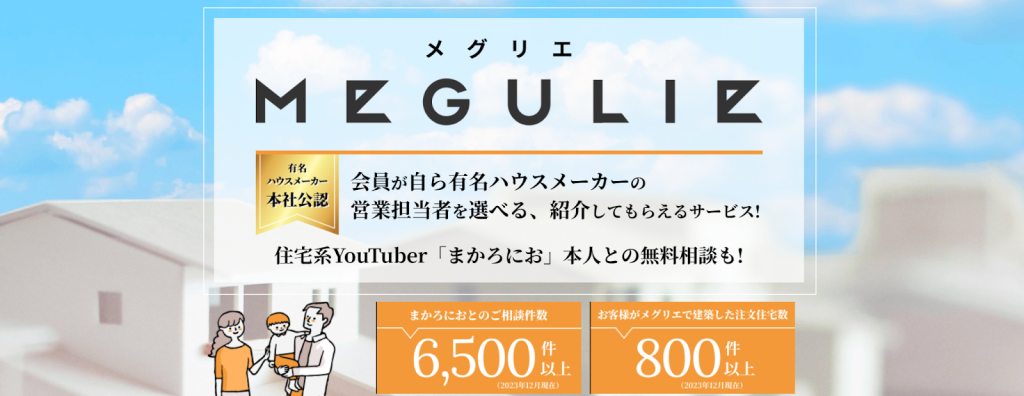
また、当サイト「メグリエ(MEGULIE)」では、家づくりの無料相談をLINEで受け付けています。「自分たちの予算でどこまで理想を叶えられるか知りたい」「利用できる補助金や住宅ローンについて詳しく聞きたい」といった悩みを専門スタッフによる丁寧なサポートで解消できるでしょう。また、リアルタイムでの最新情報を受け取ることができます。
さらに、「メグリエ(MEGULIE)」に掲載されている豊富な建築実例から気になる施工事例を選び、その施工を担当したハウスメーカーや営業担当者に直接依頼することも可能です。信頼できる担当者と出会うことが、予算内で満足度の高い家づくりを実現する近道です。
なお、当サイト「メグリエ(MEGULIE)」を活用するメリット・デメリットは、こちらの動画で詳しく解説しています。一度チェックしてみてください。
一生に一度の大きな買い物だからこそ、焦らず情報収集し、後悔のない選択をしてください。