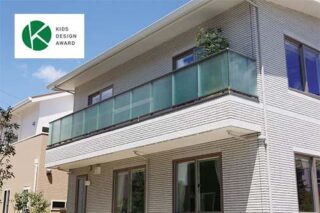この記事はメグリエ運営事務局によって作成しました。
注文住宅を建てるなら、趣味の音楽や映画鑑賞を心ゆくまで楽しみたい、仕事に集中できる静かな空間がほしい。そうした想いを叶えるのが「防音室」です。しかし、専門的な知識が必要なため「何から考えれば良いかわからない」「費用はどれくらい?」「作ってから後悔したくない」といった不安も多いのではないでしょうか?
そこで今回は、注文住宅で防音室をつくる前に知っておきたい遮音・吸音・防振の基礎知識から、具体的なメリット、後悔しがちな失敗例、そして信頼できるハウスメーカーの見極め方まで、わかりやすく解説します。正しい知識を身につけて、理想の空間づくりを成功させましょう。
防音室づくりの基本的な知識

理想の防音室を実現するためには、まず音の特性を理解し、正しい対策の知識を持つことが大切です。一口に「防音」といっても、実は「遮音」「吸音」「防振」という3つの異なるアプローチがあります。
これらをバランス良く組み合わせることで、はじめて快適な音響空間が生まれます。ここでは、後悔しない防音室づくりのカギとなる、それぞれの基本的な仕組みと役割について解説します。
音漏れを防ぐ「遮音」の仕組み
遮音とは、壁やドアといった物体で音を物理的に跳ね返し、外部へ音が漏れるのを防ぐ仕組みのことです。音は空気の振動によって伝わるため、重く密度の高い素材で壁や床を作ることにより、その振動を効果的に遮断できます。たとえば、コンクリートやALC外壁などは遮音性能が高い素材の代表例です。
しかし、どれだけ高性能な素材を使っても、コンセントの穴や換気扇のダクトといったわずかな隙間があると効果は大きく下がってしまいます。そのため、高い施工精度で気密性を確保することが、遮音性能を最大限に引き出すカギとなります。
音の響きを調整する「吸音」の役割
吸音とは、音の反響を吸収して抑え、室内での音の響きを心地良く調整する役割を担います。遮音性能だけを高めた部屋では、音が壁に反射して響きすぎてしまい、会話が聞き取りにくかったり、音楽がクリアに聞こえなかったりすることがあります。
これを解決するのが吸音で、壁の内部にグラスウールのような多孔質な吸音材を入れるのが一般的な手法です。楽器演奏やオーディオルームなど、室内での音の聞こえ方を重視する場合には不可欠な要素といえるでしょう。ハウスメーカーによっては、高性能な断熱材が吸音材の役割を兼ねることもあります。
振動を伝えない「防振」対策
防振とは、音の振動が床や壁を伝って周囲に響くのを防ぐための対策のことです。ドラムの演奏やスピーカーから出る重低音、子どもの走り回る足音などは、空気を伝わる音とは別に、建物の構造体そのものを振動させて伝わっていきます。この「固体伝搬音」は、遮音や吸音だけでは防ぐことが難しいため、専門の対策が必要です。
具体的には、床を二重構造にして間に防振ゴムを挟むといった方法がとられます。特に重低音が発生するドラムやピアノ、ホームシアターなどを楽しみたい場合は、この防振対策が満足度を左右する重要なポイントになります。
なお、床材について詳しく知りたい方は、住宅系YouTuberの「まかろにお」が運営する「まかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】」内の「後【地雷】後悔する床材とおすすめの床材」を参考にしてください。
運営者である「まかろにお」は、『人から始める家造りの重要性を世に広める』をコンセプトとした住宅系YouTuberです。元ハウスメーカー営業マンとして全国1位の営業成績を誇り、その後も不動産融資を扱う大手金融機関での実務経験を経て、幅広いハウスメーカー事情に精通しています。
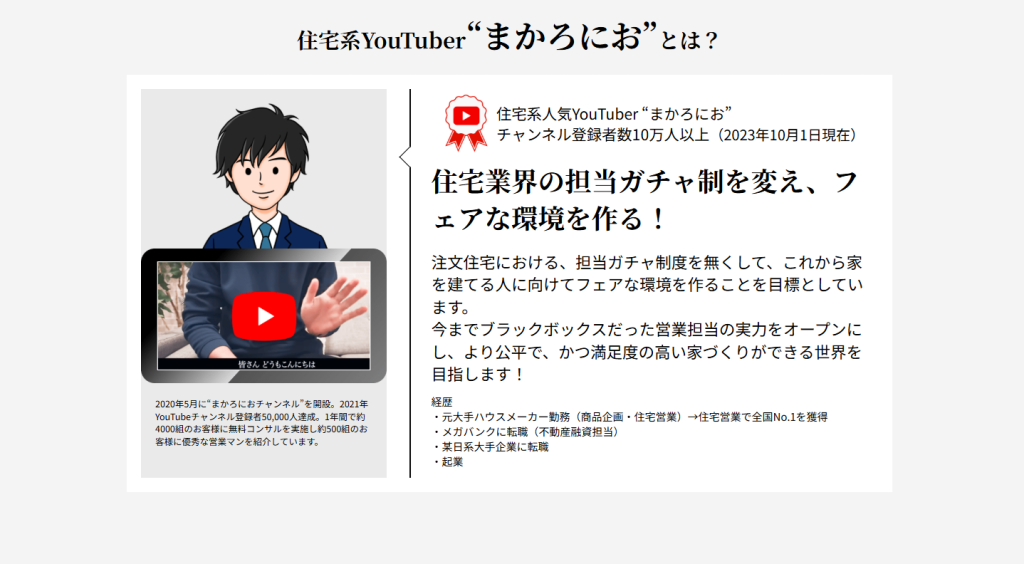
大手ハウスメーカーの特徴やメリット、デメリット、さらに注文住宅を建てる前に知っておきたい知識を中立的な立場で発信しています。
注文住宅に防音室を設ける3つのメリット

注文住宅に防音室をつくることは、単に音の問題を解決するだけではなく、暮らしの質を向上させる多くのメリットをもたらします。趣味や仕事への集中環境が手に入るのはもちろん、家族全員が気兼ねなく過ごせるようになったり、将来的には住まいの資産価値を高める要素になったりすることも期待できます。ここでは、防音室がもたらす3つの具体的なメリットについて解説します。
趣味や仕事に気兼ねなく没頭できる
防音室のメリットは、時間や周囲を気にすることなく、好きなことに思い切り没頭できる空間が手に入ることです。
音漏れの心配がなくなるため、深夜でも気兼ねなく楽器を演奏したり、映画やゲームを迫力のある大音量で楽しんだりできます。また、静かな環境が求められるテレワークや動画配信といった仕事にも最適で、生産性の向上につながるでしょう。
音に関するストレスから解放されることで、家族それぞれが自分の時間を心から満喫できる環境が整い、日々の暮らしがより豊かなものになります。
家族の生活音を気にせず過ごせる
防音室は、室内の音を外に漏らさないだけではなく、外部の音をシャットアウトする効果も高いため、家族全員の快適な暮らしにつながります。
たとえば、小さなお子さまの泣き声やペットの鳴き声がご近所に響く心配を減らせます。同時に、リビングのテレビの音や家族の会話が、書斎として使っている防音室にいる人に聞こえにくくなり、お互いのプライベートが守られるでしょう。
このように、家族が互いに気を遣うことなく過ごせる環境は、近隣トラブルのリスクを減らすだけではなく、家庭内の円満な関係づくりにもつながります。
資産価値の向上につながる可能性がある
適切に設計・施工された防音室は、住宅の付加価値となり、将来の資産価値向上に貢献する可能性があります。
ライフスタイルの多様化に伴い、自宅で音楽や創作活動を楽しみたい人、集中できる仕事部屋を求める人は増えています。そうした特定のニーズを持つ人にとって、本格的な防音室は大きな魅力であり、将来家を売却する際の強力なアピールポイントになるでしょう。
特に、住友林業のような高い施工品質で評価されるハウスメーカーで家を建てることで、その価値はより確かなものとなり、長期的な視点で見た賢い投資といえます。
注文住宅の防音室で後悔しがちな5つの失敗

夢を詰め込んだ防音室のはずが、完成してから「こんなはずではなかった」と後悔するケースは少なくありません。防音性能や費用、居住性といったポイントで思わぬ落とし穴が待ち受けています。ここでは、注文住宅の防音室づくりでよくある5つの失敗例について解説します。
- 思ったより音が漏れてしまい近隣トラブルになる
- 費用をかけすぎて全体の予算を圧迫する
- 部屋の広さや天井高で圧迫感を感じる
- 換気や空調設備を軽視してしまい快適性が低い
- コンセントの位置や数が足りず不便になる
なお、注文住宅の使用や間取りについて詳しく知りたい方は、住宅系YouTuberの「まかろにお」が運営する「まかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】」内の「注文住宅でおすすめしない仕様と間取り4選【ハウスメーカー】」を参考にしてください。
思ったより音が漏れてしまい近隣トラブルになる
防音室づくりの失敗で最も避けたいのが、完成後に音が漏れてしまうことです。この原因は、使用目的に合わない遮音性能を選んでしまったり、音の通り道を見落としたりすることにあります。
たとえば、壁の性能だけを重視しても、換気扇のダクトやコンセントの隙間から音は簡単に漏れてしまいます。
費用をかけすぎて全体の予算を圧迫する
理想を追求するあまり、防音室に費用をかけすぎて家全体の予算を圧迫してしまう失敗はよくあります。
必要以上に高い遮音性能(オーバースペック)を求めると、コストはどんどん膨らんでしまいます。その結果、防音室以外のリビングやキッチンの設備、内装のグレードを下げざるを得なくなり、住まい全体の満足度が下がってしまうかもしれません。
なお、注文住宅を安く買うコツについて詳しく知りたい方は、住宅系YouTuberの「まかろにお」が運営する「まかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】」内の「【2021年】大手ハウスメーカー金額ランキングと安く買うコツ」を参考にしてください。
部屋の広さや天井高で圧迫感を感じる
図面上の広さだけを見て計画を進めると、完成した部屋に入ったときに「思ったより狭い」と感じる失敗があります。
防音性能を高めるためには、壁や天井、床に厚みを持たせる必要があり、そのぶん室内の有効面積は狭くなります。特に天井高も低くなりがちなため、圧迫感を感じやすい空間になってしまうでしょう。
換気や空調設備を軽視してしまい快適性が低い
防音室は音を閉じ込めるために気密性を極限まで高めているため、換気や空調設備を軽視すると快適性の低い部屋になってしまいます。適切な換気計画がないと、二酸化炭素濃度が上昇し、息苦しさや集中力の低下を招く原因になりかねません。
また、人の熱や機材の発する熱がこもりやすく、特に夏場はエアコンがないとサウナのような状態になってしまいます。
コンセントの位置や数が足りず不便になる
部屋の使い勝手を大きく左右するのがコンセント計画です。
楽器のアンプやオーディオ機器、パソコン周辺機器など、防音室で使う電気製品の種類と数をあらかじめ想定しておかないと、コンセントが足りずに後悔することになります。数が足りないだけではなく、位置が悪いために部屋中が延長コードだらけになり、見た目が悪くなるうえに、足元が危険な状態になってしまうことも少なくありません。
防音室づくりが得意なハウスメーカーを見極める方法

満足のいく防音室をつくるためには、パートナーとなるハウスメーカー選びが何よりも重要です。防音室は専門的な知識と高い施工技術が求められるため、どの会社でも同じ品質で建てられるわけではありません。
実績や専門性、提案力などをしっかりと見極めることで、後悔のない選択ができます。ここでは、信頼できるハウスメーカーを見つけるための5つの具体的なポイントについて解説します。
- 防音室の施工実績が豊富か確認する
- 専門知識を持つ営業担当者がいるか確認する
- モデルハウスや見学会で実際の防音性能を体験する
- 複数の会社から見積もりを取り比較検討する
- 保証やアフターサポートの内容を確認する
防音室の施工実績が豊富か確認する
ハウスメーカーを選ぶ最初のステップは、防音室の施工実績を確認することです。公式サイトの施工事例ページを見て、これまでにどれくらいの防音室を手がけてきたか、件数を確認しましょう。
その際、自分がつくりたい音楽室やシアタールームといった用途に近い事例があるかも重要なチェックポイントです。
専門知識を持つ営業担当者がいるか確認する
防音室づくりを成功させるには、専門知識を持った営業担当者や設計士の存在が不可欠です。打ち合わせの際に、遮音等級であるDr値や具体的な防音構造について専門的な質問を投げかけてみましょう。その質問に対して的確に、かつわかりやすく答えられるかが一つの判断基準になります。
また、こちらの要望に対してメリットだけではなく、考えられるデメリットやリスクまで正直に説明してくれる誠実な姿勢も大切です。「できます」と答えるだけではなく「なぜできるのか」を構造的に説明できる営業担当者であれば、安心して任せることができるでしょう。
モデルハウスや見学会で実際の防音性能を体験する
カタログやWebサイトの情報だけではなく、必ず自分の耳で実際の防音性能を体験することが重要です。モデルハウスや完成見学会に足を運び、防音仕様の部屋があれば、音楽を流してもらうなどして、部屋の外にどれくらい音が漏れるのかを確認させてもらいましょう。同時に、室内での音の響き方もチェックすると、よりリアルなイメージがつかめます。
複数の会社から見積もりを取り比較検討する
ハウスメーカーを1社に絞り込む前に、必ず複数の会社から見積もりを取って比較・検討しましょう。
その際は、最低でも3社程度から、できるだけ同じ条件で見積もりを依頼するのがポイントです。提示された金額の安さだけで判断するのではなく、どのような防音工事の仕様で、どんな建材が使われる提案になっているのか、その中身をしっかり比較することが大切です。
保証やアフターサポートの内容を確認する
家は建てて終わりではなく、長く住み続けるものです。特に防音室は、万が一完成後に音が漏れるといったトラブルが発生した場合に、どのような保証が受けられるのかを事前に確認しておくことが不可欠です。引き渡し後の定期点検など、アフターサポートの体制が整っているかもしっかりチェックしましょう。
注文住宅の防音室に関するよくある質問

防音室づくりを検討し始めると、費用や工法、リフォームの可否など、さまざまな疑問が浮かんでくるものです。最後に、多くの方が抱える疑問点について、Q&A形式でわかりやすくお答えします。計画を具体的に進める前の不安や悩みを解消し、よりスムーズな家づくりの第一歩を踏み出しましょう。
ヤマハなどのユニット式防音室との違いは?
ユニット式防音室との大きな違いは、設計の自由度と空間へのなじみ方です。
ユニット式は工場で生産された箱型の既製品を部屋の中に設置するもので、工期が短く移設も可能な点がメリットです。
一方、注文住宅でつくる造作の防音室は、部屋の広さや天井高、窓の位置などを間取りに合わせて自由に設計できます。壁紙や床材も他の部屋と統一できるため、インテリアにこだわりたい方や、変形した土地などで部屋の形状に制約がある場合には、造作の防音室が適しています。
6畳の防音室を設置する場合の費用はどれくらい?
6畳の防音室をつくる費用は、求める遮音性能によって大きく変動するため、一概に「いくら」とはいえません。たとえば、ピアノの練習用と、重低音が響くドラムの練習用とでは、必要とされる防音工事の内容がまったく異なり、費用も大きく異なります。
防音室の費用は、部屋の広さよりも「何を」「どれくらいの音量で」楽しみたいかという目的によって決まると考えましょう。正確な費用を知るためには、必ず複数のハウスメーカーから、使用目的を伝えたうえで見積もりを取り、比較・検討することが不可欠です。
ドラムやカラオケなど目的別の注意点はある?
目的によって防音設計で重視すべきポイントは異なります。
たとえばドラムの場合、大きな音漏れを防ぐ高い「遮音」性能はもちろんのこと、ペダルを踏む振動が建物に伝わらないようにするための「防振」対策が必須です。反対に、カラオケやオーディオを楽しむ部屋では、音の反響を適切に抑えてクリアな音響空間をつくる「吸音」の役割が重要になります。
このように、楽器の種類や用途によって最適な防音のバランスは変わるため、設計の初期段階でハウスメーカーに詳細な要望を伝えることが大切です。
今ある部屋を後から防音室にリフォームできる?
既存の部屋を後から防音室にリフォームすることは可能です。しかし、新築時に計画してつくる場合に比べて、費用が割高になる傾向があります。また、建物の構造上の制約から、壁や床を厚くするのに限界があり、理想通りの高い防音性能を確保できないケースも少なくありません。
工事も壁や床を一度解体する必要があるなど大規模になりがちで、住みながらの施工は難しい場合がほとんどです。将来的に防音室が必要になる可能性が少しでもあるなら、新築時に計画に含めておくのが賢明といえるでしょう。
まとめ
注文住宅で理想の防音室を実現するには、正しい知識と信頼できるパートナー選びが不可欠です。まずは専門家から情報を集め、後悔しない家づくりを始めましょう。
防音室づくりで失敗しないための具体的なノウハウを動画で学びたい方は、YouTubeチャンネル「まかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】」の動画をチェックして知識を身につけましょう。運営者のまかろにおが、大手ハウスメーカーごとの防音性能の特徴をわかりやすく解説しています。
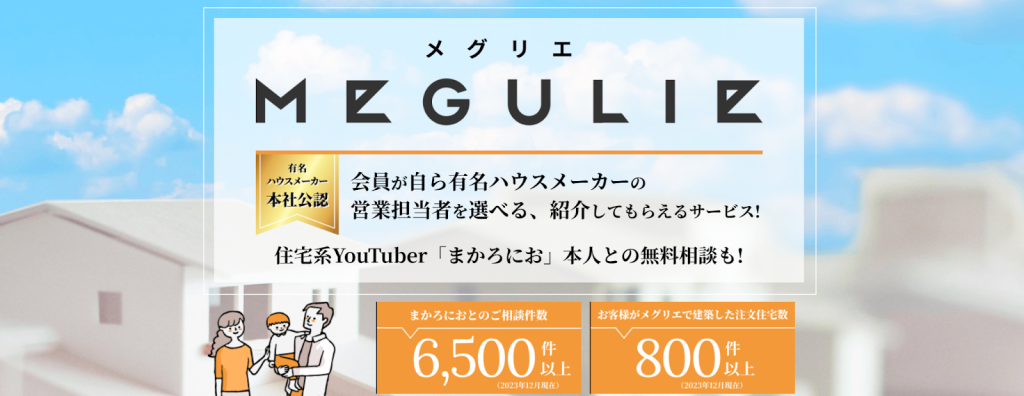
また、当サイト「メグリエ(MEGULIE)」では、家づくりの無料相談をLINEで受け付けています。「希望の防音性能を実現するための費用感がわからない」「どのハウスメーカーに頼めば予算内で収まるのか知りたい」という悩みを専門スタッフによる丁寧なサポートで解消できるでしょう。また、リアルタイムでの最新情報を受け取ることができます。
さらに、「メグリエ(MEGULIE)」に掲載されている豊富な建築実例から気になる施工事例を選び、その施工を担当したハウスメーカーや営業担当者に直接依頼することも可能です。専門知識が豊富な営業担当者と出会えれば、複雑な防音設計の要望もスムーズに実現できるはずです。
なお、当サイト「メグリエ(MEGULIE)」を活用するメリット・デメリットは、こちらの動画で詳しく解説しています。一度チェックしてみてください。
一生に一度の家づくりで理想の音響空間を手に入れるためにも、慎重に情報収集を進めていきましょう。