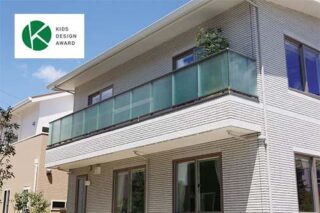この記事はメグリエ運営事務局によって作成しました。
「注文住宅は、契約のタイミングで何に気をつければ良い?」「後から追加費用は発生しない?」といった不安を抱えている方も多いのではないでしょうか?
注文住宅の契約は、人生で最も高額な契約の一つともいえる重要なステップです。しかし、仮契約や本契約、契約書の内容などをよく確認せずに進めてしまうと、後々トラブルに発展するケースもあります。
そこで今回は、注文住宅の契約に関する基本的な流れから、注意すべきポイント、よくあるトラブル事例までをわかりやすく解説します。これから家づくりを進める方が安心して契約に臨めるよう実践的な知識をお伝えするので、ぜひ参考にしてみてください。
注文住宅の契約とは
注文住宅では、家づくりの過程で複数の契約が発生します。中でも中心となるのが、住宅の建築を正式に依頼する「工事請負契約(本契約)」ですが、それに先立って「仮契約」や、土地や設計に関する「その他の契約」が交わされるケースもあります。
それぞれの契約には異なる役割や法的な拘束力があるため、どの契約をどのタイミングで結ぶのかを理解しておくことが非常に重要です。ここでは、注文住宅における代表的な契約の違いや特徴について解説します。
仮契約

仮契約とは、建築会社に対して「この会社にお願いしたい」と意向を伝えるための事前申込的な位置づけの契約です。 この契約を交わすことで、設計や見積もりの詳細作業が進められたり、希望する土地やプランの仮押さえが行われたりすることもあります。
ただし、仮契約といっても契約金(申込金・手付金)の支払いが発生することが多く、キャンセル時の返金条件や違約金の有無については事前に確認しておく必要があります。
また、書面を交わさずに口頭で進められる場合もあるため、「本契約との違い」や「いつ正式契約に切り替わるのか」などの境界を曖昧にしないことが重要です。
本契約

本契約とは、住宅の建築を正式に依頼する工事請負契約のことを指します。 建築費用・工期・支払いスケジュール・設計内容など、注文住宅の根幹をなす項目がすべて明記される重要な契約で、法的拘束力が発生する正式な契約となります。
契約書には、設計図面や仕様書、見積書が添付されることが一般的で、これらの内容が一致しているかどうかの確認が非常に大切です。
また、契約後に変更や追加がある場合は、別途「変更契約」を結ぶ必要があるため、契約前に内容をしっかり読み込み、疑問点があれば遠慮なく質問することがポイントです。
その他の契約
注文住宅に関わる契約は、建物に関するものだけではありません。たとえば、土地を購入する場合には「土地売買契約」が必要ですし、住宅会社によっては設計プランの作成前に「設計契約」を結ぶケースもあります。
これらの契約も金銭の授受を伴うことが多く、特に土地売買契約では、手付金や契約解除に関する条件、登記や引き渡し時期などを明確にする必要があります。
設計契約についても、プランの著作権や中断時の精算条件など、細かなルールが設けられている場合があります。家づくりが複数の契約で成り立っているということを理解し、それぞれの契約の意味やリスクを把握しておくことでトラブルの回避につながります。
注文住宅の契約の流れ

注文住宅の契約は、単に「契約書へサインする」だけではありません。契約までの過程には、プランの提案、費用の確認、詳細な設計のすり合わせなど、複数のステップがあります。
これらを丁寧に進めることで、契約後の「こんなはずじゃなかった」といったトラブルを未然に防ぐことができます。ここでは、契約に至るまでの一般的な流れと、それぞれのステップで確認すべきポイントについて解説します。
見積もりやプランをもらう
契約の第一歩は、希望や要望をもとにしたプラン提案と概算見積もりの提示です。ヒアリングを通して、家族構成・ライフスタイル・予算などを住宅会社に伝えることで、間取りや仕様に反映された初期プランが作成されます。
この時点ではまだ「仮プラン」の段階ですが、概算の費用感や初期費用の目安を知ることができる貴重な資料です。建物本体価格に加え、外構・諸費用・オプションなどの予算も確認し、コストバランスが現実的かどうかをチェックしておきましょう。
設計打ち合わせ・契約前確認を実施する
初期プランをベースに、より詳細な設計打ち合わせを進めていきます。
この段階では、間取りの調整や住宅設備、外装・内装の仕様選びなど、生活動線やデザインに関わる重要なポイントをすり合わせていきます。
また、標準仕様とオプションの違いを明確にし、「どの項目が追加費用になるのか」を確認することも非常に重要です。オプションが重なると想定以上の金額になることも多いため、優先順位をつけながら調整していくことがポイントです。
最終的には、設計内容と見積もりを再度確認し、図面・仕様書・見積書の整合性が取れているかをしっかりチェックしてから契約に進みます。
工事請負契約書の締結と重要事項説明を受ける
設計や費用が固まったら、いよいよ工事請負契約の締結となります。契約書には、工事内容や金額、工期、支払いスケジュールなどが明記されて、家づくりの進行を法的に取り決める重要な書類です。
また、契約時には「重要事項説明書」による法的な内容の説明が行われ、工事遅延時の対応、解除条件、保証内容なども確認する機会となります。
契約書・図面・仕様書の内容に相違がないかをしっかり確認し、不明点があればその場で担当者に質問してクリアにしておきましょう。
このタイミングでの確認不足が後々のトラブルの原因になるケースが多いため、気になる点はメモを取りながら、慎重に進めることをおすすめします。
注文住宅の契約の注意点:仮契約

注文住宅では、本契約の前に「仮契約」や「申込契約」と呼ばれる簡易的な契約が交わされることがあります。これは、住宅会社に対して「このプランで進めたい」という意思表示をするためのもので、設計や見積もりの詳細化、土地の仮押さえなどを目的としています。
しかし、仮契約とはいえ金銭のやり取りが発生する場合が多く、内容をしっかり確認せずに進めてしまうと、後からキャンセルしたくなった際に思わぬトラブルに発展することもあります。ここでは、仮契約を結ぶ際に気をつけたいポイントを3つに分けて解説します。
キャンセルした場合の違約金を確認する
仮契約を結んだあとに「他のハウスメーカーに変更したい」と思った際に、キャンセルができる期限と条件を事前に把握しておくことが大切です。
契約書にキャンセル可能な期限が明記されていないと、「既に手続きが進んでいる」として違約金や実費請求が発生する可能性があります。また、「口頭ではキャンセルしても大丈夫と言われたのに、書面では違約金ありになっていた」といったトラブルも珍しくありません。
こうした食い違いを防ぐためにも、仮契約時には書面でキャンセル条件を明記してもらうようにし、不明点はその場で確認するようにしましょう。
契約金(手付金)の返金について確認する
仮契約の際に支払うお金には、「契約金」「申込金」「手付金」などさまざまな種類がありますが、それぞれ返金ルールが異なることに注意が必要です。
たとえば、「申込金」は比較的簡易な性質で、キャンセル時に全額返金されるケースが多い一方で、「契約金」「手付金」は一部または全額が返金されない場合もあります。
解約時の返金条件や精算方法については、契約書にしっかりと記載されているかを確認し、口頭説明だけで判断しないことがポイントです。また、契約金がどの契約に紐づくのか(設計契約・本契約など)も明確にしておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
正式契約への移行タイミングを明確にしておく
仮契約から本契約へいつ移行するのか曖昧にしたまま進めることは非常に危険です。ハウスメーカーによっては、「一定の条件が整った時点で自動的に本契約に移行する」といった文言が記載されている場合もあり、気づかないうちに法的拘束力が発生することもあります。
仮契約書には、「正式契約を行う日付」や「本契約への切り替え条件」などを明記してもらい、移行時には改めて契約内容を確認する機会を設けましょう。
また、設計プランが固まっていないうちに本契約へ進むと、後から大きな変更が発生し、追加費用やスケジュールのズレが生じることもあります。そのため、焦らず納得した上で本契約へ進むことが大切です。
注文住宅の契約の注意点:本契約
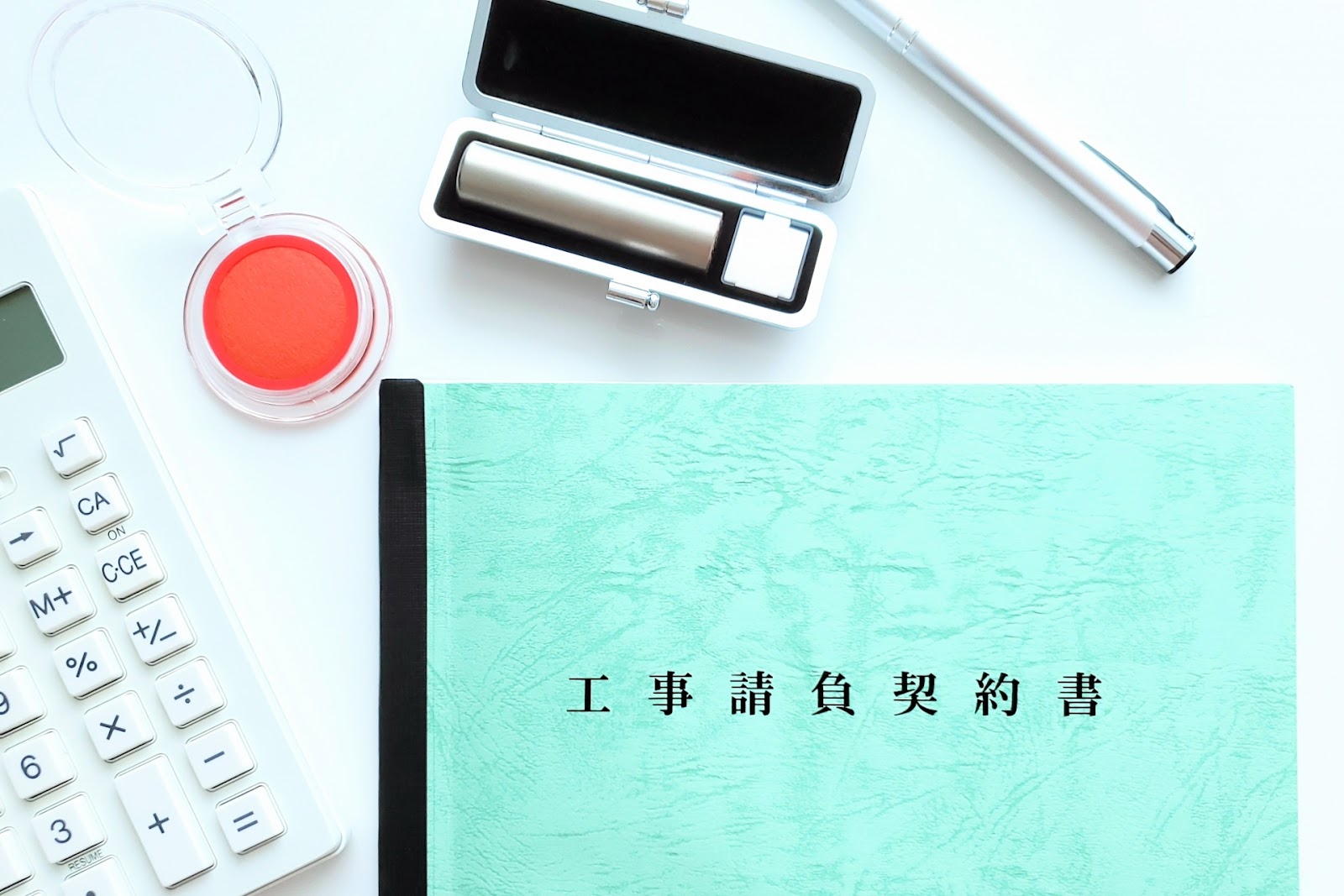
仮契約を経て、いよいよ本格的な家づくりがスタートする「工事請負契約(本契約)」です。この契約では、家を建てるにあたっての工事内容・金額・工期・支払い条件など、すべての基本事項が法的効力を持って記されています。
しかし、書類の確認をおろそかにしてしまうと、「見積もりと契約金額が違った」「思っていた仕様と違う」といったトラブルに発展することもあります。ここでは、本契約を結ぶ際に特に注意すべき3つのポイントを解説します。
契約書の内容と見積もりが一致しているかを確認する
本契約では、これまでの打ち合わせで合意した内容がすべて「契約書」に反映されている必要があります。特に工事内容・総額・支払い条件は、事前に受け取っていた見積もりと完全に一致しているか確認しましょう。
よくあるのが、契約直前に微細な変更や調整が入り、一部金額が変更されていたことに気づかないケースです。また、見積書では「込み」とされていた項目が、契約書では別記載になっていることもあるため、各書類を照らし合わせて確認することが大切です。
仕様書や設計図面に齟齬がないかを確認する
契約書には、設計図面や仕様書も添付されることが一般的です。特に間取り・内装・設備に関しては、「口頭で伝えたはず」「打ち合わせでは違う内容だった」という行き違いが起こりがちです。
図面や仕様書は、必ず最新版であることを確認し、仕上げの素材や色、設備の型番など細かな点もチェックしておきましょう。
また、記載漏れやミスがあった場合は、訂正印を押すか再発行を求めることが基本です。書類上に明記されていない仕様は後でトラブルになる可能性があるため、曖昧な内容は必ず明文化しておくようにしましょう。
支払い条件とスケジュールを明確にしておく
注文住宅の支払いは、多くの場合「契約金(着手金)→中間金→最終金」の3段階で行われます。それぞれの支払い時期と金額、支払い方法を事前に把握しておかないと、急な出費に対応できずトラブルになることもあります。
また、契約後に仕様変更や追加工事が発生した場合の追加費用の扱い方も契約書に明記されているか確認しておきましょう。さらに、工事の進捗に応じて支払うケースも多いため、工事遅延や引き渡し日の変更が起きた場合の対応ルールもチェックしておくと安心です。
注文住宅の契約で損をしないためには、事前に注文住宅について勉強しておくことが大切です。このような注文住宅に関する知識を身につけるには、元大手ハウスメーカー勤務でチャンネル登録者数13万人以上の住宅系YouTuber「まかろにお」が運営するYouTubeチャンネル「まかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】」がおすすめです。
運営者である「まかろにお」は、『人から始める家造りの重要性を世に広める』をコンセプトとした住宅系YouTuberです。元ハウスメーカー営業マンとして全国1位の営業成績を誇り、その後も不動産融資を扱う大手金融機関での実務経験を経て、幅広いハウスメーカー事情に精通しています。大手ハウスメーカーの特徴やメリット、デメリット、さらに注文住宅を建てる前に知っておきたい知識を中立的な立場で発信しています。
動画では各ハウスメーカーの優秀な営業マンからもらったリアルな情報をもとにして、役立つコンテンツを多数配信しています。
注文住宅の契約書で特に確認すべき項目

注文住宅の契約書には、建築に関するあらゆる条件が細かく記載されています。しかし、内容が専門的でボリュームも多いため、十分に確認せず署名してしまう方も少なくありません。
契約書をしっかり確認することで、後々の追加費用や工期遅延、設備トラブルなどを未然に防ぐことができます。ここでは、特に見落としがちな項目やトラブルにつながりやすい箇所を6つに分けて解説します。
工期・スケジュール
契約書には必ず「着工日」「引き渡し日」などが明記されているか確認しましょう。また、工事が予定より遅れた場合の対応についても確認しておくと良いです。
たとえば、遅延損害金の有無、免責事由などを確認しておきます。特に、天候不良や地震・台風など不可抗力による工期遅延が免責対象となっているケースもあるため、どこまでが許容範囲なのか明確にしておくことが大切です。
支払い時期や金額
「契約金」「中間金」「最終金」など、支払いのタイミングと金額が契約書にきちんと明記されているか確認しましょう。 また、追加工事が発生した場合の請求方法や、支払いに含まれる消費税や諸費用の扱いにも注意が必要です。
後から「聞いていなかった費用が請求された」ということがないよう、曖昧な点は事前に質問しておきましょう。
ローン特約
住宅ローンを利用する場合は、「ローン特約」の内容を必ず確認してください。 ローン特約はローンの審査が通らなかった場合に契約を解除できる条件であり、違約金の有無や申請期限、返金条件などに関わります。
特に、「ローンが不承認でも違約金が発生する」といったリスクを回避するためには、契約書の文言を細かく確認し、疑問があれば書き加えてもらうことも必要です。
キャンセル時の違約金
万が一、契約を解除したくなった場合に備えて、解約が可能なタイミングや違約金・実費精算の金額・ルールについても把握しておきましょう。
また、万が一のトラブルに備え、打ち合わせ記録や書面の控えを必ず保存しておくことも大切です。口頭でのやり取りは後から証明が難しいため、メールや書面でのやり取りを基本としましょう。
保証・アフターサービス
契約後・入居後のトラブルに備えて、構造躯体や住宅設備に対する保証内容は必ずチェックしておく必要があります。
たとえば、「10年保証があるのは基礎や構造部分のみ」「設備保証は2年まで」など、範囲と期間が異なるため注意が必要です。また、定期点検のスケジュールや無償修理の条件、免責事項についても確認し、将来のメンテナンス計画に役立てましょう。
見積もり・プラン
契約書に添付される見積書は、「総額」だけでなく、工事項目ごとの明細が記載されているか確認しましょう。 また、使用する建材のグレードや設備の品番、色、仕上げの内容などがプランと一致していることも非常に重要です。
「設計図と違っていた」「希望した設備が入っていなかった」といったトラブルを防ぐためにも、見積もりと図面・仕様書を並べて確認することをおすすめします。
注文住宅の契約でよくあるトラブル

注文住宅の契約は、何千万円という大きな金額が動く重大な手続きです。しかし、契約時の確認不足や認識のズレが原因で、後からトラブルに発展するケースも珍しくありません。「契約書に書いていなかった」「伝えたつもりが反映されていなかった」など、事前によくあるトラブル事例を知っておくことが大切です。
最後に、実際に起きやすい4つのトラブルを紹介し、その原因と対策を解説します。これまで解説した注意点を守らないと起こりやすいトラブルなので、注意点とも照らし合わせながらぜひチェックしてみてください。
工事の追加・仕様変更
契約後に多いトラブルが、追加費用の発生や仕様変更による工期の遅れです。「コンセントを増やしたい」「キッチンを別のメーカーに変えたい」など、細かな変更を希望することはよくありますが、それに伴い費用やスケジュールが変更されることも少なくありません。
問題なのは、それらの変更内容が書面で正式に記録されていないケースです。口頭だけのやり取りでは「言った・言わない」のトラブルにつながりやすく、後から請求額を見て驚くこともあります。
変更があった際には、必ず変更契約書を取り交わすか、書面やメールで明文化しておきましょう。
工期の遅延
天候や資材の納品遅れ、職人不足などを理由に工期が予定より大幅に延びることもあります。そのとき、契約書に着工日・引き渡し日の記載がない場合は、ハウスメーカーとの間で責任の所在が曖昧になることがあります。
特に注意したいのは、引越しや入居の予定が組まれている場合です。予定がずれることで仮住まい費用や二重ローンが発生し、家計に大きな影響を及ぼす可能性もあります。
事前に、「遅延が起きた場合の対応」や「補償の有無」について契約書で確認しておくことが重要です。
ローンに関するトラブル
住宅ローンが通らなかったことによって契約を破棄せざるを得ないケースもあります。この際、契約書に「ローン特約」が明記されていないと、違約金の請求や手付金の没収といった重大なリスクが発生する可能性があります。
また、金融機関との書類提出が遅れたことで融資が実行されず、着工スケジュールに影響が出るといった手続きミスも起こりがちです。
ローンを利用する場合は、契約書に特約があるかを必ず確認し、手続きの期限や条件も住宅会社と共有しておきましょう。
施行ミス・設計ミス
施工中・引き渡し後に発覚するトラブルの中でも多いのが、設計図と異なる施工や仕上がりの不具合です。たとえば、「コンセントの位置が図面と違う」「使う予定だった建材が別のものになっている」など、図面との相違によるミスが起きることがあります。
また、「希望していたことが設計に反映されていなかった」「設計図が最新でなかった」など、設計段階での食い違いも後を絶ちません。加えて、引き渡し後の補修対応が不十分でトラブルが長期化するケースもあります。
こうしたトラブルを防ぐには、工事中の中間検査や施主検査をきちんと行うこと、そして図面や仕様書の最新版を常に手元に置いて確認する習慣を持つことが大切です。
注文住宅の契約で失敗しないためには、事前に「よくあるトラブル」を知り、契約書や図面をしっかり確認しておくことが何よりの対策になります。
チャンネル登録者数13万人以上を誇る住宅系YouTuber「まかろにお」が運営する「まかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】」では、こういった注意点についても解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
まとめ
注文住宅の契約は、家づくりにおける最も重要な節目の一つです。金額も大きく、契約後の変更やトラブルは精神的にも金銭的にも大きな負担となるため、契約前に内容とリスクをしっかり確認することが何よりも大切です。
特に、契約書や仕様書の内容は「読みにくい」「わかりづらい」と感じることも多いですが、見積もりとの整合性や支払い条件、工期、保証内容などを丁寧に読み込むことがトラブル回避につながります。
また、「自分では判断できない」と感じたときには、住宅に詳しい第三者や専門家に相談することも有効です。
今回紹介したようなハウスメーカーの注意点などをもっと詳しく知りたい方には、YouTubeチャンネル「まかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】」の動画が大変おすすめです。元大手ハウスメーカー勤務のまかろにおが、現場のリアルな声や営業マンから得た実践的な情報をもとに、後悔しない家づくりのヒントをわかりやすく解説しています。
また、当サイト「メグリエ(MEGULIE)」では、家づくりの無料相談をLINEで受け付けています。
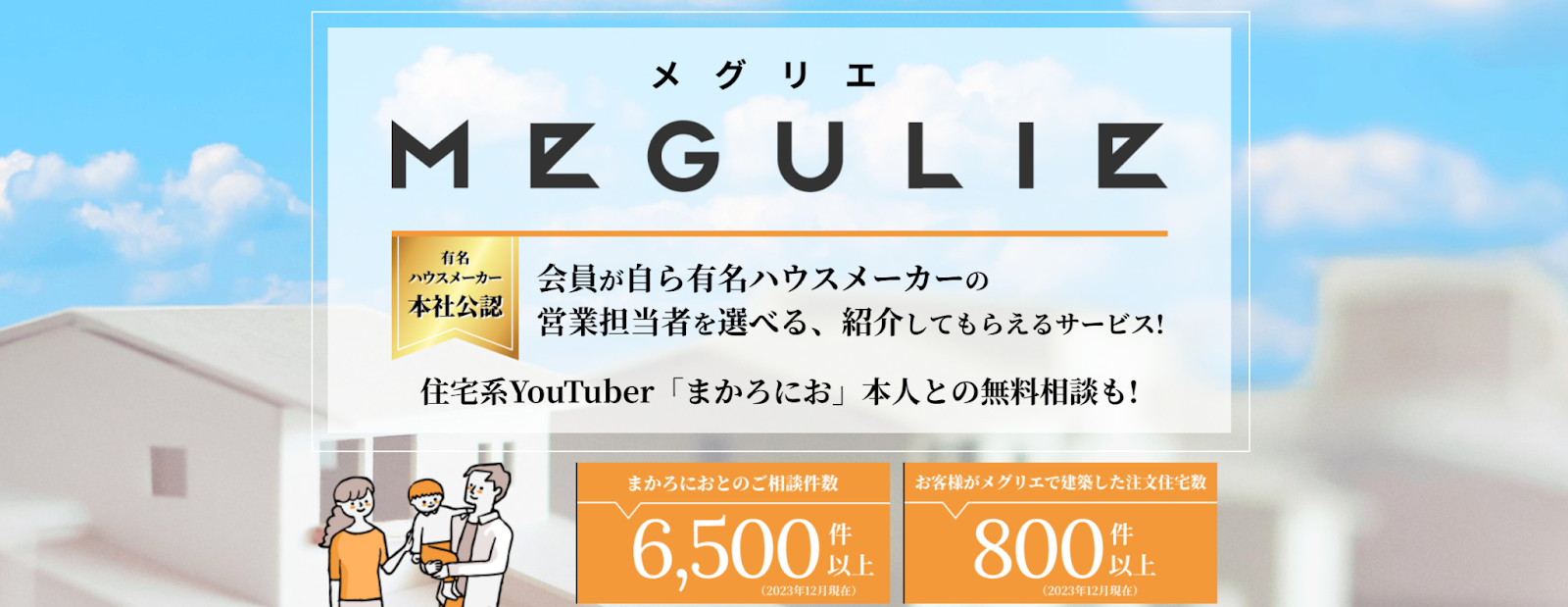
住宅に関する悩みや不安がある方は、下記のリンクから友だち追加していただくと、専門スタッフによるアドバイスや最新情報をリアルタイムで受け取ることができます。
安心して家づくりを進めるためのサポートに、ぜひご活用ください。