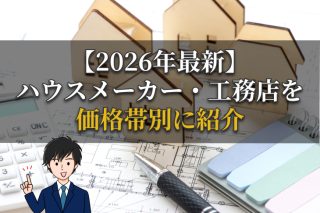この記事はメグリエ運営事務局によって作成しました。
注文住宅を検討する際、予算を抑えながらも品質の良い家を建てたいと考える方は多いのではないでしょうか?そこで注目されるのが「ローコスト住宅」です。
今回は、ローコスト住宅とは何か、そのメリット・デメリット、後悔しないためのハウスメーカーの選び方のポイント、そして建築時の注意点について解説します。さらに、おすすめのハウスメーカー9社も紹介します。コストを抑えながらも満足できる家づくりのための情報を網羅していますので、ぜひ参考にしてください。
ローコスト住宅とは

ローコスト住宅とは、一般的に建築費用が1,000万円台から、坪単価にすると30万円から60万円程度の価格帯で建てられる住宅を指すことが多いです。ただし、これはあくまで目安であり、明確な定義が存在するわけではありません。
低価格を実現できる背景には、ハウスメーカー各社によるさまざまな企業努力があります。
一つは、部材や設備の一括大量仕入れです。キッチン、バス、トイレといった設備や構造材などを一度に大量に購入することで、仕入れ単価を大幅に下げています。スケールメリットを活かしたコスト削減策といえるでしょう。
次に、設計や仕様を規格化・限定することもコストダウンにつながっています。あらかじめ用意されたプランや選択肢の中から顧客が選ぶ形式にすることで、ゼロから設計するフルオーダー住宅に比べ、設計や打ち合わせにかかる時間と人件費を削減しています。
また、広告宣伝費や住宅展示場の維持費などを抑えている点も理由の一つです。テレビCMや大規模な展示場への出展を控える代わりに、インターネット広告や紹介制度を活用するなど、販促コストを合理化し、その分を住宅価格に還元しています。
そして、柱や梁などの構造材を工場であらかじめ精密にカット(プレカット)しておくことで、現場での作業効率を高め、品質の均一化を図ります。施工手順をシステム化し、無駄な作業を省くことで、人件費の削減と工期の短縮が可能です。
ローコスト住宅のメリット

「安いものには安いなりの価値しかない」と思い込んでいませんか?実は、ローコスト住宅には、単に価格が安いこと以外にも見落としがちなメリットが数多くあります。ここでは、ローコスト住宅が持つ5つの大きなメリットについて解説します。予算を抑えながらも満足度の高い家づくりを実現しましょう。
ライフステージの変化に対応しやすい
まず、ライフステージの変化に対応しやすい点が挙げられます。
建築費用が抑えられるため、住宅ローンの借入額も少なく済み、月々の返済負担が軽くなります。これにより、将来的に家族構成や働き方が変わった場合でも、建て替えやリフォーム、住み替えといった選択肢を検討する際の経済的なハードルが低くなるでしょう。
将来の不確実性に対応しやすい、柔軟な住まい計画が可能になります。
工事期間が短い
次に、工事期間が短いこともメリットです。規格化されたプランやプレカットされた部材を使用することで、現場での作業が効率化され、一般的な注文住宅の工期と比較して、短い工期で完成することが多くなります。これにより、仮住まいの費用や二重ローンの期間を最小限に抑えられるでしょう。
家を建てるハードルが下がる
家を建てる際の経済的なハードルが下がる点も大きなメリットです。建築費用が一般的な注文住宅よりも大幅に抑えられるため、収入がまだ安定しない若年層や、教育費などを優先したい子育て世帯など、これまで予算的に注文住宅を諦めていた層でもマイホームを取得しやすくなります。
シンプルで設計しやすい
設計プロセスがシンプルでわかりやすいこともメリットといえるでしょう。間取りや設備がある程度規格化されており、選択肢が絞られているため、家づくりに関する専門知識が少ない方や、多くの選択肢から選ぶのが苦手な方でも、打ち合わせをスムーズに進めやすい傾向があります。
税金や維持費が抑えられる
最後に、税金や維持費が抑えられる可能性が高い点もメリットです。建物本体の価格が安いため、不動産取得時や取得後にかかる固定資産税、登録免許税、火災保険料などの算出基準となる評価額が低くなる傾向があります。これにより、初期費用だけではなく、長期的なランニングコストの面でも負担が軽減される可能性があります。
ローコスト住宅のデメリット
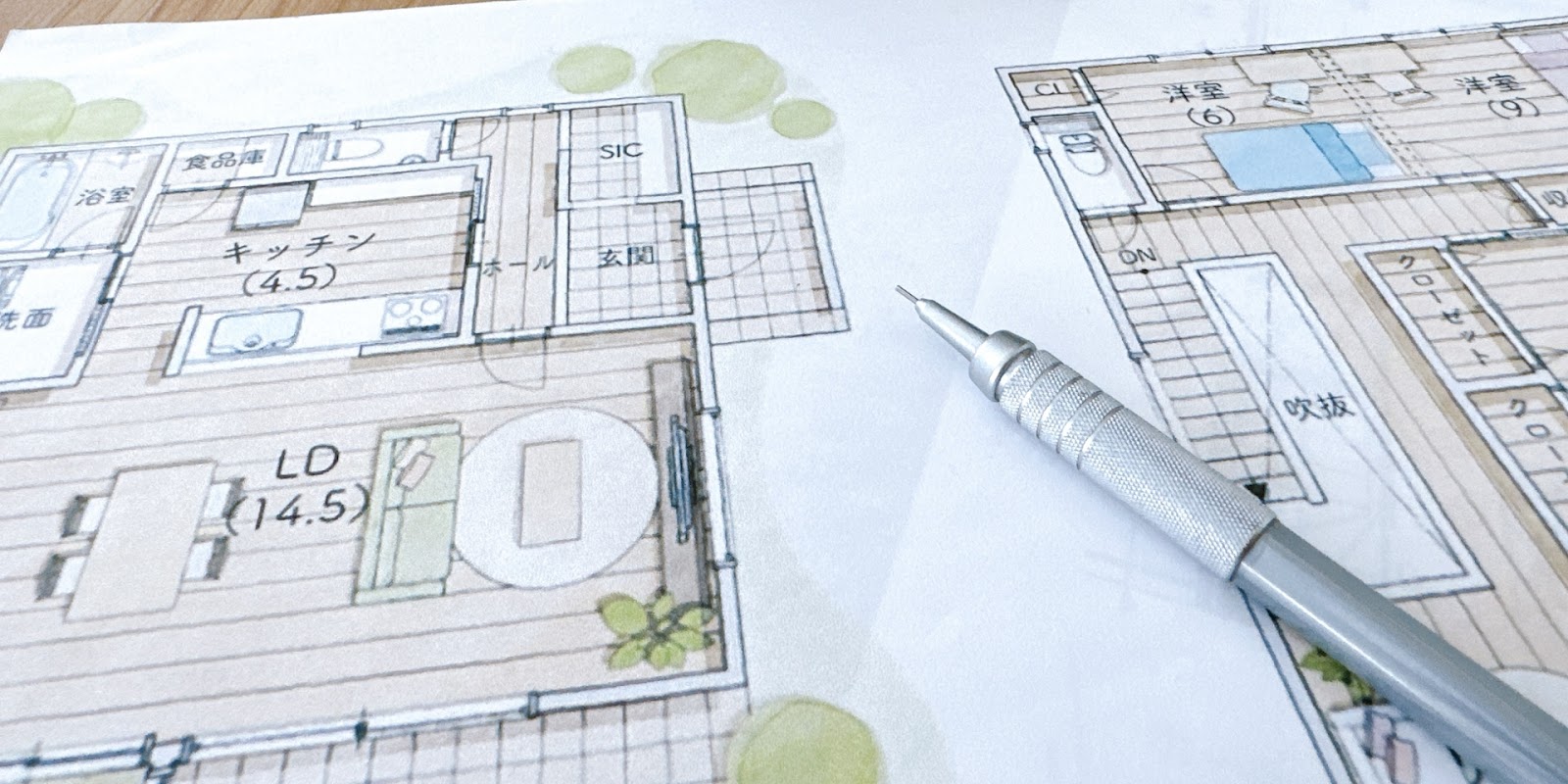
ローコスト住宅に魅力を感じていても「本当に大丈夫?何か落とし穴はないの?」と不安に思っている方も多いのではないでしょうか?
確かに、価格を抑えるために妥協している部分もあり、設備のシンプルさや設計の自由度の低さなど、理解しておくべきデメリットがあります。ここでは、契約前に把握しておくべき主な注意点を5つ解説します。目先の安さに惑わされず、長期的な視点で住まいを選びましょう。
設備や機能性がシンプル
まず、標準仕様の設備や機能性がシンプルである点がデメリットです。コスト削減のため、キッチン、バスルーム、トイレなどのグレードが、一般的な注文住宅に比べて低めに設定されていることが多くあります。
最新の高機能な設備やデザイン性の高いものを求める場合は、オプションとして追加する必要があり、その分の費用が発生します。標準仕様の内容をよく確認することが大切です。
メンテナンス費用が割高になる
次に、将来的なメンテナンス費用が割高になる可能性があります。初期費用を抑えるために、外壁材や屋根材などに安価な建材が使用されている場合、耐久性が低く、修繕や交換の頻度が高くなることがあります。
結果的に、長期的な視点で見るとトータルの住居費用が高くつくケースも考えられるでしょう。使用される建材の耐久性やメンテナンス計画についても確認が必要です。
設計の自由度が低い
設計の自由度が低いことも、ローコスト住宅の代表的なデメリットです。コストダウンと工期短縮のため、規格化されたプランや仕様が中心となるため、間取り、デザイン、仕様の選択肢が限られます。
こだわりの強い、完全な自由設計を希望する場合は、対応が難しかったり、追加費用が高額になったりする場合があります。どこまで自由度を求めるかを明確にしておきましょう。
断熱・気密性能が劣ることがある
断熱・気密性能が劣る場合がある点にも注意が必要です。
コスト削減のために、断熱材の種類や厚み、窓のサッシなどのグレードが最低限のレベルに設定されていることがあります。この場合、冷暖房効率が悪く光熱費が増加したり、結露が発生しやすくなったりする可能性があります。
ただし、近年は高性能なローコスト住宅も増えているため、具体的な性能値(UA値、C値など)を確認することが重要です。
資産価値が下がりやすい
一般的な注文住宅と比較して、将来的な資産価値が下がりやすい傾向がある点も考慮すべきデメリットです。規格化されたデザインが多く、建材や設備のグレードも標準的なものが中心となるため、耐久性や独自性の面から、中古住宅として売却する際の評価額が低くなる可能性があります。
ローコストハウスメーカーの選び方のポイント

ローコスト住宅を扱うハウスメーカーは数多く存在するため「どこで建てれば後悔しないの?」と迷っている方も多いでしょう。ハウスメーカー選びを間違えると、予想外の追加費用が発生したり、住宅性能に不満を感じたりする可能性があります。
ここでは、総額での比較方法や性能チェックのポイント、担当者との相性の重要性など、自分に合ったメーカーを見極めるための7つの選定基準を解説します。失敗しない家づくりのパートナーを選びましょう。
- 予算と総額で選ぶ
- 住宅性能と機能性をチェックする
- アフターサービスと保証内容を確認する
- 実績と口コミ・評判を調査する
- 担当者との相性を重視する
- 対応可能地域で絞り込む
- 安く建てられる理由をしっかり確認する
予算と総額で選ぶ
まず、予算と総額で選ぶことが基本です。注意点として、坪単価はメーカーごとに算出基準が異なり、参考程度にとどめましょう。重要なのは、建物本体価格以外に必要な付帯工事費、諸費用、オプション費用を含めた「総額」で見積もりを比較することです。
オプションを追加すると当初の想定より大幅に価格が上がることもあるため、複数のメーカーから総額の見積もりを取り、内容を詳細に確認しましょう。その上で、予算内で希望が叶うか、無理のない資金計画が立てられるかを確認することが大切です。
住宅性能と機能性をチェックする
次に、住宅性能と機能性をチェックします。
特に耐震性能(耐震等級)は重要で、ローコストでも等級3相当のハウスメーカーもあります。また、断熱性能・気密性能(断熱材の種類、厚み、窓の仕様、可能ならUA値、C値など)は光熱費や快適性に直結するため確認が必要です。
また、標準仕様の設備のグレードを確認し、必要に応じてオプションを検討しましょう。長期優良住宅やZEH(ゼッチ)基準に対応しているかも確認ポイントです。これは税制優遇や補助金に関わります。
そして、将来的なメンテナンス性も考慮し、耐久性の高い建材や設備が使われているかも確認しておくと安心です。
アフターサービスと保証内容を確認する
アフターサービスと保証内容を確認することも忘れてはなりません。法律で定められた初期保証期間(10年)と保証範囲は最低限です。保証期間の延長が可能か、その条件や最長保証期間を確認しましょう。
定期点検の有無、頻度、期間、内容もチェックします。住宅設備の保証期間や、トラブル発生時の連絡体制も確認しておくと、入居後も安心です。
実績と口コミ・評判を調査する
実績と口コミ・評判を調査することも有効です。ハウスメーカーの年間建築棟数や創業年数などの実績は信頼性の参考になります。希望する住宅タイプの施工実績が豊富かも確認しましょう。
インターネット上の口コミサイト、SNS、Googleマップなどで実際に建てた人の評判を調べることも役立ちます。ただし、情報は多角的に見ることが大切です。
施工事例を見て、デザインや間取りが自分の好みに合っているかを確認し、第三者機関による評価や受賞歴なども参考に、信頼性を判断しましょう。
担当者との相性を重視する
担当者との相性を重視することは非常に重要です。家づくりは担当者とのコミュニケーションが密になるため、相性が満足度を左右します。
質問に対して誠実に、わかりやすく答えてくれるか、メリットだけではなく、デメリットやリスクについても正直に説明してくれるか、こちらの要望を丁寧にヒアリングし、希望に沿った提案をしてくれるか、といった点を見極めましょう。
強引な営業がなく、信頼できる人柄かどうかも重要です。複数の担当者と話してみることをおすすめします。
担当者の良し悪しを見極めるには、住宅系YouTuberの「まかろにお」が運営する「まかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】」内の「例の営業トークには気を付けろ!!住宅営業マンが良く付く嘘ランキング!」を確認してください。
運営者である「まかろにお」は、『人から始める家造りの重要性を世に広める』をコンセプトとした住宅系YouTuberです。元ハウスメーカー営業マンとして全国1位の営業成績を誇り、その後も不動産融資を扱う大手金融機関での実務経験を経て、幅広いハウスメーカー事情に精通しています。大手ハウスメーカーの特徴やメリット、デメリット、さらに注文住宅を建てる前に知っておきたい知識を中立的な立場で発信しています。
対応可能地域で絞り込む
対応可能地域で絞り込むことも初期段階で必要です。ハウスメーカーごとに施工可能なエリアが異なるため、建築予定地が対応エリア内か最初に確認しましょう。
全国展開のメーカーだけではなく、地域密着型の工務店も選択肢に入れると、地域の特性を理解していたり、柔軟な対応が期待できたりする場合があります。
安く建てられる理由をしっかり確認する
安く建てられる理由もしっかり確認しましょう。なぜ低価格を実現できているのか、具体的なコスト削減の取り組みを説明してもらうことが大切です。
そして、価格の安さが、品質や性能、保証・アフターサービスの低下につながっていないかを確認することが重要です。見積もり内容が明確で、不透明な部分がないかもチェックし、安さの理由に納得できるか、安心して任せられるかを最終的に判断しましょう。
ローコスト住宅におすすめのハウスメーカー
「具体的にどのハウスメーカーが自分に合っているの?」という疑問を持っている方も多いでしょう。各ハウスメーカーには特徴やこだわりがあり、単純な価格比較だけでは最適な選択ができません。
ここでは、ローコスト住宅分野で実績のある9社について、それぞれの特徴やメリット・デメリットを客観的に比較します。あなたの希望や条件に合ったハウスメーカー選びの具体的な指針にしてください。
ハウスメーカーの坪単価ランキングについては、住宅系YouTuberの「まかろにお」が運営する「まかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】」内の「【2025年最新】大手ハウスメーカー坪単価ランキング」を参考にしてください。
一条工務店

一条工務店は「家は、性能。」を掲げ、住宅性能に徹底的にこだわるハウスメーカーです。特に高断熱・高気密性能は業界トップクラスで、全館床暖房や太陽光発電システムが標準仕様となっている点が大きな特徴です。
自社グループ工場で断熱材や設備などを生産することで、高性能とコスト抑制を両立しています。モデルハウスの仕様がほぼそのまま標準提供されるため、オプション費用がかさみにくい傾向があります。
メリット
一条工務店で家を建てるメリットは、住宅性能が非常に高く、省エネ性に優れ、年間を通して快適な住み心地が期待できる点です。また、長期的な光熱費削減効果が大きいことも魅力です。
デメリット
デメリットとしては、他のローコストメーカーと比較すると坪単価が高めであることが挙げられます。また、性能を重視する分、間取りなどの自由設計の幅がやや限定的になる傾向がある点もデメリットといえるでしょう。
オープンハウス
オープンハウスは、特に首都圏などの都市部において、好立地に低価格で住宅を提供することに強みを持つハウスメーカーです。土地の取得から設計・施工・販売までをグループ内で一貫して行うことでコストを削減しています。
狭小地や変形地の活用ノウハウも豊富です。住宅は標準仕様にオプションを追加していくセミオーダー形式が基本となります。
メリット
オープンハウスで家を建てるメリットは、地価の高い都心部でもマイホームが手に入る価格帯を実現している点や、土地探しから建物完成までをワンストップで任せられる利便性です。
デメリット
デメリットは、完全な自由設計は不可である点、希望に応じてオプションを追加していくと総費用が増える可能性がある点です。
飯田グループ
飯田グループホールディングスは、複数のハウスメーカーを傘下に持つ日本最大の住宅供給グループです。建築棟数は全国トップクラスを誇ります。グループ全体のスケールメリットを活かし、シンプルなデザインと安心感のある品質の住宅を低価格で提供しています。多くの場合、耐震等級3を標準で取得している点も特徴です。
メリット
飯田グループで家を建てるメリットは、大手グループならではの安心感と手頃な価格設定を両立できる点、グループ全体の大量仕入れによるコストダウン効果が大きい点です。
デメリット
デメリットとしては、デザイン面ではやや画一的で、デザイン性を重視する場合には物足りなく感じる可能性がある点が挙げられます。
アイダ設計
アイダ設計は「正直価格」を掲げ「999万円の家」など、価格設定が明朗な規格住宅を主力としています。自社でプレカット工場を所有し、木材加工から一貫して行うことで品質管理とコストダウンを両立しています。
ローコストながら、高断熱仕様が標準装備されているプランもある点は、魅力的です。
メリット
アイダ設計で家を建てるメリットは、ローコストながら断熱性能にも配慮されている点、規格住宅だけではなく自由設計にもある程度対応している点です。価格がわかりやすいのも魅力です。
デメリット
デメリットは、他の大手メーカーと比較して保証期間がやや短めであること、価格を抑えると選べる設備のグレードも制限される可能性があることです。
タマホーム
タマホームは「より良いものをより安く」をモットーに、全国展開している知名度の高いハウスメーカーです。主力商品「大安心の家」シリーズなどでは、長期優良住宅仕様やオール電化といった高性能な仕様が標準となっている場合が多いです。自由設計に対応している点も大きな特徴といえるでしょう。
メリット
タマホームで家を建てるメリットは、価格に対する性能や設備のコストパフォーマンスの良さに定評がある点、設計の自由度が高く、理想の間取りが実現しやすい点です。
デメリット
デメリットは、初期保証が10年とやや短いこと、店舗や担当者、施工業者によって対応や品質に地域差があるとの声も聞かれる点です。
秀光ビルド
秀光ビルドは「コミコミ価格品質」を掲げ、価格の透明性を重視するローコスト住宅メーカーです。建物本体価格に加えて、申請費や付帯工事費などを含んだ「コミコミ価格」を提示している点が特徴です。12回の検査体制や最長30年の保証、高断熱仕様や制震機能を標準装備するなど、品質や性能、アフターフォローにも力を入れています。
メリット
秀光ビルドで家を建てるメリットは、価格が明瞭で追加費用の心配が少ない安心感、性能を重視しながらも低価格を実現している点です。
デメリット
デメリットとしては、デザインや内装の質感についてはやや劣るとの声があること、支店や施工担当者によって品質に差が出やすい可能性が指摘されている点です。
パパまるハウス
パパまるハウスは、ヤマダホールディングスグループ(旧ヒノキヤグループ)傘下のローコストメーカーです。規格住宅を中心に展開し、特に断熱性能や空調設備に強みがあります。グループ独自の全館空調システム「Z空調」を比較的低価格で導入できるプランが魅力で、1,000万円台で住宅取得が可能な場合もあります。
メリット
パパまるハウスで家を建てるメリットは、低価格でも快適な全館空調や高断熱の家を実現できる可能性がある点、年間1,000棟以上の安定した実績がある点です。
デメリット
デメリットは、規格住宅が中心のため、設計の自由度はやや限定的であり、外観や間取りで個性を出しにくい可能性がある点です。
レオハウス
レオハウスもヤマダホールディングスグループの一員で、完全自由設計が可能なハウスメーカーです。高断熱・高気密仕様に加え、剛床工法などで耐震性も確保しています。グループの強みを活かし、IoT対応や省エネ性能に優れた住宅の提案も可能です。ヤマダグループ傘下で経営が安定している点もポイントです。
メリット
レオハウスで家を建てるメリットは、間取りやデザインの自由度が非常に高い点、IoTや省エネといった先進技術を取り入れやすい点です。
デメリット
デメリットは、自由度が高い分、オプションが増えると価格が高くなる可能性がある点、外観デザインは比較的シンプルで好みが分かれる場合がある点です。
一建設
一建設(はじめけんせつ)は、飯田グループホールディングスの中核企業で、分譲住宅のほか注文住宅も手掛けています。飯田グループのスケールメリットを活かし、高性能な家を低価格で提供することに強みがあります。標準仕様でも耐震等級3相当や省エネ基準適合など、性能が高い場合が多いです。平屋や二世帯住宅など多彩なプランに対応しています。
メリット
一建設で家を建てるメリットは、価格を最優先に考えたい場合におすすめできる点、標準仕様でもある程度の性能が確保されている安心感です。
デメリット
デメリットは、飯田グループ共通の傾向として、工事や担当者の対応にバラつきがあるとの声がある点、外観や仕様の自由度には限界がある点です。
ローコスト住宅を建てる際の注意点

せっかく頑張って建てた家なのに、後から「ここをもっと考えておけば良かった」と後悔したくないという思いは誰にでもあるでしょう。特にローコスト住宅では、土地選びから設備の選定、断熱性能の決定まで、初期費用を抑えつつも長期的な視点で判断すべきポイントがいくつもあります。
最後に、コスト削減と住み心地を両立させるための5つの主な対策を解説します。入居後も満足できる家づくりを実現しましょう。
建築コストが高くつく土地は選ばない
まず、建築コストが高くつく土地は選ばないようにしましょう。地盤が弱い土地は地盤改良費が高額になる可能性があるため、事前に地盤調査の結果などを確認します。狭小地や変形地は特殊な設計や施工が必要となり、追加費用が発生しやすいです。
高低差のある土地は造成費用や基礎工事費用がかさむことがあります。また、インフラ(水道、ガス、電気)が未整備の土地は、引き込み工事費用が別途必要になります。土地選びの段階からこれらのコストを意識することが重要です。
住宅系YouTuber「まかろにお」のチャンネルでは、「【増額注意】土地購入前に確認するべきポイント」や「失敗しない土地の選び方【注文住宅】」など、土地選びに関する重要なポイントを解説した動画も公開していますので、ぜひ参考にしてください。
打ち合わせ前にイメージ写真を用意する
次に、打ち合わせ前に理想の家のイメージ写真を用意することをおすすめします。外観、内装、間取り、雰囲気などの写真を具体的に集めておくことで、言葉だけでは伝わりにくい好みのテイストやこだわりたいポイントを視覚的に伝えることができます。
これにより、担当者とのイメージ共有がスムーズになり、打ち合わせ時間を効率的に使い、要望を的確に伝える助けとなるでしょう。SNSや住宅雑誌、メーカーの施工事例などを参考に準備しておくことがおすすめです。
家の形や建材を工夫する
家の形や建材を工夫することもコスト削減につながります。建物の形状はシンプルな四角形にすると、外壁や屋根の面積が少なくなりコストを抑えられます。凹凸が多い複雑な形状はコストアップにつながります。屋根の形状もシンプルな切妻屋根や片流れ屋根を選ぶと、コストダウンになるでしょう。
建材は標準仕様の中から選ぶことを基本とし、オプションは本当に必要なものに絞ると、よりコストを抑えられます。間仕切り壁を少なくする、オープンな間取りにするなどもコスト削減に有効な場合があります。
住宅設備は「交換しやすさ」を重視する
住宅設備は将来的な「交換しやすさ」を重視して選びましょう。設備はいずれ交換時期が来るため、将来的な交換費用や手間を考慮することが大切です。特殊な形状やサイズの設備は、交換時に選択肢が限られたり費用が高くなったりする可能性があるため、汎用性の高い製品を選びましょう。
配管や配線のメンテナンス・交換がしやすい設計になっているかも確認ポイントです。設備のグレードを抑える場合でも、将来交換することを前提に必要な機能を見極めるようにしましょう。
住んでからの光熱費を考えて断熱仕様を決める
住んでからの光熱費を考えて断熱仕様を決めることも重要です。初期費用だけではなく、入居後のランニングコストも考慮して断熱性能を決めましょう。断熱性能や気密性能の数値を確認し、必要であれば標準仕様からグレードアップを検討します。
特に熱の出入りが大きい窓は、断熱性の高いサッシやガラスを選ぶことが効果的です。ZEH基準を満たす住宅は光熱費削減効果が高く、補助金対象になる可能性もあります。初期費用とランニングコストのバランスを考えることが大切です。
住宅系YouTuber「まかろにお」のチャンネルでは「【要注意】断熱性能を上げても意味がない理由」で断熱性能について詳しく解説した動画も公開しています。これから家づくりを始める方は、ぜひご覧ください。
まとめ
ローコスト住宅は坪単価だけではなく、付帯工事費や諸費用を含めた「総額」で予算内に収まるか確認しましょう。必ず複数のハウスメーカーからプランと見積もりを取り寄せ、価格、性能、保証、担当者との相性などを総合的に比較・検討することが重要です。
自分の予算と相談しながら注文住宅を建てたいという方は、YouTubeチャンネル「まかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】」の動画をチェックして知識を身につけましょう。元大手ハウスメーカー勤務のまかろにおが、予算を抑えながらも満足度の高い家を建てるための具体的なコツをわかりやすく解説しています。
また、当サイト「メグリエ(MEGULIE)」では、家づくりの無料相談をLINEで受け付けています。「予算内で建てられるハウスメーカーがわからない」「どこまでコストを削っていいのか不安」など、注文住宅に関する悩みを専門スタッフによる丁寧なサポートで解消できるでしょう。また、リアルタイムでの最新情報を受け取ることができます。
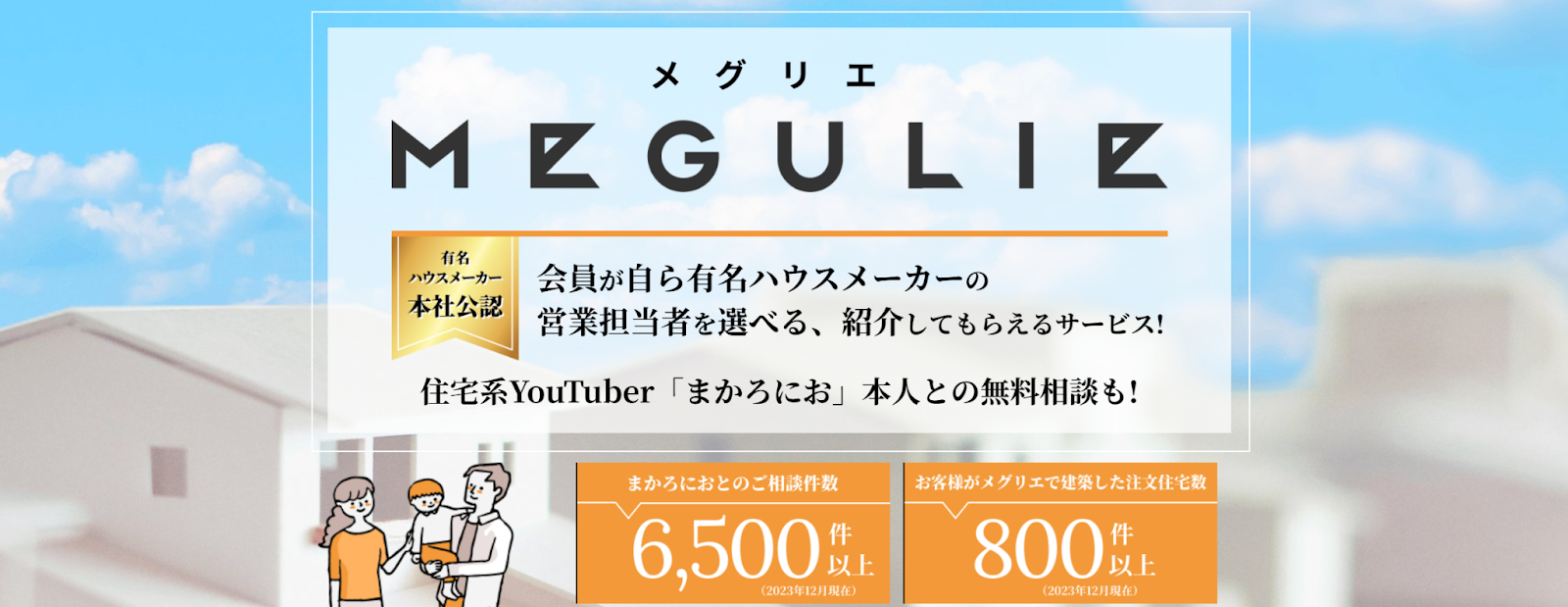
さらに、メグリエ(MEGULIE)に掲載されている豊富な建築実例から気になる施工事例を選び、その施工を担当したハウスメーカーや営業担当者に直接依頼することも可能です。経験豊富な担当者に依頼することで、コストを抑えながらも希望を叶える家づくりがスムーズに進みます。
なお、当サイト「MEGULIE(メグリエ)」を活用するメリット・デメリットは、こちらの動画で詳しく解説しています。一度チェックしてみてください。
注文住宅は一生に一度の大きな買い物です。後悔しないためにも、しっかりと情報収集をしながら、自分に合ったハウスメーカー選びを進めていきましょう。