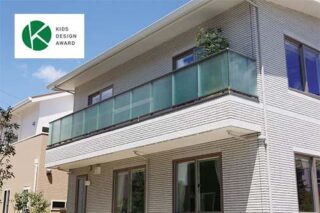この記事はメグリエ運営事務局によって作成しました。
「注文住宅は、総額いくらかかる?」「建物以外にどんな費用が必要?」そんな疑問をお持ちではないでしょうか?注文住宅にかかる費用は、建築費だけではなく土地代や付帯工事費、諸経費などを含めた「総額」で考える必要があります。
今回は、注文住宅の総額の内訳をはじめ、坪数別の費用目安や予算の立て方、総額を抑えるコツまでわかりやすく解説します。知らないままでいると、後々になって思ったより総額が高くなるといったケースもあるので、ぜひチェックしてみてください。
注文住宅の総額の内訳

注文住宅を建てる際には、「建物の価格」だけを見ていると予算オーバーになってしまう可能性があります。総額には、土地代・建築費・付帯工事費・諸経費など、さまざまな費用が含まれており、それぞれの内訳を正しく把握しておくことが重要です。
ここでは、注文住宅に必要な費用の内訳について、それぞれ詳しく解説します。
土地費用
注文住宅を建てるには、まず土地を用意する必要があります。土地費用は、立地・広さ・形状によって大きく異なり、都市部では高額になりがちです。一方、郊外や地方では比較的安く購入できることもあります。
また、土地そのものの価格だけでなく、仲介手数料・登記費用・固定資産税清算金などの諸費用も必要です。さらに、土地によっては地盤改良や造成工事が必要なケースもあり、これらは追加で数十万円〜100万円以上かかることもあります。
そのため、土地費用を検討する際は、土地本体の価格だけでなく、周辺コストも含めた「総額」で見積もることが大切です。
土地探しについては後述していますが、工務店やハウスメーカーに丸投げするのがおすすめです。自分で探すと手間がかかるだけではなく、不動産屋に足元を見られたり、設計がしづらい土地を選んでしまったりするリスクがあります。工務店やハウスメーカーは土地探しについて協力的なので、遠慮なく相談するようにしましょう。
建築費用
建築費用は、注文住宅の総額の中でも最も大きな割合を占めます。特に「本体工事費」と呼ばれる部分は、住宅の構造・仕様・デザイン・施工会社によって価格が大きく変動します。
一般的に、建築費用は「坪単価×延床面積」で計算されます。ローコスト住宅の場合の坪単価は50〜70万円程度、大手ハウスメーカーの場合は80〜100万円を超えることもあります。
また、住宅性能やデザイン性、住宅設備のグレードにこだわるほど、費用はさらに上がっていきます。建物価格は見た目だけでなく、断熱性や耐震性、間取りの工夫などによっても変わるため、「どこにお金をかけたいか」を明確にしておくと予算を管理しやすくなるでしょう。
付帯工事費
建物そのもの以外に必要な「付帯工事費」も、忘れてはならない重要な項目です。たとえば、外構工事(フェンス・アプローチ・駐車場など)や、インフラ整備工事(給排水、ガス、電気の引き込みなど)がこれに該当します。
これらは建物とは別で扱われることが多く、見積書では「別途工事」として記載される場合もあります。費用は内容によって幅がありますが、一般的には100万〜300万円前後かかることが多いです。
見積もりを確認する際は、どこまでが本体工事に含まれているのか、付帯工事が別になっていないかをしっかりチェックしておきましょう。後から思わぬ追加費用が発生することのないよう、事前に詳細を把握しておくことが大切です。
諸経費
諸経費は、建物や土地以外にかかる間接的な費用のことを指します。たとえば、登記費用・火災保険・住宅ローンの手数料・印紙代・引越し費用などが該当します。
これらの費用は、注文住宅の総額の5〜10%、金額にして200万円〜400万円程度になることが多いです。特に住宅ローンを利用する場合は、金融機関ごとにかかる事務手数料や保証料などが大きく異なるため、しっかり比較することが重要です。
また、引越し費用や仮住まいの家賃なども予算に含めておくとより安心です。諸経費は見落としやすい部分ですが、トータルでの資金計画を立てるうえで欠かせないポイントです。
「注文住宅の予算決めや費用について知りたい」「各ハウスメーカーのリアルな坪単価を知りたい」という方は、住宅系YouTuberの「まかろにお」が運営するYouTubeチャンネル「まかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】」の活用がおすすめです。
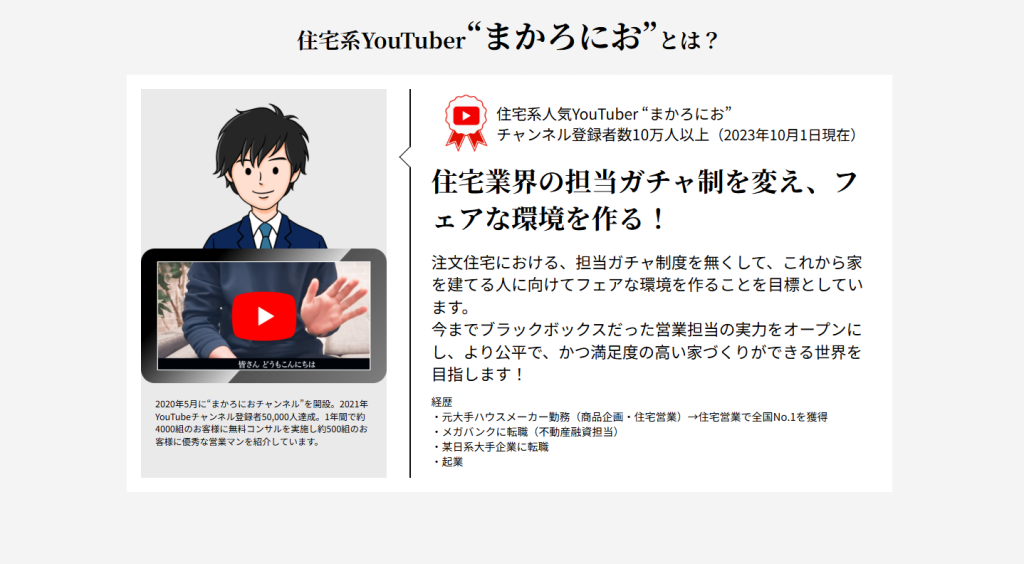
こちらのチャンネルでは、元大手ハウスメーカー勤務で、住宅営業で全国No.1を獲得した「まかろにお」が、実際の価格感や営業担当のリアルな対応、設備の選び方などをわかりやすく解説しています。費用の見極め方やハウスメーカー選びの参考になる情報が満載ですので、ぜひご覧ください。
動画では、各ハウスメーカーの優秀な営業担当者からもらったリアルな情報をもとにして、役立つコンテンツを多数配信しています。2025年7月現在、チャンネル登録者は14万人以上を誇ります。
坪数別の注文住宅の総額目安
注文住宅の総額は、住宅の「坪数(=延床面積)」によって大きく変わります。建物が広くなるほど、当然ながら本体価格や工事費も増えますが、家族構成やライフスタイルに合った広さを選ぶことが大切です。
ここでは、20坪台から50坪以上までの坪数ごとに、建物価格と注文住宅全体の費用目安をご紹介します。
20〜30坪

20〜30坪の注文住宅は、コンパクトながらも機能的な暮らしができるサイズ感です。単身世帯や夫婦2人暮らしに人気があります。3人家族などであっても、ムダのない間取り設計を工夫することで、十分な快適さを実現できるでしょう。
建物価格の目安は約1,500万〜2,400万円程度で、土地や諸費用を含めた総額は2,000万〜3,000万円が相場です。特に地方や郊外エリアでは、土地代を抑えやすいため、2,000万円台前半で収まるケースもあります。
コストを抑えたい方や、必要最小限の広さで効率的な家づくりをしたい方におすすめです。
30〜40坪

30〜40坪は、3〜4人家族にとってちょうど良い広さ帯として最も人気があります。リビングを広めにとったり、子ども部屋を確保したりと、バランスの取れたプランが実現しやすい点が魅力です。
建物価格はおおよそ2,000万〜3,200万円で、総額は3,000万〜4,500万円前後が一般的です。都市部で土地代が高い場合は4,000万円を超えることもありますが、郊外では3,000万円台前半で建てられるケースもあります。
注文住宅の標準的な広さをイメージしている方は、このゾーンが一つの目安になります。
40〜50坪

40〜50坪になると、より余裕のある暮らしが可能になります。広めのLDK、パントリーやファミリークローゼット、書斎スペースなど、機能性と快適性を両立した住まいが実現できるサイズ感です。
建物価格は約2,800万〜4,500万円、総額としては4,000万〜6,000万円台が相場です。設備や間取りにこだわるほど価格は上昇しますが、快適性を重視する方や将来を見据えて長く住みたい方には最適な広さです。
50坪以上

50坪を超える注文住宅は、2世帯住宅やラグジュアリーな設計を取り入れた家に多く見られます。複数の個室やセカンドリビング、ホームシアター、ガレージなどを取り入れたプランも実現可能で、まさに「夢のマイホーム」といえるレベルです。
建物価格は4,000万〜6,000万円以上となり、総額としては6,000万円〜1億円規模になることもあります。広い敷地が必要になるため、土地取得費も高額になりがちですが、その分ゆとりある生活空間が確保できます。
将来的な資産価値を意識したり、二世帯対応など柔軟性を重視したりする方にも魅力的な選択肢です。
注文住宅の予算の決め方

注文住宅を建てる際は、「いくらかかるか」ではなく「いくらなら無理なく建てられるか」という視点で予算を組むことが大切です。自己資金と住宅ローンのバランス、将来の生活費、ライフイベントなども踏まえたうえで、適正な予算を見極めていきましょう。
ここでは、注文住宅の予算を決めるために意識すべき4つのポイントを解説します。
返済負担率を考える
まず意識したいのが「返済負担率」です。これは、年収に対する住宅ローン返済額の割合を示すもので、一般的に世帯年収の20〜30%以内が目安とされています。
たとえば、世帯年収600万円の家庭であれば、年間返済額の上限は120〜180万円(月額10〜15万円)までが目安です。また、ボーナス併用返済を選べば、月々の返済負担を軽くすることも可能ですが、ボーナスの変動リスクには注意が必要です。
将来の教育費や老後資金も考慮し、無理のない返済計画を立てることが大切です。
総額で予算を出してみる
住宅の価格を検討する際は、「建物価格」だけでなく土地代・付帯工事費・諸経費を含めた「総額」で予算を組みましょう。
たとえば、「建物は2,500万円で建てられる」としても、土地取得や外構工事、登記費用などで1,000万円以上追加されることもあります。坪数やエリアによっても大きく変動するため、目安として「建物価格+1,000〜1,500万円」程度は確保しておくと現実的です。
この段階ではまだ「概算」で構いませんが、あらかじめ全体像を把握しておくことで、後からの予算オーバーを防ぐことができます。
住宅ローンを検討する
予算を検討するうえで、自分がいくらくらい借り入れできるのかを早めに確認しておくことも重要です。住宅ローンの審査では、年収や職業、既存の借入状況などが影響しますが、予想より借入額が少ないというケースもあります。
また、金融機関によって金利や保証料、諸費用の条件が異なるため、複数のローン商品を比較することが大切です。近年はネット銀行やフラット35など、選択肢も多様化しており、自分に合ったローンを選ぶことで長期的な負担を抑えることができます。
「家を探す前にローンを調べる」のが理想的な流れです。
補助金や優遇制度もチェックする
注文住宅を建てる際には、国や自治体からの補助金・優遇制度が活用できる場合があります。たとえば、次のような制度を利用できる可能性があります。
- こどもエコすまい支援事業
- 住宅ローン減税
- すまい給付金
こどもエコすまい支援事業は、一定の基準を満たす高性能な住宅に対して、1戸あたり100万円を補助されます。また、住宅ローン減税は、ローン残高に応じて所得税・住民税が控除される制度です。すまい給付金では、収入に応じて最大50万円程度を受け取れるため、ぜひ検討しておきましょう。
これらの制度は、時期や条件によって支給額や対象が異なるため、必ず最新情報をチェックし、早めに対応しておくことがポイントです。数十万〜100万円単位の支援を受けられることもあるため、予算組みの段階で見逃さないようにしましょう。
家づくりの裏技やお得な情報についてもっと知りたいといった方には、住宅系YouTuberの「まかろにお」が運営するYouTubeチャンネル「まかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】」の活用がおすすめです。
家づくりの参考になる情報が満載ですので、ぜひご覧ください。動画では、各ハウスメーカーの優秀な営業担当者からもらったリアルな情報をもとにして、役立つコンテンツを多数配信しています。
注文住宅の総額をなるべく抑えるコツ

注文住宅は自由度が高い分、ついついこだわりが膨らみ、当初の予算を超えてしまいがちです。しかし、工夫を取り入れることで、コストを無理なく抑えながら理想の住まいを実現することも可能です。ここでは、注文住宅の総額を抑えるために実践したい具体的なコツを3つ解説します。
見積もりは2〜3社からもらう
住宅の見積もりは、必ず複数の会社から取り寄せて比較することが鉄則です。1社だけに決めてしまうと、その会社の提示価格が高いのか安いのか、適切かどうかの判断ができないためです。
2〜3社の見積もりを比較することで、価格帯の相場感がわかるだけでなく、提案内容の違いや見積書の構成の差も見えてきます。また、会社によっては「本体価格が安く見えても、付帯工事や諸費用が高い」といったケースもあるため、総額ベースで比較することが重要です。
見積書の項目ごとに「何が含まれていて、何が別途なのか」を丁寧に確認し、隠れコストを見逃さないようにすることが、予算オーバーを防ぐために大切です。
土地探しはハウスメーカーに丸投げする
「土地は自分で探すもの」と思っている方も多いですが、土地探しはハウスメーカーに一任するのがおすすめです。なぜなら、ハウスメーカーであれば建物と土地のバランスを踏まえて、効率的なプランを提案してくれるからです。
また、地盤改良が必要な土地や、外構工事が想定より高額になる土地を事前に避けられる可能性もあります。結果的に、余計なコストのかかりにくい土地を選べるため、トータルコストの抑制につながります。
土地購入と建築の予算をワンストップで管理できる点も大きなメリットといえるでしょう。土地からの家づくりを検討している方には、特におすすめの方法です。
下記動画では、元大手ハウスメーカー勤務で、住宅営業で全国No.1を獲得した「まかろにお」が、土地探しをハウスメーカーに依頼した方が良い理由について詳しく解説しています。ぜひチェックしてください。
こだわりの優先順位を明確にする
注文住宅は自由設計だからこそ、「こだわり過ぎ」でコストが膨らむことも珍しくありません。そのため、あらかじめ「譲れないポイント」と「妥協できるポイント」を明確に整理しておくことが重要です。
たとえば、「耐震性と断熱性能は重視するけど、キッチンは標準仕様で十分」といった具合に、自分たちの暮らしに必要な価値を見極めておきましょう。必要以上のグレードアップやオプション追加は、あとから「無駄だったかも」と感じることも多いため注意が必要です。
こだわりにメリハリをつけることで、満足度を保ちながら、無駄な出費を減らすことができます。
予算別のおすすめハウスメーカー
ハウスメーカー選びは、注文住宅の総額に大きな影響を与える要素の一つです。とはいえ、各社のプランや価格帯は多岐にわたるため、まずは「本体価格ベースでどのくらいの費用感なのか」を把握することが大切です。
ここでは、建物本体価格を基準に、予算別のおすすめハウスメーカーを紹介します。なお、ここで紹介する本体価格には土地代や諸費用は含まれていないため、+1,500万円ほどの追加費用がかかる前提で参考にしてみてください。
1,000万円台
1,000万円台で建てられる注文住宅は、ローコスト住宅や規格住宅が中心です。必要最低限の機能とシンプルな設計をベースにしながらも、工夫次第で快適な住まいを実現できます。1,000万円台での家づくりが可能な代表的なハウスメーカーは次のとおりです。
- オープンハウス
- 飯田グループ
- アイダ設計
- アイフルホーム(規格住宅:ロディナ)
- タマホーム
- 桧家住宅(規格住宅:スマートワン)
- 秀光ビルド
- パパまるハウス
- 一条工務店(規格住宅:HUGme)
- レオハウス
- 一建設
- ヤマト住建(規格住宅:エネージュSGR)
- アエラホーム(規格住宅:ERABERU)
- クレバリーホーム(規格住宅:クレバコ+)
これらのハウスメーカーは、価格を抑えながらも一定の品質や性能を確保したい方におすすめです。規格住宅が中心とはいえ、プラン次第では満足度の高い住まいを実現できます。
2,000万円台
2,000万円台になると、デザイン性・住宅性能ともに満足できる選択肢が大きく広がります。自由設計に対応したプランも多く、標準仕様でも十分な住宅性能を持つハウスメーカーが多い価格帯です。代表的なハウスメーカーは次のとおりです。
- アキュラホーム(PRESTO)
- 桧家住宅(スマートワンカスタム)
- 三井ホーム(規格住宅:三井ホームセレクト)
- ダイワハウス(規格住宅:スマートセレクション)
- パナソニックホームズ(規格住宅:ヴェッセ)
- クレバリーホーム
- ウィザースホーム
- ヤマト住建
- セルコホーム
- アイ工務店
- アイフルホーム(FAVO)
- 住友不動産
- トヨタホーム(規格住宅:シンセLQ)
- 一条工務店(グランスマート・アイスマート)
- スウェーデンハウス(規格住宅:ヘンマベスト)
- タマホーム(えがおの家)
- ヘーベルハウス(規格住宅:マイデッサン)
- 住友林業(規格住宅:フォレストセレクション)
- ミサワホーム(規格住宅:規格住宅)
性能・デザイン・自由度のバランスが良いゾーンで、検討者も多い価格帯です。標準仕様のレベルも高く、ライフスタイルに合わせたカスタマイズが可能です。
3,000万円以上(ハイコスト)
3,000万円以上の価格帯では、自由設計・高級素材・高度な性能を兼ね備えたハイエンド住宅が中心です。意匠性や快適性を追求したい方、ブランドや長期資産価値を重視したい方に適した選択肢です。代表的なハウスメーカーは次のとおりです。
- 積水ハウス
- 住友林業
- ダイワハウス
- 三井ホーム
- ミサワホーム
- ヘーベルハウス
- パナソニックホームズ
- セキスイハイム
- トヨタホーム
- スウェーデンハウス
- 三菱地所ホーム
高価格帯には、ブランド力・住宅性能・意匠性すべてにおいて優れたハウスメーカーが揃っています。将来的な資産価値や、快適な暮らしを長く維持したい方に最適です。
下記動画では、元大手ハウスメーカー勤務で、住宅営業で全国No.1を獲得した「まかろにお」が、注文住宅や規格住宅を予算別にまとめて紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
まとめ
注文住宅の総額は、「建物価格」だけでなく 土地代・付帯工事費・諸経費を含めたトータルの費用で考えることが重要です。また、坪数が増えるほど建築費は高くなり、エリアによって土地価格も大きく変動します。
理想の住まいを叶えるためには、返済計画やライフプランを踏まえたうえで、無理のない予算設定を行うことが欠かせません。そのためにも、複数社の見積もり比較やハウスメーカーごとの特徴を把握し、こだわりの優先順位を明確にしておくことが大切です。
今回お伝えした内容を参考に、コストと満足度のバランスをとりながら、自分たちにとって最適な家づくりを進めていきましょう。
もっと家づくりの費用やコツについて知識を身につけたいという方には、住宅系YouTuberの「まかろにお」が運営するYouTubeチャンネルまかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】の活用がおすすめです。動画では、各ハウスメーカーの優秀な営業担当者からもらったリアルな情報をもとにして、役立つコンテンツを多数配信しています。
また、公式LINEを追加いただくと、無料で家づくりについて相談することが可能です。動画を視聴したうえでわからない点や、家づくりに関する悩みごとの相談を受け付けていますので、ぜひ活用してみてください。
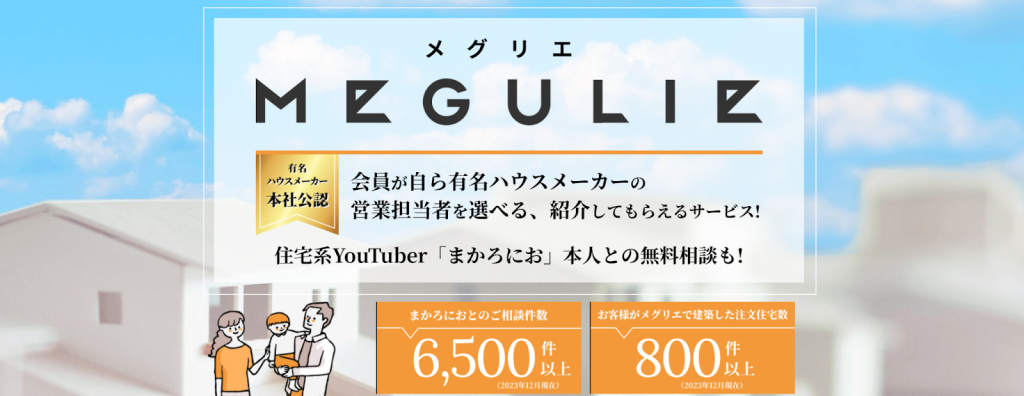
さらに、当サイト「MEGULIE(メグリエ)」では、会員登録しなくても3つの質問に答えるだけで、まかろにおが現時点で施主に最適なハウスメーカーを診断してくれる「ハウスメーカー診断」が受けられます。会員登録に抵抗がある方は、ぜひハウスメーカー診断だけでも試してみてください。
なお、当サイト「メグリエ(MEGULIE)」を活用するメリット・デメリットは、こちらの動画で詳しく解説しています。一度チェックしてみてください。
一生に一度の家づくりで後悔しないためにも、じっくりと情報を集め、最適なパートナーを見つけましょう。