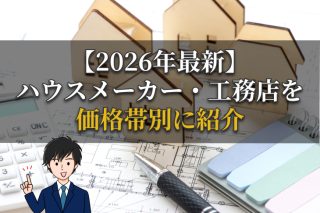この記事はメグリエ運営事務局によって作成しました。
これから注文住宅の建築を検討している方にとって、どのくらいの費用がかかるのか、そしてどうすれば予算オーバーを防げるのかは大きな関心事でしょう。土地代や建物本体価格だけではなく、外構や諸経費を含めた総額がいくらになるのか、しっかりと把握しておかないと工事が進んでから「こんなはずじゃなかった」という事態に陥ることもあります。
今回は、注文住宅の費用相場と内訳、価格帯別の特徴、さらには住宅ローンを上手に組むための考え方やコツを詳しく解説します。ハウスメーカーの選び方や標準仕様・オプションの活用術など、家づくりで後悔しないために押さえておきたいポイントを幅広く網羅しているため、ぜひ最後までお読みください。
注文住宅の費用相場はいくら?

注文住宅の費用を考える際には、土地代や諸経費なども含めた総額を最初から視野に入れておくことが大切です。土地をすでにお持ちの方でも、地盤改良費や外構工事など建物以外の費用が思いのほかかさむことがあります。どの程度の費用感になるのかを具体的にイメージするためにも、まずは建物本体価格にどんな項目が含まれるのかを理解しておきましょう。
建物本体価格に含まれる項目
注文住宅の建物本体価格には、基本的な構造躯体と内部設備、それに関連する申請費用や仕上げ材が含まれます。
大きな割合を占めるのが、基礎工事のコンクリートや鉄筋、柱・梁などの躯体にかかる費用です。内部設備としては、キッチン、浴室、トイレなどの住宅設備機器や、標準仕様として設定された内容が見積りに組み込まれています。
また、建築確認申請や工事監理費など、家を建てるために必要な公的手続きや専門家の監理業務に伴う費用も本体価格に含まれるケースがほとんどです。さらに、壁紙や床材などの内装材、サイディングや塗装などの外装材も本体価格に加わります。
これらの基本内容を押さえていないと「契約時の金額に何が含まれているかわからない」という事態に陥り、想定外の追加費用を請求されることになりかねません。特に注文住宅はオプションを選ぶ楽しさもある反面、標準仕様の範囲内でどこまでカバーできるのかをしっかりと確認しておくことが予算管理の第一歩といえます。
土地代や諸費用
注文住宅の総額を考える際、見落としがちなのが土地代と諸費用です。土地購入から検討している場合、土地代そのものが大きな割合を占めるだけではなく、仲介手数料や登記費用などの諸経費も追加でかかります。
特に注意が必要なのが、地盤調査や地盤改良工事の費用です。表面上の土地価格は安く見えても、実は地盤が弱く改良費に数百万円かかることもあります。また、住宅ローンを利用する場合、ローン保証料や印紙税、火災保険などの加入費用も発生します。
外構費用は、庭や駐車場、門扉など家の外周りを整える費用です。照明や家具、カーテンといったインテリア関連も別途費用に含める必要があります。
こうした諸費用を最初から計画に入れず「建物本体価格だけで予算を組んでしまう」人が多いため、実際の工事に入ってから初めて総額を知り、大きな誤算を抱えてしまいがちです。全体像を把握して、無理のない予算計画を立てることが重要です。
注文住宅の価格帯別の特徴

注文住宅の価格帯はおおまかに1,000万円以下、1,000万〜3,000万円台、3,000万〜4,000万円台、そして4,000万円以上の4つに分けられることが多く、それぞれに特徴があります。土地や諸経費を含まない建物本体価格としての相場感ではありますが、家づくりのグレードや選択肢がどの程度広がるのかを把握するための目安となります。ここでは、価格帯別の注文住宅の特徴について解説します。
1,000万円以下の注文住宅
1,000万円以下の価格帯では、ローコスト系のハウスメーカーや規格住宅を検討することが中心になります。この価格帯で家を建てる場合、建物の形状やプランがある程度決まっているケースが多く、間取りや仕様の自由度は低めです。
設備や内装も基本的には標準的なものに限られ、オプションを追加しすぎると一気に予算オーバーにつながるため、極力シンプルな家づくりが求められます。土地の条件が良ければ予算内で収まる可能性は十分にありますが、立地やデザインよりもコスト削減を最優先に考える人向けといえるでしょう。
コストを抑えつつも生活に必要な機能を確保するには、優先順位をしっかり決めて、本当に必要な部分にだけ費用をかける姿勢が重要です。ローコストだからといって品質を妥協する必要はなく、基本性能を確保した上でシンプルさを追求する方向性が賢明です。
この価格帯では、性能とコストのバランスを取りたい方には、一条工務店のHUGmeシリーズなどを検討してみましょう。
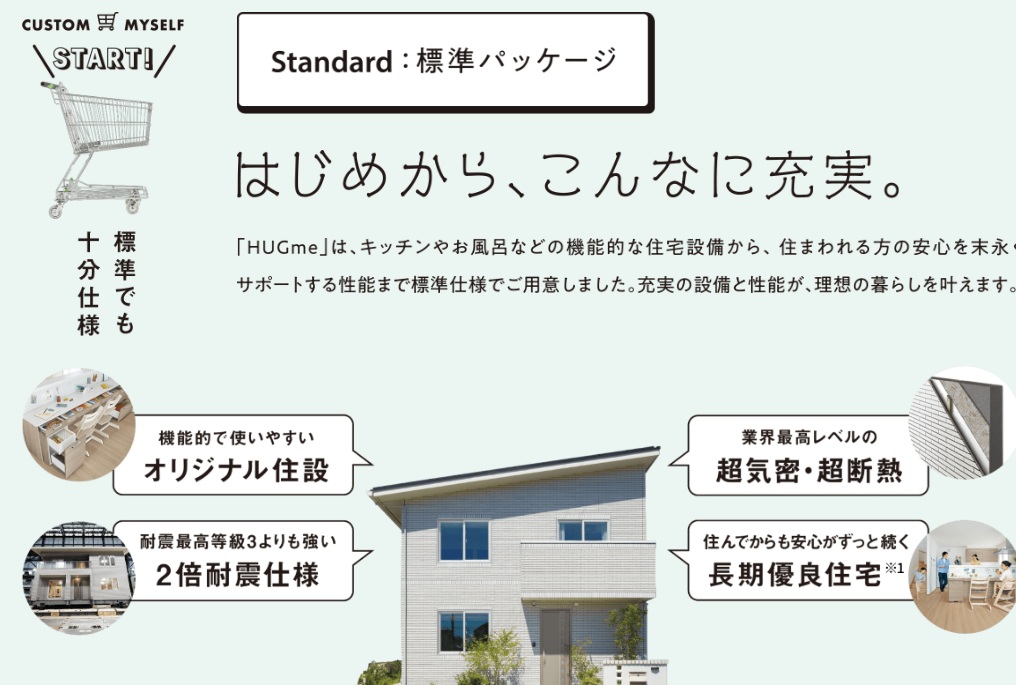
画像引用元:一条工務店
標準仕様でも高い断熱性能と耐震性能を備えながら、決められたプランから選ぶことでコストを抑えられます。
1,000万〜3,000万円台の注文住宅
1,000万〜3,000万円台になると、ハウスメーカーのセミオーダー商品や一部の大手メーカーの規格住宅が選択肢に入ってきます。ある程度自由度のある間取りやデザイン性を確保できるため、家づくりの楽しみも増えますが、その反面、外構費用や諸費用を後回しにしてしまうと簡単に予算オーバーに陥ることがあります。
住宅ローン返済計画とのバランスが取りやすい価格帯とはいえ、設備を厳選し、オプションを必要最低限にするなど冷静な管理が必要です。特に家族構成や将来の生活スタイルを考慮した間取りにしやすいのがこの価格帯のメリットでしょう。
この価格帯では、標準仕様とオプションのバランスを見極めることが重要です。すべてにこだわりを持つのではなく、重点的に投資したい部分と標準仕様で十分な部分を明確に区別することで、効率的な予算配分が可能になります。
この価格帯では、大手ハウスメーカーの規格住宅やセミオーダー商品が選択肢となり、次のものなどがおすすめです。
- ダイワハウスやセキスイハイム:標準商品
- 住友林業:フォレストセレクション
- 三井ホーム:スマートスタイル
- ミサワホーム:規格住宅
工業化による品質の安定と適度な自由度のバランスが取れた家づくりが可能です。
3,000万〜4,000万円台の注文住宅
3,000万〜4,000万円台では、大手ハウスメーカーや設計事務所のプランも視野に入ります。断熱性能や全館空調などのハイグレード設備を導入しやすく、吹き抜けや大きな窓などデザイン性を高める工夫も取り入れやすいことが特徴です。
一方で、土地費用を含めると総額4,000万円を超えてくる可能性が高くなるため、予算を超過しがちな点には注意が必要です。高性能な住宅はランニングコストが下がるメリットもありますが、初期投資が大きくなるため、住宅ローン計画を慎重に立てることが欠かせません。
この価格帯では、長期的な視点での投資価値を考慮することも大切です。たとえば、高断熱・高気密仕様や省エネ設備は初期費用がかかっても、将来的な光熱費削減や快適性向上につながります。住宅の性能とデザイン性を両立させながら、長く住み続けられる家を目指すのが理想的です。
この価格帯では、性能とデザイン性の両方を重視したい方に、積水ハウス、パナソニックホームズ、ヘーベルハウス、住友林業、三井ホームの完全注文住宅がおすすめです。特に、積水ハウスのシャーウッドや住友林業のBF(ビッグフレーム)構法は木造の魅力を活かした高性能住宅を実現でき、パナソニックホームズは耐震性と全館空調に定評があります。
4,000万円以上の注文住宅
4,000万円以上の予算を確保できる場合、完全自由設計やハイクラス仕様による豪華な家づくりが可能になります。間取りのこだわりや外観デザイン、さらにはハイエンドな内装材やオーダーメイドの収納など、自由度が飛躍的に高まるでしょう。
一方で、坪単価が上がりやすいため、打ち合わせ回数も増え、想定よりも工期やコストが膨らむリスクがあります。将来的なメンテナンス費用も大きくなる傾向があるため、建物完成後のランニングコストを含めて長期的に計画することが重要です。
この価格帯では、設計や素材、施工技術に至るまで妥協のない家づくりが実現できますが、それだけに予算管理の難しさも増します。デザイン性や高級感に流されすぎず、実用性とのバランスを常に意識することが、満足度の高い家づくりにつながります。
この価格帯なら、トップブランドである積水ハウス、住友林業、三井ホームの最高グレード商品がおすすめです。積水ハウスのイズシリーズや住友林業のグランドライフ、三井ホームの完全自由設計で、最先端の設備や匠の技術を活かした唯一無二の住まいを実現できます。
注文住宅の費用を抑えるポイント

注文住宅は自由度が高い反面、どこにお金をかけて、どこで削減するかの判断を誤ると簡単に予算オーバーしてしまいます。ここでは、費用を抑えるための具体的なコツについて解説します。
要望に合ったハウスメーカーを選定する
住宅の価格はハウスメーカーのスタンスやブランド力によって大きく差が出ます。ローコスト系や規格住宅を取り入れると大幅にコストを抑えられる反面、間取りの自由度は低くなります。大手メーカーでもセミオーダー型の商品を選べば、自由度を一定程度維持しながら予算を抑えやすいでしょう。
また、高気密高断熱性能に強いメーカーは初期費用こそかさむものの、光熱費などのランニングコストは低くなりやすいメリットがあります。地域の工務店を含めて比較検討することで、品質と価格のバランスを把握しやすくなるため、「少しでも費用を抑えたい」「性能は落としたくない」と考える方は早めに複数の候補を見比べることをおすすめします。
間取りや外観をシンプルにする
建築費用を抑えるには、間取りや外観の形状をできるだけシンプルにまとめることが有効です。凸凹の多い外観や大きな吹き抜けは、見た目のインパクトこそ高まりますが、その分施工手間や材料費が増えます。
同じ素材をまとめて使用することで施工コストを下げることも可能です。たとえば、壁紙の色や床材の種類をむやみに増やさない、屋根形状を複雑にしないなど、こだわりを程々にするだけでも予算を大きく圧縮できます。
さらに、部屋数を必要最小限に留め、広さよりも使い勝手を優先したプランを構築することも効果的です。将来的な家族構成の変化も見据えて、可変性のある間取りを検討することで、リフォーム費用の削減にもつながります。
標準仕様を上手に活用する
注文住宅では、オプションを追加すればするほど費用が膨らむ傾向にあります。ハウスメーカーの標準仕様に含まれる設備や内装でも、実は十分に使いやすいものが多いため、「とりあえず全部こだわってオプションをつける」のではなく「標準仕様で満足できる範囲はどこか」を見極めることが重要です。
さらに、カタログだけではなく、モデルハウスで実物を確認することも大切です。意外と標準仕様でも質感や性能に不足がなく「最初にオプションを見ずに標準で検討すればよかった」と後から気づくことも少なくありません。
設計段階で将来の追加費用が発生しないよう、コンセント位置などの細かい部分も含めて打ち合わせを行いましょう。
外構や諸費用も最初に計画に入れる
建物の予算だけを先に決めてしまうと、外構工事や諸費用の見積もりで一気に数百万円の追加支出が出ることは珍しくありません。土地の高低差があると擁壁工事が必要になる場合もあります。
また、登記費用や住宅ローン関連費用も「想定より多くなってしまった」という事例が多いため、土地条件や法規制を調べたうえで余裕を持って予算取りをしておきましょう。予備費を一定程度確保しておくと、地盤改良などのリスクにも備えやすくなります。
住宅ローンの組み方と返済計画

家づくりでは、住宅ローンが占める比率も見逃せないポイントです。せっかくローコストな家を建てても、ローンの組み方が不適切だと月々の返済に苦労し、結局は家計を圧迫してしまいます。最後に、借入額の考え方や金利タイプ、返済手段などを見直して、無理のないローンを組む方法を解説します。
物件価格に合った借入額の決め方
住宅ローンの借入額を決定するときは、まず物件価格と頭金、さらに諸費用をトータルで考えることが重要です。日常生活で支障をきたさない範囲の毎月返済額をイメージし、その返済額でカバーできるローン総額を算出してみましょう。
多くの金融機関は物件価格の8〜9割程度を貸し出すケースが多いですが、金利上昇リスクにも配慮して、あまりに大きな借り入れにならないよう注意する必要があります。せっかく建てた家でゆとりある暮らしをするには、返済が苦しくなっては本末転倒です。やや控えめに設定した金額でも、実際に生活が成り立つかどうか試算しておきましょう。
金利タイプの選び方
住宅ローンの金利タイプとしては、主に次の3種類が挙げられます。
自分のライフプランや収入の安定性、将来の金利変動に対する考え方によって最適解は異なるため、慎重なシミュレーションが欠かせません。金融機関による金利優遇条件なども比較検討し、総返済額を試算した上で判断することが重要です。
変動金利
変動金利は当初の金利が低めに設定されることが多いですが、将来的な金利上昇リスクを抱えるため、経済情勢に敏感にならざるを得ません。
固定金利
固定金利は返済額を確定しやすく返済計画を立てやすいものの、変動金利より当初の負担が大きい傾向があります。
ミックスローン
ミックスローンは借入額を変動と固定に分けることでリスク分散を図りますが、手続きが複雑になるケースも考えられます。
借り換えや繰り上げ返済のメリット
住宅ローンの金利は経済状況によって変動するため、借り入れ時期によっては高い金利で契約しているケースもあるでしょう。そんなときは、金利が低い時期に借り換えを検討すると総返済額を大幅に削減できる可能性があります。
また、繰り上げ返済で元本を早めに減らすと利息負担が抑えられるため、ボーナスやまとまった資金が入ったタイミングで活用するのがおすすめです。
ただし、借り換えや繰り上げ返済には手数料や事務手数料がかかる場合があります。トータルで見て本当に得かどうかは、各金融機関の条件を比較しながら判断してください。
返済比率のシミュレーション方法
住宅ローンの返済額は、世帯収入の25〜30%以内に収めるのが目安とされています。共働き家庭なら、今後出産や育児休業で一時的に収入が減るシナリオも考慮し、ボーナス返済に依存しすぎない計画を立てるのがおすすめです。
たとえば、毎月返済額が世帯収入の3割を超えると、何か想定外の出費があった場合に一気に家計が逼迫しやすくなります。月々の返済をもう少し抑えてその分貯蓄に回す選択も視野に入れるのが賢明です。
住宅ローンの事前審査と本審査
住宅ローンでは、家の契約前に事前審査を受け、金融機関から大まかな借入可能額を知ることができます。ここで自分の希望条件に近い金利やサービスを持つ銀行を複数比較し、本審査に進む流れが一般的です。
本審査では勤続年数や返済能力を含む詳細なチェックが行われるため、事前審査のときより厳しく見られる場合があります。契約書類の不備や自己資金の不足がないよう、あらかじめ準備を整えておきましょう。
まとめ
注文住宅はいくらかかるのかという疑問に対しては、建物本体価格と土地や諸費用を含めた総額、そして住宅ローンを絡めた返済計画を総合的に考える必要があります。オプションや諸経費を事前に明確化しないまま家づくりを進めてしまうと、完成直前や引き渡し後に予想外の出費が一気に膨らみ、予算オーバーや暮らしにくさの原因となるでしょう。
特に土地の形状や建物の外構計画、さらにはローンの金利タイプなどは家計への負担を大きく左右するため、できるだけ早い段階で見通しを立てておくことが大切です。施工後に「こんなはずじゃなかった」と後悔しないためには、費用計画を最優先で組み立て、仕様や間取りに関しても設計段階でしっかりと検討しておくことが不可欠です。
大きな吹き抜けやオプション満載の設備に魅力を感じることは自然なことですが、将来の家族構成やライフプランを踏まえたうえで、本当に必要なものを見極めることが肝心です。住宅ローンについても、借り入れ可能額だけではなく、返済比率や金利リスクを十分にシミュレーションしながら、自分たちに合ったプランを選ぶようにしましょう。
自分に合った住宅ローンの組み方をもっと詳しく知りたいという方は、住宅系YouTuber「まかろにお」のYouTubeチャンネル「まかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】」をチェックしてください。住宅に関する情報を深掘りしながら、わかりやすく発信しているため、多くの疑問を解決できるはずです。
また、LINEの友だち登録による家づくりに役立つ情報の配信もあるため、後悔しない家づくりを目指すうえで大いに活用してください。家づくりは人生の大きな買い物です。十分な知識を身につけて、満足度の高いマイホームを実現しましょう。