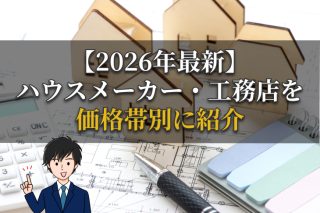この記事はメグリエ運営事務局によって作成しました。
「注文住宅でも値引き交渉はできるの?」「どのタイミングで交渉すればよいの?」そんな疑問をお持ちではありませんか?注文住宅の値引き交渉について気になる方は多いと思いますが、実際にはどのように進めていけばよいのでしょうか?
今回は、注文住宅での値引き交渉を成功させるコツや、値引き交渉以外にも活用できる予算削減の工夫を解説していきます。理想のマイホームを少しでもお得に手に入れたい方は、ぜひ参考にしてください。
注文住宅は値引き交渉できる

注文住宅の値引き交渉は可能です。交渉のタイミングや方法を工夫すれば、コストダウンできる可能性が十分にあります。
ただし、実際に値引きしてもらえるかどうかは、ハウスメーカーや営業担当者の裁量、さらには会社の方針によって大きく異なります。また、注文住宅は一棟ごとに間取りや仕様が異なるオーダーメイド形式のため、建売住宅よりも値引きの難易度が高い傾向にあります。
注文住宅は値引きやハウスメーカーについて深く知りたい方は、「人から始める家造りの重要性を世に広める」をコンセプトとした住宅系YouTuber「まかろにお」が運営するYouTubeチャンネル「まかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】」をチェックしてみてください。大手ハウスメーカーの特徴やメリット・デメリット、さらに注文住宅を建てるうえで知っておきたい知識などを定期的に発信しています。
これから家づくりをする方にとって役立つ情報が満載なので、ぜひ参考にしてみてください。
注文住宅の値引きの相場は3~8%

注文住宅の値引き率は、一般的に本体価格の3〜8%が相場とされています。たとえば、3,000万円の住宅であれば90万円〜240万円ほどの値引きが期待できる計算です。中には、10%ほどの値引きに応じてもらえる場合もあります。
ただし、こうした値引き率はあくまでも目安にすぎません。実際には、ハウスメーカーごとの方針や営業戦略、エリアによって状況は異なります。たとえば、同じハウスメーカーであっても、都市部と地方とでは人件費や建材の調達コスト、輸送費などが異なるため、値引きの幅に差が出てしまうのです。
値引き率はあくまで参考値としてとらえ、現実的なラインで交渉を進めることが大切です。
注文住宅の値引き交渉が難しいと言われる主な理由

注文住宅は、値引き交渉が難しいと言われています。ここでは、なぜ難しいのか、その理由について解説します。
注文住宅には売れ残りの概念がないから
注文住宅の値引き交渉が難しい理由の1つは、「売れ残り」という在庫リスクが存在しない点にあります。
建売住宅の場合、すでに完成した物件を販売しているため、一定期間内に売れなければ在庫として抱えることになります。建物が完成してから1年を過ぎると「新築」として販売できなくなり、資産価値が下がってしまうため、ハウスメーカー側は値引きしてでも早く売却したいと考えます。
しかし、注文住宅は施主からの依頼を受けてはじめて設計・施工が始まる仕組みです。そのため、契約前の段階では物件自体が存在しておらず、販売在庫という概念がありません。ハウスメーカー側は「早く売らなければ赤字になる」といった事情がなく、値引きする必要性も低いのです。
このように、注文住宅は在庫処分としての値引きが期待できないため、交渉が成立しにくいのが実情です。値引き交渉をする際は、この前提を理解しておく必要があります。
ハウスメーカーとの関係が悪くなる可能性があるから
注文住宅の値引き交渉が難しい理由は、ハウスメーカーや営業担当者との関係性が悪くなる可能性があるためです。
注文住宅の家づくりは、契約から着工、引き渡しに至るまで長い期間を要します。その間、間取りの調整や仕様の変更など、何度も打ち合わせを重ねながら計画を進めていく必要があります。だからこそ、担当者との信頼関係は非常に重要です。
無理な値引き交渉を何度も持ちかけたり、高圧的な態度で交渉を迫ったりするような言動は、相手からの信頼を損ねる原因になりかねません。場合によっては「他のお客様を優先したい」と判断され、契約自体を断られることもあります。
たとえ値引きに応じてもらえても、関係性が悪化した状態では、その後の打ち合わせに支障をきたし、満足のいく家づくりができなくなる可能性もあります。そのため、信頼関係を築きながら、現実的な範囲で値引き交渉を進めることが大切です。
建物の品質に影響が出る可能性があるから
注文住宅で無理な値引き交渉を行うと、建物の品質に悪影響を与えてしまう可能性があります。
建売住宅と違い、注文住宅は契約後に設計・施工が始まるため、価格調整の段階では工事内容や使用する建材がまだ確定していません。こうした段階で無理な値引きを求めると、ハウスメーカー側はどこかでコストを削らざるを得なくなります。
たとえば、キッチンや浴室などの設備グレードを一段階下げられる可能性がありますし、人件費が削減されれば工期が延びたり、施工精度が下がったりするリスクが生じます。価格だけにこだわるのではなく、品質と長期的な満足度も重視することが大切です。
注文住宅の値引き交渉で失敗しないためのコツ

ここでは、注文住宅の値引き交渉で成功するためのコツを解説します。
月末の契約を狙う
値引き交渉は、月末の契約が狙い目です。
多くの営業担当者には月単位のノルマや目標が設定されており、その結果が評価やインセンティブに直結しています。そのため、月末は契約を決めたいという営業側の動きが活発になる傾向があるためです。
同じ条件での交渉でも、月初に相談するより、月末に「今月中に契約できる」と伝える方が、値引きに応じてもらえる可能性が高くなります。また、決算期は会社全体として売上を上げたい時期のため、さらに交渉のチャンスが期待できます。
値引き交渉は内容だけでなく、いつ交渉するかも重要なポイントです。
契約の意思表示を明確に行う
値引きを引き出すためには、「このお客様は本気だ」と営業担当者に思ってもらうことが大切です。なぜなら、営業担当者が社内で値引きを承認してもらうには、上司や管理部門への根回しが必要になるためです。本気度が伝わらない相手に対しては、その手間をかけるメリットがないと判断されてしまうこともあります。
たとえば、「もし〇〇円まで下げていただけるなら、今月中に契約を決めたいと考えています」といったように、値引きの条件と契約の意思をセットで伝えることがポイントです。明確な意思表示をすることで、営業担当者も「この条件なら契約につながる」と判断しやすくなり、交渉がうまく進む可能性があります。
契約の意思表示を明確に行う必要性については、「【100万円以上トクする】新築マイホームを値切る3つのステップ」でも詳しく紹介していますので、ぜひご視聴ください。
他社の見積もりを根拠に交渉する
他社の見積もりを根拠とした値引き交渉は、非常に効果的です。「他社では同じ仕様でこの金額でした」といった具体的な比較材料があれば、営業担当者も社内で調整しやすくなります。
比較する際には、グレードや規模が近い会社同士で行うことが重要です。高価格帯のハウスメーカーに、ローコスト住宅の見積もりを見せても説得力は弱くなってしまいます。
他社の見積もりは、あくまで交渉を前向きに進めるための資料として活用し、「御社で建てたいけれど、迷っている」といったスタンスで伝えると効果的です。適切な比較と伝え方によって、相手も「それならこの部分だけでも値下げできるかもしれない」と対応を検討してくれる可能性があります。
極端な金額の値引きを要求しない
値引き交渉を行う際には、どこまでが現実的な範囲なのか見極めましょう。
注文住宅では、値引きの相場は3〜8%程度といわれています。たとえば、3,000万円の物件であれば100万円前後の値引きが現実的なラインです。しかし、300万円や400万円など過剰な値引きを要求すると、ハウスメーカー側も利益が出なくなってしまい、対応が難しくなります。
それだけでなく、信頼関係にも悪影響を与えかねません。値引き交渉は、相場を意識し、現実的な金額で交渉を行うことが重要です。
端数切りを狙う
目標としていた金額の値引きが難しいときは、「端数切り」を提案するのも一つの方法です。たとえば、見積もりが4,080万円だった場合、「キリの良い4,000万円ちょうどにしてほしい」とお願いする形です。
この場合、80万円の値引きとなりますが、印象としては過度な要求には見えにくく、受け入れてもらいやすい傾向があります。営業担当者にとっても、端数を調整する程度であれば社内の承認を得やすいため、比較的進めやすい交渉といえます。
大きな値引きが難しい場合でも、少しの工夫で納得できる金額に近づけられる場合もあるため、最後のひと押しとして活用してみてください。
端数切りを狙った交渉については、「【100万円以上トクする】新築マイホームを値切る3つのステップ」でも詳しく紹介していますので、ぜひご視聴ください。
値引きの結果だけで判断しない
値引きに成功したかどうかだけで、ハウスメーカーを決めるのは避けましょう。たとえ大きな値引きを提示されたとしても、施工品質やアフターサービス、保証内容に不安があるようでは、本末転倒になってしまいます。
値引きしてもらえるかだけにとらわれず、「本当に建てたい家はどのハウスメーカーで実現できるか」を念頭に置いてハウスメーカーを選ぶことが重要です。
営業担当者を味方につける
値引き交渉を成功に導くうえで、最も重要なのは営業担当者との信頼関係です。一方的に値引きを要求するよりも、「御社の商品に魅力を感じている」「御社で建てたいと思っている」という気持ちをしっかり伝えることで、担当者も「このお客様のために頑張りたい」と思ってくれるようになります。
たとえば、予算が限られていることを素直に話し、どうすれば希望のプランに近づけるかを一緒に考えてもらうスタンスで相談するとよいでしょう。営業担当者が味方になれば、値引きの調整やコストダウンの提案を積極的に行ってくれる可能性もあります。
値引き交渉以外で注文住宅の予算を抑える方法

注文住宅は値引きが難しい場合もありますが、それでも工夫次第で予算を抑えることは可能です。最後に、値引き交渉以外に実践できる具体的な方法を紹介します。
キャンペーンを利用する
1つ目は、ハウスメーカーが実施しているキャンペーンを利用する方法です。
ハウスメーカーでは、決算期前や新商品発売、周年記念などの節目に合わせて、さまざまな特典付きのキャンペーンを実施しています。内容は、建築費用の一部割引をはじめ、設備の無償グレードアップや人気のオプション追加プレゼントなど、多岐にわたります。
たとえば、通常なら数十万円かかる太陽光発電システムや床暖房といった高額設備が、キャンペーン期間中なら無料または値引きされる場合があります。このようなキャンペーンを上手に活用できれば、値引き交渉をしなくてもコストを下げられる可能性があります。
キャンペーンは事前告知が限定的なこともあるため、公式サイトやSNSなどを定期的にチェックし、気になるハウスメーカーがどんなキャンペーンを実施しているのか、こまめに情報収集しておくと良いでしょう。
ハウスモニター制度を利用する
ハウスモニター制度は、予算を抑えたい方にとってお得な制度です。
ハウスモニター制度とは、完成した自分の家を一定期間モデルハウスとして公開することを条件に、建築費を割り引いてもらえる仕組みのことです。一般的には、数十万円から100万円程度の割引を受けられます。
制度の内容はハウスメーカーによって異なりますが、完成後の住宅を見学会などで使用されたり、外観や内装の写真がパンフレットやホームページに掲載されたりする場合が多いです。特別な手間が発生するわけではないため、検討する価値があるといえるでしょう。
生活が始まる前に見知らぬ人出入りすることに抵抗がある方もいるかと思いますが、それさえ問題なければ、非常にお得な制度といえるでしょう。気になる方は、営業担当者にモニター制度の有無や条件について質問してみてください。
設計や間取りを見直す
理想の家づくりを目指す中で、設計や間取りにこだわりすぎて予算が膨らんでしまうことも珍しくありません。注文住宅のコストを抑える方法として、設計や間取りの見直しはとても効果的です。
たとえば、使用頻度が低い部屋や過剰に広い収納スペースなどは、本当に必要かどうかを冷静に再検討してみましょう。また、廊下の面積が多すぎる場合は、居室にその分を割り当てることで、無駄を削減しつつ使い勝手を改善できる可能性もあります。
間取りの見直しは、コストカットだけでなく将来的な暮らしやすさにもつながる重要なポイントです。間取りを見直したいという方は、「【厳選】間取りの失敗事例から学ぶ!後悔しない間取り5選!」もぜひチェックしてみてください。
オプションを見直す
注文住宅は、自分好みにカスタマイズできる反面、オプションの追加によって当初の予算を大きく超えてしまうことがあります。そのため、建築費を抑えるには、本当に必要なオプションなのかを見直すことが大切です。
たとえば、人気の高い食器洗い乾燥機や浴室暖房乾燥機なども、ライフスタイルによっては必要ない場合もあります。また、標準仕様で十分な設備にまでオプションを加えてしまうと、見積もり額はあっという間に上がってしまいます。
見直す際は、オプションに優先順位をつけて考えるのがおすすめです。絶対につけたいオプションなのか、「あったらよいな」と思うくらいのオプションなのかを精査していきましょう。
来客の多いリビングには少し費用をかけ、普段ほとんど使わない部屋は標準仕様で抑えるなど、メリハリをつけることも有効です。
補助金・助成金制度を利用する
国や自治体が提供している補助金・助成金制度をうまく活用すれば、費用を大幅に抑えられる可能性があります。特に近年では、省エネ性能や耐震性の高い住宅に対する支援制度が充実しています。
たとえば、長期優良住宅やZEH住宅と呼ばれる省エネ住宅を新築する場合、条件を満たせば補助金を受けられます。補助金を利用できれば、実際に支払う費用が数十万円〜100万円ほど安くなる可能性もあるのです。
また、子育て世帯や若年層向けの助成金制度を設けている自治体もあり、地域によってはさらに上乗せで支援を受けられる場合もあります。
ただし、制度には申請期限や受付枠があるため、早めの情報収集と申請準備が必要です。どの制度を利用できる可能性があるのか、どういった利用条件なのかなどは、ハウスメーカーの担当者に確認してみましょう。
長期的な支出を考慮する
注文住宅を計画する際には、建築時の初期費用だけでなく、住み始めてからのランニングコストも併せて考えることが重要です。
たとえば、断熱性や気密性の高い省エネ住宅は、初期費用は上がるものの、冷暖房費が抑えられるため、長期的には経済的です。太陽光発電システムも同様で、設置費用はかかりますが、電気代の削減や売電による収入につながる可能性があります。
目先の価格だけで判断せず、住んだあとの費用を含めて住宅建築の計画を立てることをおすすめします。
まとめ
注文住宅の値引き交渉は、決して不可能ではありません。適切なタイミングを見極め、現実的な交渉を心がけることで、コストダウンにつながる可能性は十分にあります。
ただし、価格だけにとらわれすぎると、本来重視すべき部分が見えにくくなるおそれがあります。たとえ大幅な値引きに成功したとしても、その代償として建物の品質が下がったり、施工後のフォローに不安が残ったりしては意味がありません。ハウスメーカーや営業担当者との信頼関係を大切にしながら、値引き交渉を進めましょう。
また、値引き交渉以外にも、コストダウンする工夫はできます。キャンペーンやハウスモニター制度、補助金などをうまく活用すれば、建築費を抑えられます。設計や間取り、オプションの見直しをして無駄を削減することも重要です。
上手に組み合わせることで、予算内でも満足度の高い家づくりを実現することが可能になります。
初期費用をできるだけ抑えたいという方には、「まかろにお【住宅価格高騰に備える!初期コスト大幅カット術10選】」の視聴がおすすめです。予算内で満足度の高い家づくりを目指すためのヒントが詰まっています。
「人から始める家造りの重要性を世に広める」をコンセプトとした住宅系YouTuber「まかろにお」が運営するYouTubeチャンネル「まかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】」では、注文住宅を建てるうえで知っておきたい知識などを定期的に発信しています。これから家づくりをする方にとって役立つ情報が満載なので、ぜひ参考にしてみてください。