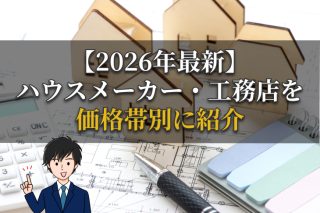この記事はメグリエ運営事務局によって作成しました。
注文住宅は、自由に設計できるという魅力がある一方、決めなければならないことが多く、どのような順番で計画していけばよいかお悩みの方も多いのではないでしょうか?
今回は、注文住宅の準備段階から引き渡しまでの流れに沿って、決めていくことを順番に解説します。注文住宅の建築計画を円滑に進めていくためのポイントも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
注文住宅で決めることの順番:準備期間
まずは、注文住宅の準備期間に決めることを順番に解説します。
決めること1:予算

まずは、予算を決めます。建物や土地に加え、外構工事などの諸費用を含めた総予算で考える必要があります。
自己資金のほか、住宅ローンをどの程度組むか、その返済計画も含めてバランスをとりながら資金配分を検討しましょう。金融機関のシミュレーターを使って借入可能額の目安を把握したうえで、早い段階で住宅ローンの事前審査を受けることをおすすめします。
事前審査に通っていれば、迅速に土地を購入でき、ハウスメーカーとの打ち合わせでも信頼性が高まります。
また、住宅以外にも生活費や教育費、将来のライフイベントに備える資金も確保しておく必要があります。目先のローン返済額だけでなく、長期的な視点で無理なく続けられる資金計画を立てることが重要です。
決めること2:ハウスメーカー

予算の目安が決まったら、次は注文住宅を建てるハウスメーカーを選定します。ハウスメーカーによってデザインや構造、価格帯などが異なるため、しっかり比較することが大切です。
各ハウスメーカーのホームページやSNSにある施工事例などを参考にすると、理想の家を具体的にイメージできます。また、耐震性能や断熱性といった基本性能、アフターサポート体制なども比較しましょう。
営業担当者の対応や相性も重要です。説明の丁寧さや提案力から、この担当者になら任せたいと思えるかがポイントです。
理想の住まいを提案してくれる担当者に出会いたいという方は、当サイト「メグリエ(MEGULIE)」への登録がおすすめです。「メグリエ(MEGULIE)」では、施工事例からお気に入りのプラン探しや、そのプランを手がけた有名ハウスメーカーの優秀な担当者に直接家づくりを依頼することが可能です。
また、「メグリエ(MEGULIE)」の会員登録時に、希望する住宅タイプや予算、詳細な要望など希望条件を登録すると、「メグリエ(MEGULIE)」に登録している有名ハウスメーカーや営業担当者からの提案を公募することもできます。
単に「家づくりが好き」というだけではなく、「時代を見据えた提案ができる」プロフェッショナルと直接コンタクトが取れるため、理想の家づくりを安心して進められます。また、万が一担当者が合わない場合でも、本社公認サービスとして担当者の変更が可能ですのでご安心ください。
チャンネル登録者数13万人以上の住宅系YouTuber「まかろにお」本人との無料相談も可能で、家づくりに関する疑問や不安を直接相談できます。サービスは無料で利用でき、無理な営業も一切ありません。ぜひご活用ください。
決めること3:土地

注文住宅を建てる土地を所有していない場合は、土地探しが必要です。
土地探しは、自分だけで行うのでなく、ハウスメーカーと一緒に行うようにしてください。なぜなら、土地には建築に関するさまざまな制約があり、土地の広さや形状、地盤の強度、法規制などによって、建てられる家の内容が左右されるためです。
不動産会社に土地探しを任せると、住宅の建築条件を十分に考慮せずに紹介されることがあり、あとになって「希望の間取りが入らない」「想定外の地盤改良工事が必要だった」といったトラブルに発展するリスクがあります。
また、注文住宅には、土地と建物以外に「諸費用」がかかります。
たとえば、2,000万円の土地に、坪単価100万円の建物を35坪で建てる場合、諸費用が1,000万〜1,500万円ほどかかる場合があります。つまり、最終的に必要な総額は6,500万円から7,000万円程度になる可能性があるのです。
この諸費用は土地によってかかる金額が変わり、専門家であるハウスメーカーに見てもらわないと、確定ができません。
こうした点から、土地探しは必ずハウスメーカーと一緒に行いましょう。
住宅系YouTuberの「まかろにお」が運営する「まかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】」内の「まかろにお 注文住宅を建てる場合、土地探しは自分でしてはいけない!」を観ていただくと理解が深められますので、ぜひチェックしてみてください。
注文住宅で決めることの順番:契約から着工まで
続いて、注文住宅の契約から着工までに決めることを順番に解説します。
決めること1:間取り
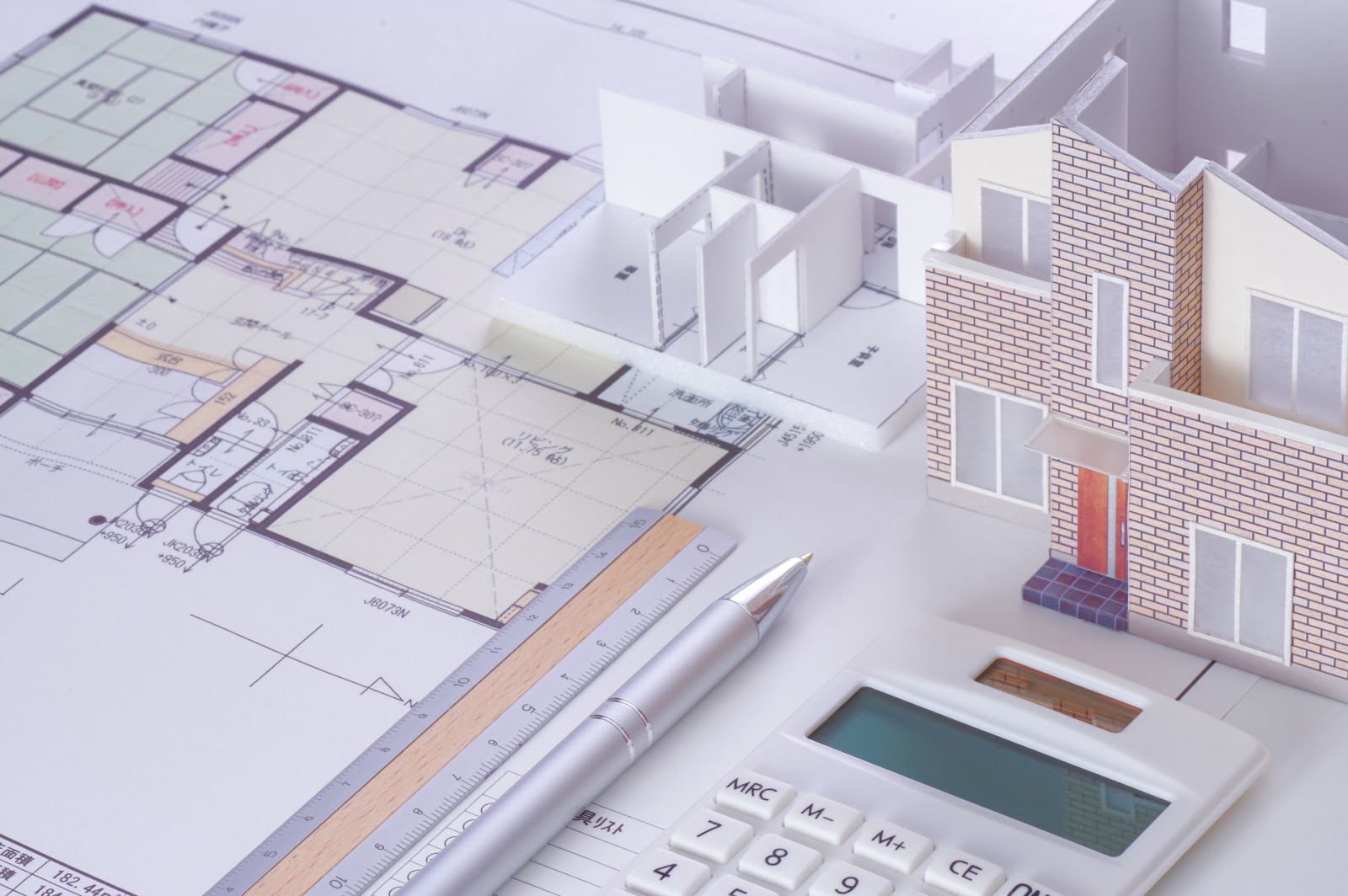
間取りを考える際は、家族のライフスタイルに合わせた設計が大切です。住み心地の良さは、部屋の配置や動線の快適さによって大きく左右されるためです。
どんなにおしゃれな間取りでも、動きづらければストレスがたまりやすく、住み始めてから不便さを感じます。そのため、家族の過ごし方や生活パターンを軸に、必要なスペースや動線を意識することが重要です。
たとえば、共働き世帯で家事の時間を効率化したい場合には、キッチンと洗面所を隣接させたり、玄関からキッチンまでの動線を短くすることで、家事導線のストレスを減らすことができます。
間取りを考える際には、現在の暮らしの中で不便に感じていることや、絶対に叶えたいと思っていることを家族で共有し、優先順位をつけて整理することがおすすめです。家族全員の希望をすべて叶えるのは難しいですが、優先順位をつけて、家族それぞれが使いやすい間取りをハウスメーカーに提案してもらいましょう。
間取りについてもっと詳しく知りたいという方は、「まかろにお【間取りはリビングが命】注文住宅で絶対クリアしたい重要ポイント10選」の視聴がおすすめです。
決めること2:内装

間取りが決まったら、床材や壁紙、ドアなどの内装を決めます。ハウスメーカーを決める際に、施工事例などを活用して、デザインのイメージを膨らませていると思いますが、それを具体的に形にしていく作業です。
「ナチュラルテイスト」や「北欧テイスト」など、理想のイメージをもとに、統一感を意識しながら色合いや素材を選んでいきます。
内装のカラーコーディネートでは、「ベースカラー」「メインカラー」「アクセントカラー」の3つに分け、それぞれの比率に従って決めるとまとまりやすいという基本ルールがあります。
| カラーの種類 | 比率 | 概要 |
|---|---|---|
| ベースカラー | 約70% | 壁や天井など、部屋全体を占める色。白やアイボリーなど、落ち着いた色が一般的です。 |
| メインカラー | 約25% | 家具や建具などに使う色。部屋の印象を決定づけます。 |
| アクセントカラー | 約5% | クッションや小物などに使い、部屋の雰囲気にメリハリをつけます。 |
上記のように、3色以内の配色にまとめると、統一感のある内装に仕上げることが可能です。施工事例などを見直しながら、理想の空間となるように内装を決めましょう。
おしゃれな内装にこだわりたいという方は、「まかろにお【保存版】オシャレな注文住宅はこうやって造ります。」の動画もチェックしてみてください。
決めること3:設備

内装が決まったら、キッチンや浴室、トイレなどの設備を決めます。水まわりは毎日使う場所なので、機能性やお手入れのしやすさ、家族のライフスタイルに合った使い勝手を意識して選ぶことが重要です。
たとえば、キッチンだけでも「I型」「L型」「アイランド型」などの形状から、コンロの種類、食洗機の有無、色の組み合わせなど、細かく決めなければなりません。調理をする人の身長や動線、収納の量など、実際の使い勝手をイメージしながら決めていく必要があります。
また、設備はデザイン性や機能を追求するほど、予算が大きく膨らみやすい傾向にあります。便利そうに見えても、実際には使わない機能がついていることもあるため、ショールームで実物を確認したり、他の人の使用感を参考にしたりしながら、本当に必要かをしっかり見極めることが重要です。
決めること4:外装・外構

外装・外構は、内装の雰囲気との統一感を意識して決めましょう。また、周囲の景観との調和も意識すると、周囲から見ても美しい外観にできます。
外構は家の完成間近になってから考えるハウスメーカーも多いですが、内装や間取りと合わせて検討することが非常に大切です。後回しにしてしまうと、すでに間取りや内装、設備に予算を多く使ってしまい、外構に十分な費用をかけられないという事態に陥る可能性があるためです。
たとえば、希望していたウッドデッキやカーポート、植栽などを諦めることになり、思い描いていた完成イメージとは大きく異なってしまい、後悔するという方も少なくありません。そのため、外構は内装に合わせ、早めに検討することが大切です。
しかし、早い段階から外構の提案を積極的にしてくれる営業担当者は多くありません。そのため、こちらから意識的に「外構も含めてトータルで提案してほしい」と伝えることが必要です。外装・外構は内装とセットで考えて、統一感のある家づくりを心がけましょう。
外構については、「まかろにお 失敗する外構の特徴と具体的な解決策【注文住宅】」で詳しく解説しています。
決めること5:電気配線

注文住宅の電気配線は、ハウスメーカーが提案してくれますが、家庭によって電化製品の数や使用する場所が異なりますので、具体的にイメージして決める必要があります。
電気配線は完成後に簡単に変更できるものではなく、使いにくいと感じても簡単には直せません。コンセントの数が足りなかったり、家具でふさがれてしまったりすると、生活の中で大きなストレスとなってしまいます。
たとえば、キッチンでは、電子レンジやトースター、炊飯器、ミキサー、コーヒーメーカーなど、日常的に使うものをリストアップし、作業動線を考えながらコンセントの数や位置を決めましょう。
そのほかにも、スマートフォンやタブレットの充電スペース、パソコン周辺機器の設置場所、テレビ裏の配線スペースなども忘れずに検討したいポイントです。
電気配線は暮らしやすさに直結する部分ですので、ハウスメーカーの担当者に任せたままにせず、時間をかけて検討することをおすすめします。
決めること6:その他
注文住宅の詳細が決まったら、他にも着工する前に決めなければならないことがあります。
地鎮祭

一つは、地鎮祭を行うかどうかです。地鎮祭は、建築工事の無事と安全を祈願するために、土地の神様にお祈りを捧げる儀式です。
地鎮祭は必須ではなく、ご家族や地域の考え方に応じて判断してください。実施する場合は、近隣の神社に依頼するか、ハウスメーカーに手配してもらうことが可能です。
近隣への挨拶回り

もう一つは、近隣への挨拶回りについてです。
工事が始まると、資材の搬入や工事車両の出入り、作業中の音など、少なからず周囲にご迷惑をかける場面が出ます。そのため、あらかじめ近隣の方へ一言ご挨拶をしておくと、トラブルの予防にもつながり、良好なご近所付き合いを始められます。
挨拶の範囲としては、両隣・向かい・裏手の住宅が基本ですが、接道状況や周辺環境によっては、少し広めに考えておくとより良い印象を与えることができます。また、挨拶に伺う際には、タオルやお菓子などの簡単な手土産を添えると、より好意的に受け取ってもらえることが多いです。
ハウスメーカーによっては、担当者が一緒に挨拶回りをしてくれる場合もあります。不安な方や、挨拶時にどのような説明をすれば良いか迷う場合は、事前に相談してみると良いでしょう。
ここまで決めたら、いよいよ注文住宅の着工に入ります。
注文住宅で決めることの順番:着工から引き渡しまで
注文住宅で決めることは、着工してからもあります。着工してから引き渡しまでに、以下のことを決めます。
| 決めること | 内容 |
|---|---|
| 火災保険 | 住宅ローンを利用する場合、火災保険の加入が義務付けられている場合が多いです。建物のみの保証か、家財も含めるか、地震保険をつけるかなど、補償内容をよく検討しましょう。 |
| 家具・家電 | 新居で使用する冷蔵庫・洗濯機・テレビなどの家電や、ベッド・ダイニングセットなどの家具を選定します。設置スペースや搬入経路の確認も忘れずに行ってください。 |
| 電気・ガス・水道などのライフライン | 引き渡しに合わせてそれぞれの開始日を決め、手配する必要があります。 |
| インターネット回線業者 | 工事が必要な場合もあるため、引っ越し日から逆算して、余裕を持って手続きをしましょう。 |
| 引っ越し業者 | 複数社から見積もりを取り、できるだけ早めに手配を済ませておくことをおすすめします。 |
| 引っ越し日・現在の住居の解約日 | 現在賃貸住宅にお住まいの場合、一般的には1ヶ月前の通知が必要です。家賃の二重払いを防ぐためにも、引っ越しとのタイミングを合わせて計画的に進めてください。 |
新生活に向けて、必要な手続きや日程調整を進めましょう。
注文住宅に関することを決めるときのポイント

注文住宅は自由度が高い反面、決めるべきことも多く、時間が足りないと感じたり、思ったように計画を進められないと感じたりすることも多くあります。最後に、注文住宅の建築計画を円滑に決めていくためのポイントを解説します。
家族で優先順位をすり合わせておく
注文住宅の計画は、家族で意見のすり合わせを行い、優先順位をつけておくことが大切です。希望やこだわりには個人差があり、すり合わせずに進めてしまうと、打ち合わせのたびに迷いや衝突が生まれやすくなるためです。
たとえば、「リビングは広くしたい」「収納をたくさん確保したい」「キッチンはアイランド型がいい」など、それぞれの理想があるかと思います。しかし、土地や予算の制約の中で、すべてを叶えることが難しい場合もあるのが現実です。
そうしたときに備え、「絶対に譲れない点」と「できれば叶えたい点」をあらかじめ明確にしておくと、優先順位がはっきりします。いざというときに判断がしやすくなり、プランの見直しも円滑に進められるでしょう。
家づくりは家族で長く暮らしていくための計画です。一人ひとりの意見を尊重しながら、家族全員が納得できる選択をできるよう意識することが大切です。
スケジュールに余裕をもつ
注文住宅の計画では、スケジュールに十分な余裕を持って進めることが非常に重要です。
計画が順調に進めば半年から1年ほどで家が完成しますが、実際には土地探しが難航したり、間取りや仕様の打ち合わせに想定以上の時間を要したりする場合も少なくありません。また、工事中に天候や資材の手配などで工程が遅れることもあるため、予定にゆとりをもたせておかないと、完成時期がどんどん後ろ倒しになってしまう可能性があります。
たとえば、「子どもの入学前までに引っ越したい」といった希望がある場合は、逆算して余裕をもって動く必要があります。焦って決断をすると後悔するリスクがあるため、注意が必要です。
余裕のあるスケジュールを組み、一つひとつの選択にしっかり向き合える時間を確保しておくことで、納得のいく判断ができ、理想の家づくりにつながります。
打ち合わせの記録を残す
注文住宅の計画は、営業担当者や設計士、インテリアコーディネーターなど、さまざまな立場の専門家とやり取りを重ねながら進めていかなければなりません。その分、伝達ミスや認識のズレが起こりやすく、思わぬトラブルにつながる場合があります。
こうしたトラブルを防ぐためには、打ち合わせ内容はしっかり記録しておくことが大切です。営業担当者と電話でやり取りした場合も、改めてメールやLINEに文章として残しておき、あとで見返せるようにしておくと安心です。
ハウスメーカーの営業担当者も、打ち合わせ時は記録を残すことが多いですが、電話での伝達だと記録しないこともあり、トラブルの原因となりやすいです。そのため、とくに仕様変更や見積もりに関する内容は記録しておきましょう。
また、疑問点や不安な点は、遠慮せずにその都度確認しておくことが重要です。小さな疑問でも早めに解消すると、トラブルを防ぎやすくなります。
注文住宅の完成後も営業担当者と良い関係でいるためにも、打ち合わせ記録を残し、認識のズレをなくしていくことが大切です。
まとめ
注文住宅の家づくりは、自由度が高い分、決めることが非常に多く、不安や負担を感じる方も多いでしょう。しかし、各ステップでやるべきことを整理し、順番に決めていくことで、不安を軽減しながら計画的に進めていくことができます。
準備段階では、まず無理のない予算設定から始め、理想の家に近づけるためのハウスメーカーや土地を慎重に選びます。契約後には、間取りや内装・外構、設備、電気配線といった細部の仕様を決定しましょう。
注文住宅の建築計画を円滑に決めていくには、家族での優先順位すり合わせをしておいたり、スケジュールに余裕を持ったり、打ち合わせの記録を残したりすることが重要です。本記事の内容を参考に、各ステップで一つずつ着実に決め、理想の家づくりをしましょう。
注文住宅を建てるうえで、もっと知識を深めたい方や、ハウスメーカー選びでお悩みの方は、『人から始める家造りの重要性を世に広める』をコンセプトとした住宅系YouTuber「まかろにお」が運営するYouTubeチャンネル「まかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】」の視聴がおすすめです。
大手ハウスメーカーやメガバンクで勤務してきたまかろにおの経験を活かし、忌憚ない意見を述べていることが特徴のYouTubeチャンネルです。2025年4月現在で登録者は約13万人を超え、住宅系チャンネルの中では最大規模です。
また、当サイト「メグリエ(MEGULIE)」は、まかろにおが運営している有名ハウスメーカー公認の注文住宅オンライン相談サービスです。単にハウスメーカー同士を比較・検討できるだけでなく、各社の優秀な営業担当者を紹介してもらえることが強みです。
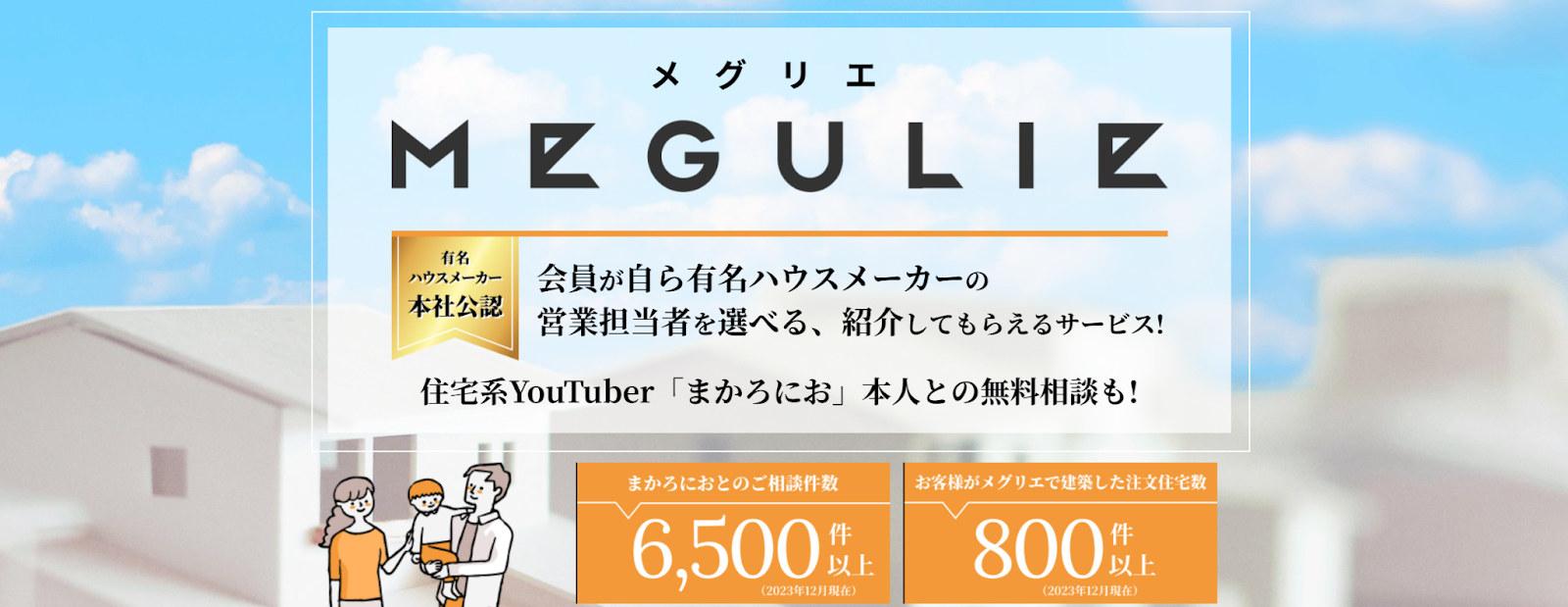
注文住宅の場合、営業担当者との相性で家の仕上がりや施主の満足度が大きく異なることも珍しくありません。「メグリエ(MEGULIE)」に登録すると、ハウスメーカーの営業担当者と直接コンタクトを取り、家づくりを依頼できます。
会員登録後のマイページTOPに「まかろにおに相談する」という項目が出てきます。希望すれば、まかろにおとWeb会議で相談が可能です。また、LINEで直接やり取りをして、気になることや不安を解消できます。公式LINEに登録すれば、相談以外にも限定セミナーの案内を受け取れるなど、さまざまなメリットがあります。
家づくりのためにより詳しい情報を集めている方は、ぜひ利用してみてください。無理な営業等は一切ありません。最後までまかろにおは中立的な立場でサポートしてくれます。
また、「メグリエ(MEGULIE)」に掲載されている豊富な建築事例から、お気に入りの事例を探し、施工を行ったハウスメーカーや営業担当者に依頼することも可能です。
なお、会員登録しなくても3つの質問に答えるだけで、まかろにおが現時点で施主に最適なハウスメーカーを診断してくれる「ハウスメーカー診断」が受けられます。会員登録を迷っている方は、まず「ハウスメーカー診断」を受けてみましょう。
家は高価な買い物であり、仕上がりに不満が残っても簡単に買いなおすことはできません。家づくりのサポートをしてくれる方がいれば心強いでしょう。