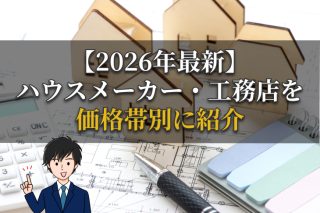この記事はメグリエ運営事務局によって作成しました。
注文住宅は、人生で最も大きな買い物の1つです。そのため、「年収はいくらあれば注文住宅を建てられるのだろう?」と疑問に感じる方は多いでしょう。
実は、年収がそれほど高くなくても、住宅ローンを活用することでマイホームを実現しているケースは少なくありません。「年収が低いうちに家を建て、長期間かけて返済していくのも一つの方法」と考える人も増えています。
今回は、注文住宅を建てるために必要な年収の目安や、年収別に組める住宅ローンの上限額について詳しく解説します。注文住宅を検討中の方は、資金計画の参考としてぜひ最後までご覧ください。
注文住宅を建てる世帯の年収
注文住宅を建てている世帯の中心は、世帯年収400万〜800万円の層です。国土交通省住宅局「令和5年度住宅市場動向調査報告書」によると、全国の注文住宅取得世帯の平均年収は808万円です。
最も多いのは、年収600万〜800万円未満(25.8%)、次いで400万〜600万円未満(22.9%)となっています。また、400万円未満でも8.3%の世帯が注文住宅を建てており、年収に関わらず家づくりが可能であることがわかります。
【全国版】
| 年収 | 割合 |
|---|---|
| 400万円未満 | 8.3% |
| 400万~600万円未満 | 22.9% |
| 600万~800万円未満 | 25.8% |
| 800万~1,000万円未満 | 19.1% |
| 1,000万以上 | 6.7% |
一方、東京・大阪・名古屋を含む三大都市圏では、世帯年収600万〜1,000万円未満がボリュームゾーンです。平均年収は924万円と全国より高く、これは都市圏特有の高年収層や土地価格の影響が大きいといえます。ただし、都市圏でも年収400万円未満で家を建てた世帯は5.3%存在し、工夫次第で実現できることが読み取れます。
【三大都市圏の割合】
| 年収 | 割合 |
|---|---|
| 400万円未満 | 5.3% |
| 400万~600万円未満 | 11.7% |
| 600万~800万円未満 | 21.1% |
| 800万~1,000万円未満 | 25.1% |
| 1,000万以上 | 8.8% |
なお、注文住宅取得世帯の平均年収は一見高く感じますが、これは「世帯年収」であり、夫婦共働きや子どもを含めた収入の合算によるものです。
たとえば、夫婦でそれぞれ年収400万円なら世帯年収800万円、夫が500万円・妻が300万円の場合も同様です。共働きが一般化した現代において、800万円程度の世帯年収は珍しい水準ではありません。
建てられる注文住宅の年収別の違い

注文住宅の予算は、世帯年収によって大きく異なります。一般的に、住宅ローンの借入可能額は「年収の6〜7倍」、手取り年収の場合は「8倍」が上限の目安とされています。たとえば、年収400万円の場合、手取りベースで約2,400万円が借入上限です。
また、注文住宅を依頼できるハウスメーカーは、建築費用に応じて次の3つに大別されます。
- ローコスト系:30坪の家が1,000万円台
- ミドルコスト系:30坪の家が2,000万円台
- ハイコスト系:30坪の家が3,000万円台
この基準をふまえ、年収ごとに選びやすいハウスメーカーや家づくりのポイントを解説します。さらに詳しいハウスメーカーの価格帯については、YouTubeチャンネル「まかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】」内にある「【最新2025年版】ハウスメーカーの注文住宅、規格住宅を予算別にまとめて解説してみました」を参考にしてください。
まかろにおは、大手ハウスメーカーの勤務経験を活かし、『人から始める家造りの重要性を世に広める』をコンセプトとした動画を配信している住宅系YouTuberです。中立的な立場で注文住宅に関する幅広い情報を発信しています。
世帯年収400万~500万円の場合
世帯年収400万円の場合、手取りは約300万〜340万円ほどです。住宅ローンの上限は2,400万円程度となり、ローコスト系またはミドルコスト系の一部が選択肢になります。
ローコスト系では、建売住宅や規格住宅が主力ですが、自由度が限られる反面、近年は一条工務店「HUGme(ハグミー)」のように100種類以上から選べるプランも登場しています。
年収500万円まで上がると、手取りは約375万〜425万円となり、ミドルコスト系ハウスメーカーの利用が現実的になります。ただし、オプション設備や外観・内装にこだわりすぎると、予算を超えるリスクも。希望を叶えるには、頭金を多めに用意するなどの工夫が必要です。
年収600万~800万円の場合
世帯年収600万〜800万円では、手取りの目安は次のとおりです。
- 年収600万円:手取り450万〜510万円
- 年収700万円:手取り525万〜590万円
- 年収800万円:手取り600万〜680万円
この年収帯では、4,000万円〜5,000万円台の住宅ローンが組めるため、ミドルコスト系だけでなく、ハイコスト系ハウスメーカーも選択肢に入ります。
ただし、自由度が高くなる分、間取りや設備、外観のデザインにこだわりすぎると、容易に予算オーバーとなる点には注意が必要です。無理のない資金計画を立て、必要に応じてハウスメーカーの担当者と相談しながら計画しましょう。
年収800万円以上の場合
世帯年収が800万円以上あれば、ハイコスト系ハウスメーカーを活用し、間取りや設備、性能にこだわった理想の住まいづくりが可能です。特に、オーダーメイドに近い自由度の高いプランを希望する方に適しています。
一方で、教育費や将来のライフイベントによっては、年収が高くても住宅予算に制約が生じる場合もあります。注文住宅は選択肢が豊富だからこそ、事前に予算の上限と内訳をしっかり決めておくことが、満足のいく家づくりのポイントです。
家の建築費別に必要となる年収

注文住宅の建築費に見合った年収の目安を知ることは、予算計画の第一歩です。建築費だけでなく、土地代や諸費用を含めた総費用を考慮する必要があります。一般的に、総費用のうち建築費が占める割合は約70〜80%です。
たとえば、土地1,000万円、建築費3,000万円、諸費用800万円の場合、総費用は4,800万円となります。また、国土交通省「令和5年度住宅市場動向調査報告書」によると、注文住宅の建築資金は、全国平均で4,319万円、三大都市圏では4,943万円です。
ここでは、建築費別に必要な年収の目安と家づくりの特徴を紹介します。
1,000万円台~2,000万円台の家を建てるために必要な年収
1,000万円台〜2,000万円台の注文住宅の場合、世帯年収が300万円台後半〜400万円台でも建築が可能です。この価格帯の注文住宅は、間取りや仕様に一定の制約はありますが、建売住宅と比べて性能面やアフターフォローが充実している点が魅力です。
3,000万円台の家を建てるために必要な年収
3,000万円台の注文住宅を建てるには、世帯年収が400万円台後半が現実的です。この価格帯になると、間取りやデザインの自由度が増し、理想に近い家づくりが可能になります。
ただし、設備やデザインにこだわりすぎると、予算オーバーになりやすいため注意が必要です。
4,000万円台~5,000万円台の家を建てるのに必要な年収
注文住宅の平均価格帯である4,000万円〜5,000万円台の家を建てるには、世帯年収500万〜600万円台以上が目安となります。夫婦共働き世帯であれば、無理なく到達できる年収水準です。
ただし、教育費や介護、老後資金など、家づくり以外にも大きな出費が見込まれる場合は、より高めの年収や、計画的な資金準備が必要になるケースもあります。
注文住宅を建てる際に組むローンの平均金額

注文住宅では、住宅ローンは多くの世帯が活用する重要な資金源です。実際に「2023年度 フラット35利用者調査」によると、土地付き注文住宅の平均借入額は4,171万円、建物のみの注文住宅では3,092万円となっています。土地価格は高額と思われがちですが、宅地相場は1,000万円台が一般的です。
また、借入額が年収の何倍に相当するかを示す「年収倍率」は、土地付き注文住宅で7.6倍、建物のみで7.0倍という結果です。多くの世帯が、年収の7〜8倍程度を目安に住宅ローンを組んでいます。
前述のとおり、ローンの上限は一般的に手取り年収の8倍程度が目安です。たとえば、年収400万円の世帯では、手取りが約300万〜340万円となり、単独でローンを組む場合は上限が2,400万〜2,720万円前後です。一方、夫婦でそれぞれ年収400万円なら、ペアローンを活用することで最大5,440万円の借入も可能です。
なお、返済期間が長いローンは月々の返済額を抑えられる一方、利息が増え総支払額は高くなります。また、年齢が上がるほど年収は増えやすいものの、完済までの期間は短くなります。これらを踏まえ、家を建てるタイミングやローン計画を慎重に検討しましょう。
ローンの借入額を上げる方法

物価高の影響で、注文住宅の建築費は近年上昇傾向にあります。特に、注文住宅はこだわりが反映されやすいため、予算が膨らみやすい傾向にあります。そのため、「もう少しローンの借入額を増やせないか」と考える方も少なくありません。ここでは、代表的な「借入額を増やす方法」を2つ解説します。
ペアローン:夫婦の収入を合算して借入額を増やす
ペアローンは、夫婦や親子など2人で1つの物件の住宅ローンを組む仕組みです。近年は共働き家庭が一般的となり、二世帯住宅などでは親子で組むケースも増えています。
この方法では、2人の収入を合算することで、単独より高額な借入が可能です。ただし、注意点もあります。
たとえば、出産・育児などで一時的に片方が働けなくなった場合でも、ローンの返済は減額されません。さらに、ペアローンの場合は団体信用生命保険(団信)の適用範囲が限定され、債務者が亡くなった場合も、その人が負担していた分のみが保険で返済されます。
そのため、特に妊娠・出産を予定している場合や、将来的に収入減少のリスクがある場合は、無理のない返済計画を立てることが重要です。
親子リレーローン:親子で収入を合算し、返済期間を延ばす
親子リレーローンは、親がローンの返済を始め、将来的に子どもがローンを引き継ぐ仕組みです。たとえば、親が50代、子どもが社会人になったばかりで、二世帯住宅や実家の建て替えを検討する際によく利用されます。
通常、高齢になると長期ローンが組みづらくなりますが、親子リレーローンを活用すれば、返済期間を長く設定でき、結果的に借入額を増やすことが可能です。
ただし、親子ともに安定した収入があることが前提となります。さらに、親が70歳を超えている場合や、健康状態によってはローンが組めないケースもあるため、事前確認が欠かせません。
加えて、兄弟姉妹が複数いる家庭では「誰がローンを引き継ぐのか」を明確にしておかないと、相続時にトラブルの原因となることもあるため注意が必要です。
注文住宅の価格を抑えるポイント
注文住宅はこだわりや選択肢が多い分、気づかないうちに予算オーバーしやすいという特徴があります。しかし、ポイントを押さえれば、予算内で理想の家を建てることも十分可能です。最後に、注文住宅の価格を抑える具体的な方法を解説します。
坪単価の低い大手ハウスメーカーの規格住宅を利用する
費用を抑えたい場合は、坪単価の低い「規格住宅」を検討しましょう。規格住宅とは、仕様やプランをあらかじめ標準化・大量生産することでコストを下げた住宅です。多くの大手ハウスメーカーが、コストパフォーマンスの高い規格住宅を展開しています。
ハウスメーカーの坪単価は、「まかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】」の「【2025年最新】大手ハウスメーカー坪単価ランキング」で確認できます。
一条工務店:HUGme
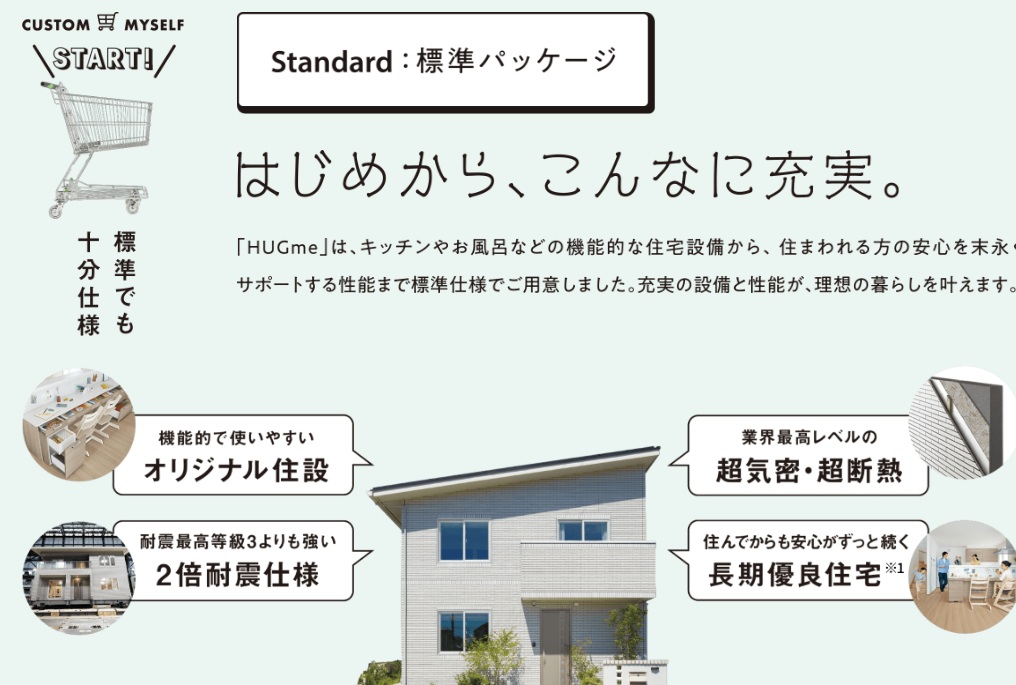
画像引用元:一条工務店
一条工務店が提供している「HUGme」は、100通りの選択肢がある規格住宅です。
一条工務店は「家は性能」をコンセプトとしているハウスメーカーです。通常の規格住宅ではオプション扱いになる設備が標準装備であり、アフターフォローも充実しているのがメリットです。価格を抑えつつ高性能の家を建てたい方に適しています。
三井ホーム:MITSUI HOME SELECT

画像引用元:三井ホーム
三井ホームの「MITSUI HOME SELECT」は、価格がはっきりしていて予算オーバーの心配がない、プロが厳選した間取りや外観をセレクトできるなどの強みを持っています。
自由度は低いですが性能は高く、ZEH住宅や長期優良住宅を建てたい方にも適しているハウスメーカーです。
ヘーベルハウス:my DESSIN

画像引用元:旭化成
ヘーベルハウスの「my DESSIN」は、「自由でゆとりある人生を支える、住み心地のよさがいつまでも続く家」をコンセプトとした住宅です。暮らしやすさに重点を置いた間取りや設備を設置できるのが強みです。
ヘーベルハウスは旭化成の住宅ブランドで、耐久性や耐震性の高さで知られています。その分、自由度が高い家は坪単価も高めのため、「ヘーベルハウスを利用したいけれど、予算が厳しい」と悩んでいる方は、検討してみてください。
デザイン面の工夫でコストダウンする
建築費を抑えるには、デザインの工夫が効果的です。
たとえば、片流れ屋根にする、ベランダを省略する、扉や窓の数を減らすといった方法があります。特にベランダは、設置だけで50万円以上、さらに維持管理費もかかるため、不要なら省くのも手です。
また、大きな窓やドアは開放感が出ますが、断熱性が低下し、冷暖房費にも影響します。営業担当者と相談しながら、不要な設備は積極的に見直しましょう。
デザインに関する工夫は、まかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】」内の「住宅価格高騰に備える!初期コスト大幅カット術10選」も参考になります。
外装デザインをシンプルにする
外装を「シンプル」または「シンプルモダン」にすることで、装飾を最小限に抑え、建築コストを削減できます。さらに、シンプルなデザインは流行に左右されず、築年数が経過しても古さを感じにくいというメリットもあります。
ただし、外壁は安易に安価な素材を選ばず、耐久性やメンテナンスコストも考慮して決めましょう。
外構費用をかけすぎない
外構(庭・塀・門・カーポートなど)も意外とコストがかかります。オープン外構にする、門やフェンスは後付けにする、庭づくりは段階的に行うなど、工夫次第で初期費用を抑えられます。
ただし、カーポートや目隠しなど、日常生活に必要な外構設備は削らないよう注意しましょう。
事前に予算上限を明確にし、営業担当者に伝える
予算を守るコツは「予算の上限」を事前にしっかり決め、ハウスメーカーの営業担当者と共有することです。オプションが豊富な注文住宅では、必要な設備・不要な設備を家族で整理し、優先順位を明確にしておきましょう。
特に「後付けが難しい設備」は優先して設置し、後から取り付け可能なものは将来のリフォーム時に検討するのも有効です。
「まかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】」内の「【損失500万以上】後悔する注文住宅オプション15選」も併せてチェックしておきましょう。
まとめ
注文住宅は、世帯年収500万〜600万円以上であれば選択肢が広がり、無理のない資金計画が立てやすくなります。とはいえ、共働きが一般的になった現在では、20代〜30代の夫婦でも収入を合算すれば、十分に注文住宅を建てることは可能です。その際は、ペアローンの活用も選択肢となりますが、万が一の収入減少時に備えたリスク対策も忘れてはいけません。
さらに、住宅の価格は、ハウスメーカーの選び方や建物の設計次第で大きく変わります。大手ハウスメーカーの規格住宅を選んだり、間取りやデザインを工夫したりすることで、限られた予算内でも理想の住まいを実現することができます。
注文住宅の家づくりは、資金計画や住宅ローン、ハウスメーカー選びなど、押さえるべきポイントが多くあります。これから家づくりを始める方は、まず「まかろにお【大手ハウスメーカー攻略法】」を参考に、相場や住宅ローンの基礎知識、ハウスメーカーごとの特徴をしっかりと把握しておくと安心です。