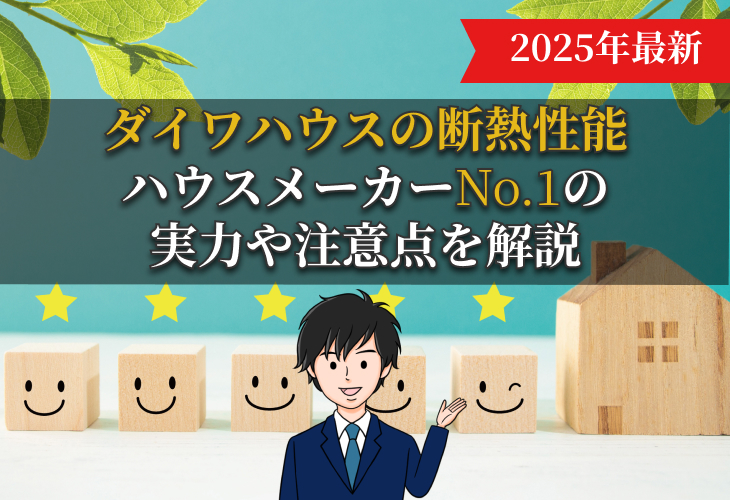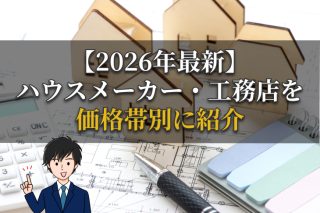別の記事で紹介したハウスメーカーの断熱性能ランキングで、1位がダイワハウスでした。
今回はダイワハウスの断熱性能は他のハウスメーカーと比べて特にどこがすごいのかについてお話していきます。
全体像から解説するので、断熱性能についてしっかり知識を得て、ハウスメーカー選びの参考にしていただければと思います。
断熱性能の全体像
ダイワハウスの断熱性能のすごさについてお話する前に、一旦全体像について整理してみます。
まず「断熱」と呼ばれるもの自体がなかなかイメージできない人が多い気がしていて「断熱って冬場に有効なものでしょ?」と考える方が非常に多いです。

断熱性能を高めるイコール冬場に対応するための性能という感じで捉えている現場の住宅営業マンの方も多いですし、なんとなくのイメージで「断熱」という言葉から冬場を想定する個人のお客さんも結構多いです。
断熱というのは、わかりやすくお伝えすると水筒です。

水筒に冷たいお茶を入れるとします。
そうすると、その冷たいお茶の温度がキープされます。
キープされるということは、要は水筒の中で保温されているということで、あとは外気、夏場はすごく熱いですが、それをシャットアウトしてくれているわけです。
中の気体・液体を保温する能力と外気の影響をシャットアウトする能力、この2つのことをかけ合わせて断熱と言っているのです。
ですので、冬場だけのものではなく、当然夏は夏の暑さをシャットアウトしてくれて、エアコンの効きをよくしてくれます。
冬に関しては、暖気を担保してくれるものであり、外の冷たい空気をシャットアウトしてくれるものということになります。
加えて、水筒も蓋を開けっぱなしにしていたら意味がありません。
蓋で密閉して初めて中の液体の温度が保たれると思いますが、この密閉性のことを「気密性」と言っています。
ですので、断熱だけよければいいわけではないのです。
「蓋を閉めようね」ということで、気密性能を高めるとは蓋を閉めるということなのです。
水筒を思い浮かべてもらえれば、断熱と気密はセットなものであって、2つあることによって1つの水筒の効果を発揮するということがわかると思います。
住宅も同じで、建物の断熱性能というのは、いわゆる水筒の能力がどれだけ優れているのか悪いのかという話で、まず蓋を閉めたとしても、そもそもの側の性能が悪かったら意味がありません。
ペットボトルがそうです。

いわゆる断熱性能がありません。
しばらくして中の液体が生ぬるくなったり、冬場だったら温かいお茶がどんどん冷たくなったりします。
側がしっかりしている上で密閉されることによって効力を発揮するので、まずはきちんと側の性能を高め、その上で密閉性を担保することが大切です。
まずは断熱をきちんと強化し、その上で気密を担保するという考え方で家づくりをやっていくのが非常に重要な考え方になります。
この考え方は、8割型理解していないのではないかと思います。

断熱性能の歴史
ハウスメーカーは今まで断熱というものを真剣に考えず、そこから逃げてきた歴史があります。
闇を感じます。
「断熱性能は上げなくていい」と言われていた
私が新卒だった2012年くらいの時は、住宅業界的に「断熱性能はほどほどでいい、そんなに上げる必要ない。それを上げるのはオーバースペックだ。」とよく言われていました。
先輩からも「断熱なんか上げなくていいんだよ。」とよく言われました。
「なんでだろうな?」と思っていたのですが、当時はネットも普及していなかったので、自分も最初はそういうものかと思っていました。

名だたる大手ハウスメーカーだったとしても「うちは断熱がしっかりしています!」と言いながら、家が建つと夏はとても暑く、冬はとても寒くて「これで十分とは言えなくないか?」という疑問は当時からありました。
一条工務店の登場
そんな中で登場してきたのが一条工務店です。
一条工務店は「家は性能」と言って、断熱性能が非常に優れていますという感じで当時から謳っていたハウスメーカーです。
今もその性能の高さは謳っていますが、やはり一条工務店が出てきて「一条工務店の家は暖房をつけなくても暖かい」「冷房がすぐ効いて涼しい空間になりやすい」というのは当時としては驚きでした。

ただハウスメーカー各社は「一条工務店がやってることはオーバースペックだ。やる必要ない。日本は夏は暑くて冬は寒い、それが文化だ。」というように言っていました。
昔の日本の家は、夏は窓を全開にして風通しを良くして暑さをしのぎ、冬は寒いけれどとにかく耐え忍ぶというような文化で生きてきた国なので、その文化を大切にするなら「夏は暑くて冬は寒いのは当たり前」くらいの感覚だったのです。

ですので、断熱性能を上げる必要性はないとなっていたのです。
断熱等級7の新設
国の基準で、当時は断熱等級4が最高でしたが「うちのハウスメーカーは断熱等級4が取れているから最高の家。国が認めてるんだからこれ以上やる必要ない。」そういうロジックでお客さんに説明して、断熱等級を上げてこなかったわけです。

ただ「さすがにこれじゃまずいよね」ということになり、2022年10月に断熱等級7が新設されて、3段階もグレードが上がりました。
ようやく海外に追随する性能の家を日本でも建てられるようになったのが、つい3年前くらいです。
20年間くらい横暴な営業トークをし続け「国が断熱等級4を制定していてそのマックス数値を取れているわけだから十分です。」とひたすら言い張ってきたのです。
「断熱等級はほどほどでいい」「断熱は考えなくてもいい」という変な文化がつくられてしまっているのです。
そのため、ハウスメーカー各社で断熱気密の話をするとアレルギー反応を起こして、考えたくない、聞きたくないと思ってしまう方が非常に多いです。
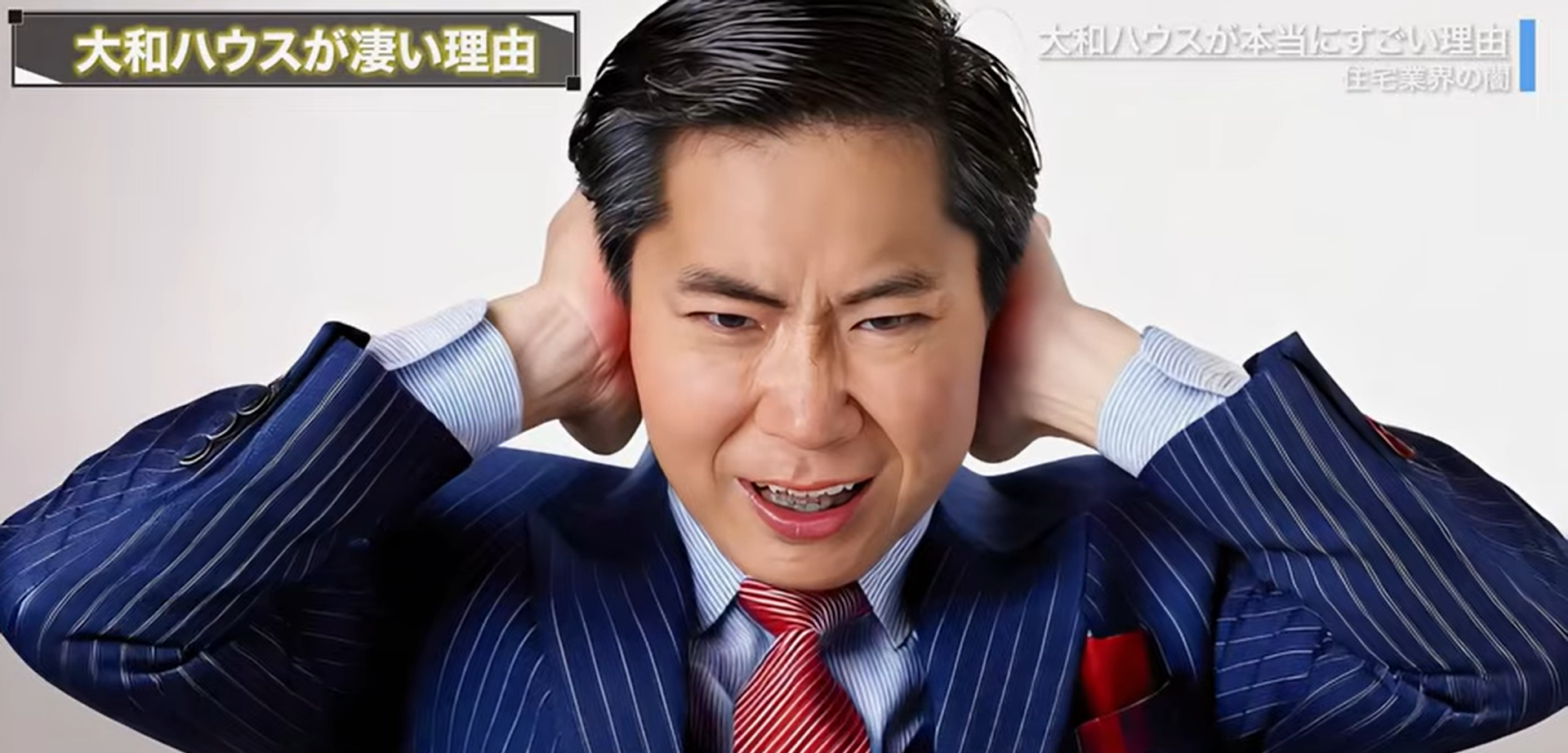
UA値での断熱等級の判断
今現在は形を変えて定着しています。
どういうことかというと、今は「断熱等級6標準です。」と謳っているハウスメーカーが多いのですが、これは「なんちゃって断熱等級6」の可能性があるのです。
断熱等級は何で判断するのかというとUA値という数値を算出して、その上でこの建物は断熱等級5・6ですと決めているわけです。
UA値は言葉で聞くとすごくわかりづらいのですが、小さいAの方はアベレージ、平均値という意味なのです。
屋根・壁・床下、この3つの平均値で断熱等級が判断されるのですが、一部だけ良くすれば平均値はよくなるわけです。

屋根だけ断熱材を厚くして、壁や床下がペラペラでも「断熱等級6です。7です。」と言える可能性があるのです。
実際そういう例は結構あります。
断熱等級6ですと言っていても、一番スペースに空きがあるのは屋根裏で、あそこはただただ空いているスペースなので、そこに断熱材をもりもり詰めればいいやという感覚で、平均値をよくしているのです。
そもそもハウスメーカーという企業の業態自体が戦後から続く「住宅の大量生産をする企業」なわけです。
大量生産をする企業なので、平均点80点くらいを取れればいい、という感覚で商品を展開しています。
ハウスメーカーがやっていることは、住宅をなるべく安く、そしてある程度の品質のものをとにかく量産するという軸からブレた活動ではないわけです。
ですので、別に一部分だけ断熱性能がよくて、天井だけ断熱材がもりもりで、それ以外がペラペラだったとしてもいいわけです。
ハウスメーカーがやっていることというのは、住宅の大量生産、それなりのものを世に一斉に大量に普及するのが目的なので、別に悪いことではないのです。
しかし、もう戦後から明けて何十年も経っているので、そこら辺のハウスメーカーの成り立ちというところは、知らない人が多いです。
知らない人からすると「そんな家づくりおかしくない?」となるのは、確かに気持ちとしてはわかります。
ダイワハウス全部の断熱性能がいいわけではない
過去の歴史やハウスメーカーの裏の実態を含めても、ダイワハウスは「断熱性能が高い」と言われていますが、ダイワハウスが全部断熱性能がいいかと言われれば、そうではありません。
具体的にダイワハウスには、鉄骨の商品「ジーヴォシグマ」と、木造の商品「グランウッド」の大きく分けて2種類があります。
厳密に言えばビーウッドという商品もあるのですが、それは一旦省いておき、基本木造と鉄骨の2つがあります。
大和ハウス工業というくらいなので、やはりダイワハウスも基本的には「安く、それなりの品質のものを大量生産する」という軸足は変わっていないわけです。
鉄骨の方はリサイクルスチールを使っており、これは溶かして再利用することができます。
ですので、鉄骨の方が生産コストが安いのです。
そういった観点から「量産型の住宅をつくる」というところで、ジーヴォシグマをそれなりの性能、一定の質で量産する体制を整えているので、ダイワハウスの鉄骨づくりで家を建てようと思うと、断熱性能を上げるのに限界があるというのは実態としてあります。
断熱等級7を取れるダイワハウスの仕様
木造住宅に関しては結構力を入れていて、5段階選べる断熱性能があり、1番上の「ウルトラダブル断熱」を選ぶと、今国が定めている最高等級の断熱等級7を取れる仕様まで上げられます。
この断熱等級7を取れる仕様は、一条工務店とダイワハウスくらいしか有名どころではつくれないのではないかというくらい、市場優位性があります。
ですので、量産型住宅の中で質を高めていくことを考えるなら、ジーヴォシグマにも何段階か商品形態があるので、上の商品を選ぶ、価格に合わせて、自分たちの財布に合わせて一番下のランクを選ぶ、中間くらいを選ぶなど、その辺の調整をしてもらえればと思います。

より断熱性能を高くして、細かくつくり込みたいという方であれば、量産型の鉄骨住宅ではなくて木造住宅、つまりジーヴォグランウッドを選んでもらうといいかと思います。
ジーヴォグランウッドですと、予算に応じて5段階くらい断熱性能があるので、好きな断熱性能を選んでもらい、より追求したいという方は、一番上の「ウルトラダブル断熱」を選んでもらえば、今日本でできる最上級の性能の家が建てられるのではないかと思います。
ただ、値段はプラス400万くらいで、結構高いです。
ダイワハウスで現実的に断熱性能を上げるなら部分強化
現実的に断熱性能を上げていきたいと思ったら「部分強化」というのがおすすめです。
これがどういうものかというと、ダイワハウスの「ウルトラダブル断熱仕様」の断熱材を一部転用するという考え方で、例えば、床下部分だけウルトラダブル断熱にする、壁だけウルトラダブル断熱にする、天井だけウルトラダブル断熱にするといったように、部分的に強化ができるのです。
ですので、予算に応じて部分的に強化をするのが得策かなと思っています。
優先順位的には、最近夏が長いので、まず屋根を最初に強化して、その次に床下、最後に壁という順番で部分的に強化していくのがいいのかなと思います。
あと、ウルトラダブル断熱は「クリプトンガス」というのが入っているガラスを標準で使っています。
このクリプトンガスは、昨今の情勢の影響もあり、希少価値が上がり、非常に価格が高くなっています。
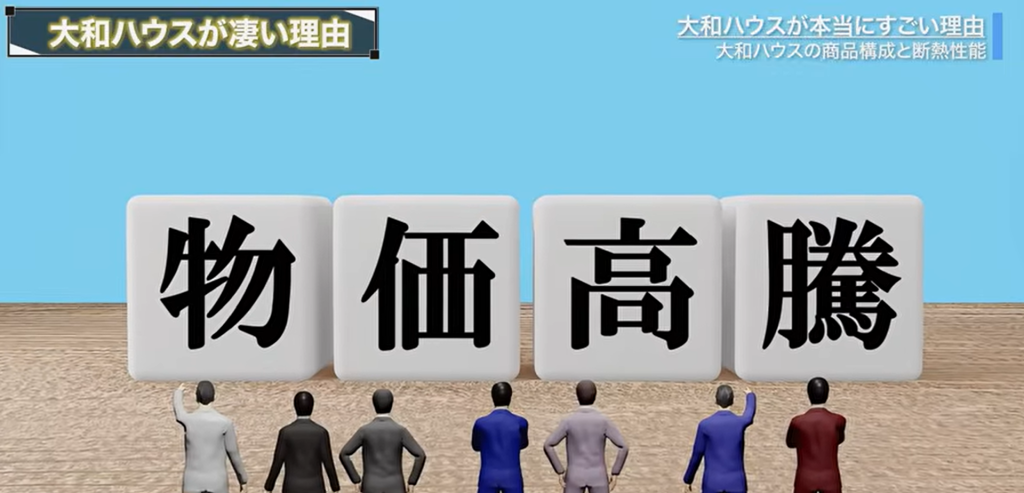
このクリプトンガスの仕様からアルゴンガスに変更するだけで、200万円ぐらい金額が落ちます。
クリプトンガスからアルゴンガスに変更すると若干断熱性能が落ちますが、断熱等級はガグっと下がることはないですし、性能値も極端にガクっと下がるわけでもないので、クリプトンからアルゴンに変えて200万円落とし、その200万円でもきついなということであれば、部分的な断熱の強化で優先順位としては屋根、床下、壁という順番で強化を考えていくと、ある程度コストバランスを調整することができます。
本当は全部強化するのがベストですが、予算の強弱をつけなければならないとなってくると、どうしても優先順位をつけなければならないので、やはり日射の影響を一番受けやすい屋根をどうカットするのか、特にハウスメーカーは屋根断熱というつくり方ではなく、天井断熱というつくり方になっていることが多いので、なおのことやはり太陽光の熱をなるべくカットするというつくり方にした方が快適は快適なわけです。
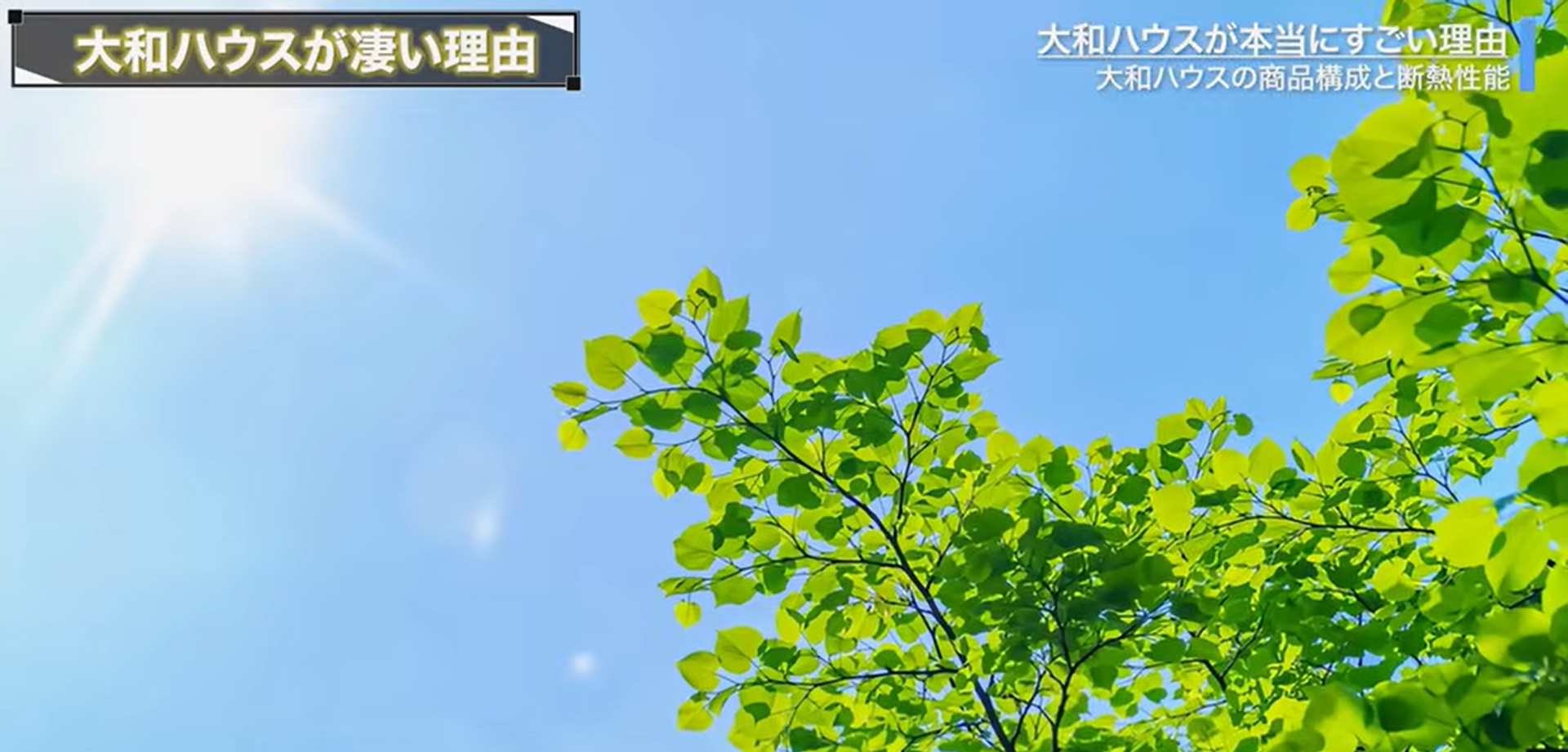
とにかくハウスメーカーは、安く大量生産をする前提でつくられているので、なるべくコストがかからない天井断熱というつくり方になっているわけです。
天井断熱は安いけれども、断熱性能は屋根断熱に比べていまいちという特徴があるので、そこはやはりコスト優先で天井断熱になっているのを、弱点を補うためにはどうしたらいいかと言ったら、天井の断熱材を厚くする必要があるので、そこは最優先でやってもらいたいです。
あとは他の断熱に関してちょっとな…というのはわかりますが、断熱はあくまで中の空気を保温するための能力で、外気を遮断するための能力なので、例えば住宅密集地である程度家に囲まれているところは、家の外壁に直射日光がガンガン当たるわけではありません。

周りの家が日差しをカットしてくれます。
ですので、思っているほど壁が影響を受けないんじゃないか説があります。
床下に関しては床下断熱といって、基礎の中を換気させる、これを白アリに強いつくり方にするために基礎の中に外気を通すというつくり方をしていて、冬場は冷たい空気がバンバン基礎の中に入ってくるので、日差しなど関係なく、どうしても床下が冷たくなるわけです。
少しでもその冷たさを緩和するためには、床下の断熱材を厚くする必要があります。
昨今少し冬場の期間が短くなっているというのもあるので、屋根が1番で床が2番、壁が3番でいいのではないかと思います。
ダイワハウスの注意点
ダイワハウスも完璧ではないので、注意点もあります。
それが何かというと、ダイワハウスはどこまで行っても鉄骨推しのメーカーだということです。
やはりハウスメーカーは戦後から始まる住宅の大量生産をやっていて、大和ハウス工業というくらい、やはり鉄骨住宅をずっとメインで売ってきた企業なので「木造はダメ、鉄骨が最強」という文化が脈々と受け継がれている状態なのが今のダイワハウスです。

ですので、これから家を建てる人が一生懸命勉強してダイワハウスに「木造で建てたいです。」と言っても木造を提案してくれないことが多いのです。
「鉄骨でも十分ですよ。」と言って知らない間に鉄骨住宅を提案されてしまいます。
あとは、そもそも木造住宅を設計できない場合があります。
これがどういうことかというと、住宅は2つの寸法基準があり、1つ目が尺モジュールという寸法、もう1つがメーターモジュールという寸法、この2つです。
尺モジュールというのは910mm×910mmのマスを積み上げて設計していく方法で、メーターモジュールはメーターというだけあり1m×1mのマスを積み上げて家づくりをしていく方法なわけです。
わかりやすく言うと、例えばトイレは2マスでつくっていきます。
ですので、尺モジュールでつくった場合、91cm×91cmのマスを2つ積み上げてトイレという空間をつくるので、横幅91cm、奥行き182cmになるわけです。
これで尺モジュールのトイレの空間ができます。
メーターモジュールの場合も、2マス積み上げてトイレをつくりますが、メーターなので横幅1m、奥行き2mになります。
ですので、同じトイレという空間をつくっても、尺モジュールの方が一回り小さいトイレになり、メーターモジュールの方が一回り大きい空間になるわけです。
こういう寸法の基準があります。
ダイワハウスが今までずっと推してきたジーヴォシグマという鉄骨商品は尺、グランウッドはメーターです。
ですので、寸法基準が違います。
今まで尺で設計していた人がメーターにすると、全体的に一回り空間が大きくなってくるので感覚がおかしくなり、設計できないのです。
逆はできます。
メーターですと小回りを効かせたような設計になってくるので、メーターで設計慣れしている人は尺でも設計できるのですが、尺に慣れている人がいきなりメーターをやるとできません。
そういうこともあり、ダイワハウスで「グランウッドで提案してください。」と言っても、メーターの設計ができない、そもそもやはり鉄骨を売ることが正義だと思っているので、鉄骨住宅になってしまうことが多いです。
一応そういう現状にダイワハウス本社も「どうしたもんかな」と考えて生まれたのが、実は「ビーウッド」という商品です。
ビーウッドという商品に関しては、やはり現場がメーターモジュールのグランウッドを設計できないため、本社が尺モジュールに対応した商品を出したというものなのです。
ビーウッドであれば尺モジュールで設計できるので、現場も対応しやすいはしやすいです。
だけれども、現場としては「鉄骨を売ることが正義」となっているので「木造なんて…。」と思っている営業マンに当たってしまうと「鉄骨でも大丈夫です。」と言われて、鉄骨になってしまいます。
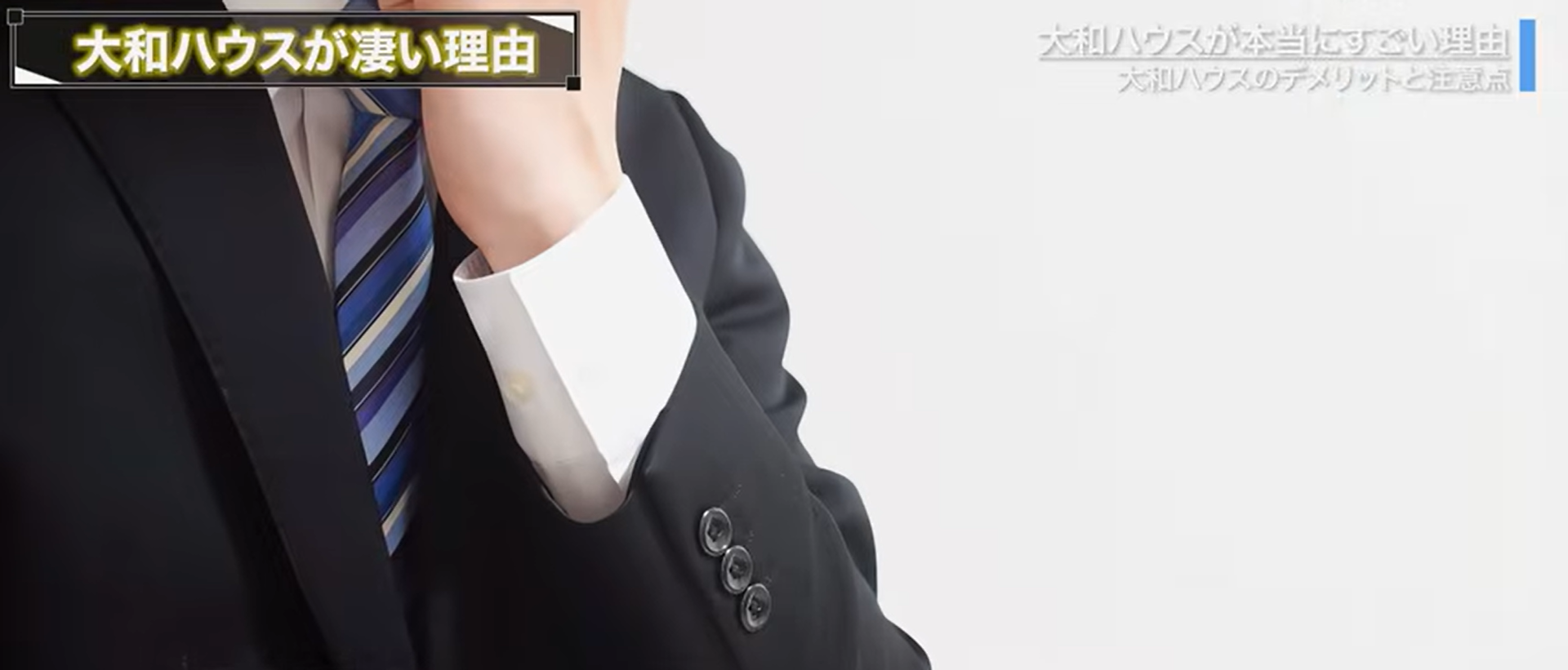
あとビーウッドですと、やはり尺なので、柱の大きさがメーターと違って細いです。
1mと91cmです。
柱の太さが違うということは、壁の厚みが違うわけです。
そうすると入れられる断熱材の厚さが違います。
ですので、ビーウッドに関しては、選べる断熱仕様が3段階しかありません。
グランウッドは5段階あります。
そういう意味で制限がかかってくるというか、若干商品の見劣りさがあるというのがビーウッドではあります。
「積水ハウスみたいな家、グランウッドでも建てられるじゃん!」というように思って、しかも「断熱等級7を取れるんだったら最強じゃない?」ということから「ダイワハウスを検討したいです。木造で家を建てたいんです。」という人は多いです。
しかし、知らない間に鉄骨になっていることは多いのです。
そこは、デメリットかもしれません。
いい人だったり、そもそも木造の設計が得意な人だったり、そういう人に出会えたらスルッと進んでいくのでいいですが、そこは難しいところです。
ダイワハウスの木造は昔、子会社でした。
子会社だったのでやはり本社の方が偉い、子会社の方が下というようなヒエラルキーがある中で途中から合併して一緒の会社になりました。
ですので、やはり社内的な感じでも「木造は下」「鉄骨が上」「鉄骨を売る人の方がすごい」「木造なんかダメ」というのがどうしてもあります。
そういうこともありなかなか難しいところではあるのですが、商品だけ見たら「いいよ」という話です。
ダイワハウスの断熱性能のまとめ
今回はダイワハウスの断熱仕様についてお話をさせていただきました。
基礎中の基礎として、やはり「断熱はしっかりと厚めに確保する」これがもう大前提です。
断熱が薄いのはありえません。
厚めに確保するのは重要なのですが、その中の一つの手段として、ダイワハウスのウルトラダブル断熱など、特に木造系は大手ハウスメーカーの中では断熱材が厚めに入っているので、そこを優先的に検討してもらうのは非常にアリかなと思います。
ただフルマックスで強化してしまうと金額がすごく上がるので、厳しいなということであれば部分強化など、その建てる立地などに合わせてカスタマイズを加えていただくといいかもしれません。
あとは、本当に「いい人に巡り合いましょう」というところがポイントになるかと思います。
最後に告知です。
今現在、公式LINEに登録をしていただくことで、全国の優秀な住宅営業マンや設計士のご紹介、大手ハウスメーカー攻略カタログのプレゼント、これらの特典を受けることができます。

また、私が作った自ら担当者を選べるネット版住宅展示場メグリエに登録をしていただくと、無料で私との個別面談ができるようになります。
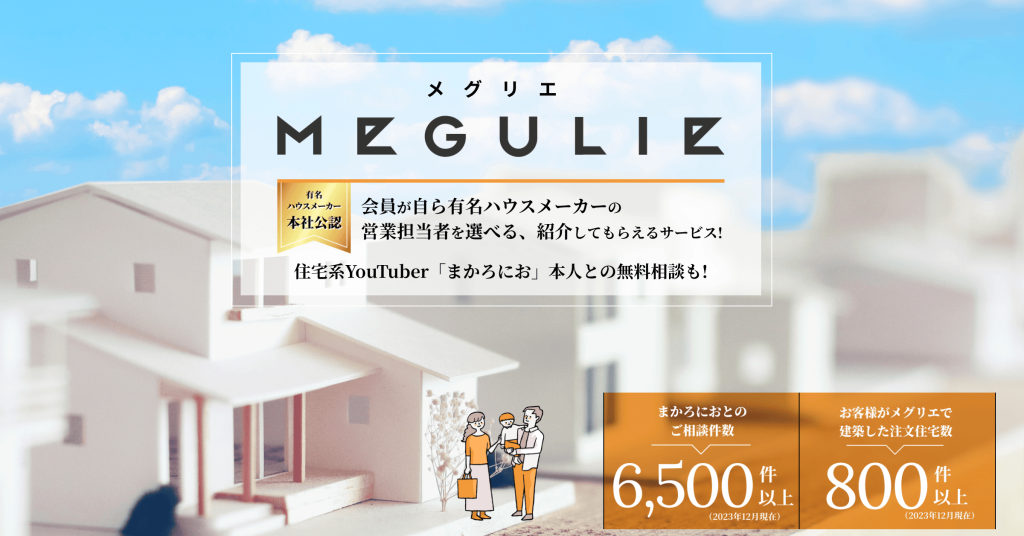
各ハウスメーカーの弱点や比較ポイントを知りたい、注文住宅を買いたいけれど何から始めればいいのかわからない、最短で自分にあったハウスメーカーを知りたい、これらに該当する方はこの機会にぜひ公式LINEとメグリエの登録を済ませておいてください。